UnsplashのJonas Schöneが撮影した写真
痛みとともにある、本当の“心の安らぎ”
“Peace Of Mind(心の安らぎ)”と聞くと、穏やかで優しい音楽を思い浮かべる人も多いだろう。けれど、稲葉浩志が描く“安らぎ”は、決して一面的ではない。
このアルバムに流れているのは、癒しだけではなく、怒りや焦り、孤独や葛藤といった複雑な感情だ。それらを否定せずに受けとめ、その先にようやく見えてくる静けさ─それこそが“心の安らぎ”として描かれている。
「今のままでもいい」と安易に慰めるのではなく、言葉にならなかった思いを少しずつ拾い上げ、自分の感情に名前を与えていくようなまなざしが、この作品全体を貫いている。
“Peace Of Mind”とは、問題のない完璧な状態を指すのではない。むしろ、痛みや迷いを抱えたままでも、自分の心と折り合いをつけながら歩んでいく─そのしなやかさこそが、本当の安らぎなのだと思う。
ここには劇的な感動や即効性のある希望はない。それでも、気づけば自分の気持ちに静かに戻ってこられる。このアルバムに流れる時間は、そんな感覚をそっと思い出させてくれる。
そして、このアルバムを聴くことで、誰かの正しさに従うのではなく、自分の声に静かに耳を澄ますという選択─その意味を、そっと思い出させてくれる。
Release:2004.09.22
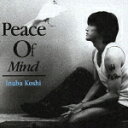
※本記事では、稲葉浩志のアルバム『Peace Of Mind』に収録された各楽曲について、歌詞の一部を引用しながら、その表現やメッセージについて考察しています。引用にあたっては、著作権法第32条に基づき、正当な範囲での引用を行っております。
表現される感情
【気楽】×『おかえり』
日々の暮らしには、小さな疲れや、言葉にならない孤独が潜んでいる。
誰かに気をつかいすぎた日。うまく笑えなかった日。そんな帰り道に、「おかえり」と迎えられる情景を思い浮かべるだけで、心がふっとほぐれていく。
稲葉浩志の3rdアルバム『Peace Of Mind』の1曲目「おかえり」は、そんな日常の揺らぎに静かに寄り添う一曲だ。
「笑っておかえりなさい」という冒頭のフレーズは、迎えるだけでなく、また歩き出す人への小さなエールとして、そっと響いてくる。
「オミヤゲは今度でいいから」「オマモリはカバンに入れて」—無理に結果を出さなくていい。ただ無事でいてくれればいい。そんなささやかな願いが、飾らない言葉のなかにやさしく宿っている。
アコースティックギターを軸に、そぎ落とされた音の配置が、歌と言葉の輪郭をやさしく際立たせる。
アルバム『Peace Of Mind』という名の扉を開くことで、この曲は、聴く人のなかにある“帰れる場所”と、“もう一度進む力”を静かに思い出させてくれる。
「行こう」ではなく、「おかえり」から始まる—その静かな始まりにこそ、このアルバムが大切にしている心の安らぎの本質が滲んでいる。
音楽に迎えられる場所─『おかえり』から始まる、心の安らぎ
冒頭のサビから伝わってくるのは、励ましでも慰めでもない、そっと背中に手を添えるような、小さなやさしさだ。
笑っておかえりなさい オミヤゲは今度でいいから
太陽に 均かれながら
ともに いさぎよく いきましょう
何かを背負わせるでもなく、何かを期待するでもなく、“また戻ってこられる場所がある”という静かな信頼がそこにある。
押しつけのない言葉と、そぎ落とされた音の隙間が、人と人との健やかな距離感を美しく描いている。
A〜Bメロでは、現実の不安や息苦しさを、まっすぐにすくい取っていく。
何が起きるか?見当もつかないよ
ほらひびいてる 驚告のベル
昔も今も それはいっしょだろう
この星の現状 どこだって戦場
眠る前には あなたを想うよ
「どこだって戦場」と語られる世界は、何も大げさな比喩じゃない。私たちはそれぞれの場所で、自分なりの闘いを続けている。
けれど、そんな日々のなかでも、誰かを想うその気持ちが、自分を今日もここに立たせてくれている。自分をまた一歩前に進ませてくれる。
そのぬくもりが、このパートの奥深くに、静かに流れている。
現実の不安や、言葉にならない葛藤に触れたあとのサビは、深呼吸をしてから、また“自分の場所”へ戻ろうとする気持ちに寄り添ってくれるようだ。
笑っておかえりなさい オマモリはカバンに入れて
雨には うたれながら
ともに いさぎよく いきましょう
日々の中で感じた痛みも、迷いも、無理に片づけなくていい。問題を抱えたままでもいい。
雨に濡れながら歩くようなその情景は、強さや明るさではなく、静かな再出発に必要な余白と、寄り添いの温度を教えてくれる。
この曲は、何かを変えようとする音楽ではない。変わらない日々の中で、ふと立ち止まりたくなる瞬間に、そっと寄り添い、ただそこに在り続ける音楽だ。
『おかえり』レビューまとめ
少し疲れたときも、言葉にならないまま抱えてきた気持ちも、すべてを受け止めようとはしない。けれど、そっと隣を歩いてくれる。
「おかえり」は、単に戻るための言葉ではないのかもしれない。自分のリズムを取り戻し、もう一度歩き出すための、小さな合図なのだろう。
そんな音楽が、アルバム『Peace Of Mind』の最初に置かれていることに、きっと意味がある。

【満ち足りている】×『Wonderland』
3rd Single
Release:2004.07.14
稲葉浩志のソロシングル「Wonderland」は、タイトルの軽やかさとは裏腹に、人間関係の奥深いテーマを突きつけてくる一曲だ。
歌われているのは、他人を変えようとする傲慢な姿勢─“正しい”と信じた価値観を押し付ける自身の姿である。
しかし物語はやがて転じ、説得するつもりだった自分の言葉が空回りするうちに、むしろ自分の信じてきたものの脆さに気づかされていく。
サビで描かれる「影が光に変わり、醜さが美しさへと反転する世界」は、その瞬間を鮮やかに示している。押し付けではなく、相手の世界をそのまま受け入れることの大切さを、キャッチーなメロディにのせてリスナーの胸に刻み込むのだ。
物語の結末では、主人公が一度は無価値だと切り捨てたものを大切そうに抱え、自然体で笑う相手の姿が浮かび上がる。そこには“価値観の逆転”の真理がある。自分にとってはガラクタにしか見えなかったものが、誰かにとっては確かな輝きを放つ─そんな当たり前の事実に気づかされる瞬間だ。
「Wonderland」は、価値を押し付けることの虚しさと、他者の視点を受け入れることの豊かさを同時に伝えてくれる。聴き終えた後には、日常に転がる“ささやかな宝物”の存在までも愛おしく思えてくるだろう。
『Wonderland』が描く、価値観
冒頭のAメロで浮かび上がるのは、すべてを自分の価値観という物差しで測ろうとする主人公の姿だ。
ねぇ 扉を閉ざして そこから動かないのは
臆病者のやることだと 信じて疑いもしなかったんだよ
君を変えてやろうなんて はずかしく思いあがり
まるで天国かどこかに 導くように話しかけていた
閉ざされた扉を目にして、それを“臆病”と断じ、相手を変えようとする。だがそれは、あくまで自分から見た一方的な解釈にすぎない。
そこには、自分の価値観こそが正しいと信じて疑わず、相手を“導こう”とする傲慢さがにじんでいる。
この描写は、人間関係におけるすれ違いの始まりを象徴している。相手の世界を理解しようとする前に、自分の「正しさ」で相手を動かそうとする。
誰もが心のどこかで思い当たるその感覚を、鮮明な言葉で掬い上げている。
Bメロでは、自分の内側に突きつけられる違和感と苛立ちに直面する。
顔を見るたび あせっていらいら
見当違いの使命感を抱いて
いったい僕はナニサマなんだ
ああ ほんとに馬鹿みたい
相手を見て苛立つのは、結局その姿に自分の未熟さを映し出しているからだ。
強い使命感に駆られていたはずなのに、それは実は見当違いで、相手のためではなく自分を安心させるための“正しさ”にすぎなかった。
そんな思い込みを自覚した瞬間、ふと「自分はいったい何様なのか」と疑問が突きつけられる。
このパートは、他人を変えようとする時に必ず伴う“苛立ちの正体”を暴き出している。相手に感じていた苛立ちは、実は自分の中の不安や焦燥の裏返しなのだろう。
サビでは「Wonderland」というタイトルが象徴する“未知の世界”が広がる。
OH La La La
うらがえしの世界をごらんなさい
勇気があるなら
しがみつくのも 手を離すのも
あっというまの Wonderland
ここで歌われているのは、物事を裏側から眺めてみる勇気だ。しがみつくことも、手を離すことも、選んだ瞬間に世界はまるで別の姿を見せる。
その一歩の先に待っているのが、自分の価値観では測りきれない「Wonderland」なのだろう。相手の世界に飛び込むことは怖さも伴うが、ほんのわずかな勇気があれば、これまでとはまったく違う景色が広がっていく。
その躍動感を「OH La La La」という軽やかなフレーズが彩り、メッセージの重さをポップに包み込んでいる。
曲のラストで描かれる光景は、特別なドラマではなく、あまりにさりげない日常の一コマだ。
僕がいつか捨てた ガラクタを磨いて
ぴかぴかのそいつを抱いて
君はただ笑ってる フツーに笑ってる
その姿は何かを語るわけでもなく、説得しようとするわけでもない。ただそこにある自然体の笑顔が、どんな言葉よりも雄弁に響いてくる。
この結末は、派手な感情を用意するのではなく、静かな余韻で物語を閉じている。
『Wonderland』レビューまとめ
「Wonderland」は、人を変えようとすることの空しさを描きながら、最後には“そのままを受け入れる”という静かな答えを示している。
劇的な解放ではなく、日常の片隅にある小さな笑顔を通して伝えられるのは、相手を肯定することの力強さだ。
聴き終えたときに心に残るのは、他者の価値観を無理に変える必要はない、自分とは違う世界をそのまま尊重していいのだという、やさしい肯定感である。

【生き生きとした】×『THE RACE』
ひときわ強烈なメッセージを放つ3曲目「THE RACE」。
幼い頃に始まった“かけっこ”が、いつの間にか人生そのものを縛るレースへと姿を変えていく―そんな社会の縮図を、疾走感あふれるロックサウンドに乗せて描き出している。
「勝ち組なの?負け組なの?」という直球の問いかけは、2000年代の社会風潮を鋭く切り取ると同時に、聴く者自身の胸にも突き刺さる。
だがこの曲は、単なる社会批判にとどまらない。サビでは「泥にまみれ綺麗になれ」と逆説的な肯定を打ち出し、失敗や無様さをも価値に変える視点を提示している。
アルバム全体が内省的なテーマと向き合うなかで、「THE RACE」はその核心を最もストレートに言葉にしたロックナンバーと言えるだろう。
『THE RACE』が示す競争社会からの脱却と自己肯定
A〜Bメロでは、誰もが経験してきた“競争”の感覚が描かれている。
秋空の下でみんなで並んで 位置についてよーいドンを聞いて
始まったレースは 今も脈々と続いてる
何を競い 誰と争う?
数字に縛られ なぜかムラムラ
何位になれば 君は振り向いてくれるの?
子どもの頃はただ楽しかったはずのかけっこも、大人になるにつれて点数や順位に置き換わり、いつしか人生そのものを縛るレースへと変わっていく。
この描写が胸に響くのは、誰もが自分の現実と重ね合わせられるからだ。仕事の成績やSNSの数字、学歴や肩書き―気づけば「誰と競っているのかも分からないのに、走らずにはいられない」状況に陥っている人は少なくない。
ここで表現されているのは単なる社会批判ではなく、リスナーの心に潜む不安そのものだ。なぜ焦ってしまうのか、なぜ他人と比較してしまうのか。
普段は見過ごしている問いを音楽を通して突きつけられることで、私たちは“自分がどんなレースを走っているのか”を改めて意識させられる。
サビで響くのは、従来の“勝つことこそ価値”という考えをひっくり返すようなメッセージだ。
走れよ走れ 無様に煌めいて
誰にも見えないあの白いテープを切ろう見事に
転べよ転べ 泥にまみれ綺麗になれ
笑って目指そう 今世紀最強の木の坊
上でもよろしい 下でもよろしい 真ん中もよろしい
おのれ自身をCHASE 汗だくのFACE とこしえのRACE
泥にまみれ、転び、無様であってもいい―むしろその姿にこそ人間らしい輝きがあると歌いかけてくる。社会では見栄えや結果ばかりが評価されるけれど、この曲は「失敗しても笑って立ち上がればいい」と励ましてくれる。
誰もが自分の中に“木偶の坊”のような無力さを抱えている。しかしその弱さを否定するのではなく、ユーモラスに受け止めて進んでいく姿勢が、この曲をただの社会批判ソングではなく、自己肯定を後押しする応援歌にしている。
さらに「上でも下でも真ん中でもよい」というフレーズは、序列に縛られず自分の位置を肯定する視点を示している。
大切なのは、自分だけのレースを走り続けること。その姿を汗だくのままでも抱きしめてくれるような温かさが、このサビにはある。
ブリッジパートで歌われるのは、「上を目指す」ことの限界だ。
上を目指し その先にはどんな世界があるというのでしょう
そのさみしさを ごまかしても 人はどこにも行けない
もちろん、努力を重ねて成果を手にすることは人生に充実感をもたらし、挑戦があるからこそ人は成長できる。成功を求めること自体は尊い営みだ。
しかし、その先に待っているのは必ずしも理想の世界ではない。結果や数字ばかりを追い続ければ、心は次第にすり減ってしまう。だからこそ、足元にある喜びや、すでに手にしている価値に気づくことが、健やかに前へ進むための支えになる。
このブリッジが伝えているのは、「努力してもいい、夢を目指してもいい―けれど、その過程で自分を見失うな」という警鐘だ。
上を目指す情熱と、いまを肯定する眼差し。その両方を抱きしめるとき、レースの風景はきっと違って見えてくる。
『THE RACE』レビューまとめ
「THE RACE」は、人生を終わりなき競争にたとえながらも、失敗や泥だらけの姿さえ肯定する力強いロックナンバーだ。
無様でも走り続ける姿にこそ輝きがある―その逆説的なメッセージは、日々の焦りや比較に押しつぶされそうな心をふっと軽くしてくれるはずだ。
この曲は“人生というレース”を苦しみの象徴ではなく、自分を輝かせるための舞台へと変えてくれるだろう。

【興奮状態】×『正面衝突』
切れ味鋭いファンキーなギターリフがうねりを生み、そのあとを追うようにブルースハープが鋭く響く。「正面衝突」は、アルバム『Peace Of Mind』の中でもっとも肉感的で、挑発的なロックチューンだ。
歌詞で描かれるのは、欲望に逆らわず突き進む瞬間。理性で避けようとしても、避けきれない衝動に導かれてしまう。その衝撃を稲葉は「正面衝突」と名付けた。事故ではなく、あえて求めてぶつかりにいく快楽―逃げ場のない官能を肯定する言葉として響く。
「濡れて光るゲート」「潔くその両手を離せ」といったフレーズは、直接的でありながらも比喩の遊び心に満ち、聴く者の想像をかき立てる。ハードなビートとグルーヴに呑み込まれるとき、リスナーもまた自らの“正面衝突”を体験することになる。
欲望と快楽の『正面衝突』―理性を越える官能のロックチューン
Aメロでは、取り繕いのない“むきだしの自分”がさらけ出される。
絶対真実の瞬間 タネもシカケもありゃせんぞ
むきだしのボク キミが包んで
イガミアイ続く未来 でもこの本能はみんな同様
愛より前の時代にさかのぼれ
そこにはごまかしも演出もなく、ただ本能のままに向き合う関係が描かれる。
人間社会のいがみ合いや未来への不安すらも飛び越えて、根源的な衝動へ立ち返ろうとする強さがある。
愛という言葉に包まれる以前の、もっと原始的な欲求を直視せよ―そんなメッセージを、ファンキーなグルーヴが力強く響かせている。
Bメロに入ると、抑えきれない欲望がより直接的な形を帯びていく。
一つになりたいと願えど 叶わぬきりのない思い
限りなく近づいてゆきたい 濡れて光るゲートに
言葉はさらに官能を帯び、目の前に開かれる扉は欲望の行き着く先を強烈に示している。
そのイメージにリスナーは否応なく引き込まれ、理性と本能の狭間で揺さぶられる感覚を味わうことになる。
サビでは欲望がついに臨界点を越え、抗いようのない衝突として炸裂する。
正面衝突 正面衝突
避けられない運命
Show me the way Show me the way
これこそ自ら望んだGoal
ここで描かれるのは偶然の事故ではない。理性で避けることをやめ、自ら望んで突き進む肉体の歓びだ。
繰り返される言葉は、まるで欲望の鼓動を刻むかのように響き渡り、ギターの刻みとドラムの強いビートが高揚感を一気に押し上げていく。
全身を突き抜ける快感と解放感―それが「正面衝突」のサビがぶつけてくる衝撃だ。
『正面衝突』レビューまとめ
「正面衝突」というタイトルは、この曲のすべてを物語っている。ファンキーに刻まれるギター、鋭く切り込むハープ、肉体を揺さぶるビート、そして欲望と理性の狭間を描く歌詞―その全てが真正面からぶつかり合い、逃げ場のない熱を生み出している。
『Peace Of Mind』の中でも、これほど衝動をストレートに叩きつけてくる曲はない。音の衝撃に身をゆだねた瞬間、リスナーは自分の内側に潜む衝動と真正面から向き合うことになる。
だからこそ、この一曲は体験してこそ意味がある。あなた自身の「正面衝突」を、ぜひ味わってほしい。

【感動する】×『水平線』
「水平線」は、遠い星に思いを馳せるスケールの大きな視点から始まり、人の心が不完全であるがゆえに、幸せと苦しみの狭間でもがく姿を映し出す。
ピアノが紡ぐ透明な旋律は、稲葉浩志の声に宿るかすかな震えや息づかいを照らし出し、リスナーの心を深い感情の海へと沈めていく。
そこに立ち現れる水平線は、人の心には決して届かない“完全な美”の象徴として姿を見せるが、やがてその輪郭をやわらげ、最後にはすべてを包み込む静けさへと変わっていく。
不完全さを抱えながらも愛を求め、傷つきながら生きる人間の姿が、澄み渡る青の景色に重なり、聴き終えたあとも胸の奥で静かに波紋のように広がり続けていく。
溶けゆく感情は青に染まる―『水平線』が示す不完全な心
冒頭で描かれるのは、遠い昔に生まれた星の光。
遠い昔の星の灯の
長い旅路を想うならば
こんな涙はとるに足らない
わがままなしずくでしょう
冒頭で描かれるのは、遠い昔に生まれ、何万年もの旅を経て地球に届いた星の光。その悠久さに思いを馳せると、いま流れる涙はほんの“小さなわがままのしずく”に過ぎないように見えてくる。
壮大な比喩を持ち出しながらも、そこににじむのは無視できない感情の重みだ。星の光を背景に、人間の弱さと愛おしさが静かに浮かび上がってくる。
Bメロで水平線は、到達できない“完全な美”の象徴として立ち上がる。
幸い求め 災いから逃れられないのは
この心が あの水平線のように 完璧な美しさじゃないから
水平線は、どこまでも真っ直ぐに伸び、揺らぎや歪みのない線として目に映る。
しかし人間の心は、その線のように乱れなく保つことはできない。迷い、傷つき、矛盾を抱えて揺れ動いてしまう。
だが同時に、その不完全さこそが人を人たらしめている。揺れる心を持つからこそ、誰かを強く求め、そして「失いたくない」という切実な想いが生まれる。
水平線という揺るぎない直線を鏡のように掲げることで、弱さを抱えた心にこそ真実が宿ることを静かに示しているのだろう。
サビでは、それまで広がりを持って描かれていた視点が、一気に身近なものへと収束する。
おねがい どこにもいかないで
風に吹かれ抱きしめあった人よ
あれはまぶしくはかない
夕陽のきらめきです
大切な人に「どこにもいかないで」と懇願する言葉は、飾り気のないシンプルさゆえに胸の奥を深く突き刺す。
その想いを映す情景が「夕陽のきらめき」だ。愛する人と過ごした瞬間の尊さと、やがて消えてしまう儚さを同時に抱え込むその光は、強烈な残像となって心に焼きつく。
“失いたくない”という切実な気持ちを、まばゆさと切なさが同居する夕陽に重ねることで、この楽曲は痛みと美しさを併せ持った感情の輪郭を鮮やかに描き出している。
『水平線』レビューまとめ
曲の終盤で願いの言葉は静かにほどけ、残されるのはすべてを受け止めるように横たわる水平線と、果てしなく広がる青の情景だ。
激しい感情の揺れも、抱えきれない矛盾も、最後にはその景色に溶け込んでいく。
稲葉浩志が描いたのは、完全ではない心をそのまま抱えながら生きることの美しさであり、聴く者の胸に深い静けさを刻むバラードである。

【精力的】×『すべての幸せをオアズケに』
『Peace Of Mind』の中盤を彩る「すべての幸せをオアズケに」は、アップテンポのロックナンバーとして力強く響く。
「幸せじゃなきゃ不幸だなんて」というフレーズに象徴されるように、稲葉浩志は日常で押しつけられる“幸福の基準”を、ユーモアと皮肉で軽やかに突き崩してみせる。
カタカナで掲げられた「オアズケ」というタイトルもまた、重くなりがちなテーマを笑いに変える仕掛けとして作用している。思想的な鋭さを持ちながらも、ロックの疾走感と豊かな音の広がりがその重さを和らげ、リスナーに心地よい解放感をもたらす。
シリアスな問いかけと快活なサウンドが織りなす鮮やかなコントラスト─それこそが、この曲の魅力だろう。
『すべての幸せをオアズケに』が描く、稲葉浩志の幸福論
曲の始まりは、誰もが日常でふと直面する「幸せかどうか」という問いから幕を開ける。
月曜日の街で聞かれた
今あなたは幸せですか
歩きながら 笑って答えた
いいえ 別に
待ちあわせの場所に さあ急げ
主人公はその問いに、どこか力の抜けた返答をする。その曖昧さはむしろリアルであり、幸せか不幸かを即答できない感覚に、多くの人が共感できるはずだ。
しかし内省の余韻に浸る間もなく、現実のリズムはすぐに歩みを進める。慌ただしい日常に引き戻され、次の行動を促される光景が浮かんでくる。
ここには、哲学的な問いと忙しない日常とが並走する、現代人の姿が鮮やかに切り取られている。
サビで提示されるのは、「幸せでなければ不幸だ」という極端な価値観への痛烈な拒絶だ。
もういいよベイビー どうかこれ以上脅さないで
幸せじゃなきゃ不幸だなんて
こうなりゃ いっそ みんなで笑える日がくるまで
すべての幸せを オアズケに
押しつけられる幸福の基準に対して、稲葉浩志は「そんな脅しには屈しない」とばかりに、むしろ全員で“幸福をお預けにしてしまおう”という逆転の発想を提示する。
その中心にあるのが「オアズケ」という言葉の軽やかさだ。本来なら重苦しく響くテーマを、ユーモラスな響きに変換することで、リスナーは肩の力を抜きながら受け止められる。
痛烈な批評性と遊び心のある言葉選びが同居することで、サビはひときわ鮮やかな場面となり、リスナーの記憶に鮮烈な跡を残すだろう。
ブリッジに入ると、この曲は一気に思想の核心へと踏み込む。幸福をめぐる比喩が畳みかけるように展開され、 リスナーはいつの間にか「そもそも幸せとは何か?」という問いに向き合わされる。
その昔 神さまが決めた巷の定理
幸福は奪いあう一個の甘いケーキ
そしてこのからくりにはまったやつら
全員同時の幸せは不可能
それでも不幸にびくつきながら
幸福を待ちわび毎日スラローム
不幸なんてものをなくすために
ここはおもいきって皆さん幸福を捨てて下さい
すべてを支配するのはコ・コ・ロ
ここで登場する「スラローム」という言葉は特に印象的だ。スキー競技の回転種目を指し、旗の間を左右に曲がりながら滑り降りる姿を思い起こさせるこの言葉によって、私たちが不幸を避けながらジグザグに生き抜いている様子が鮮烈に描かれる。
それでいて、曲調は重苦しく沈み込むのではなく、むしろ勢いを増して駆け抜けていく。そのギャップが皮肉をただの悲観ではなくユーモアとして響かせ、リスナーに“自分の心が選ぶ幸せ”というテーマをすっと浸透させていく。
アルバム全体の中でも最も哲学的でありながら、同時に聴きやすさを失わない─まさに稲葉浩志らしい仕掛けだ。
『すべての幸せをオアズケに』レビューまとめ
「すべての幸せをオアズケに」は、ただ幸福論を語るだけの歌ではない。
シリアスな問いを投げかけながらも、軽やかに駆け抜けるロックサウンドによって、リスナーに余計な重さを背負わせない。
アルバム『Peace Of Mind』の中盤で響くこの曲は、私たちの中にある「幸せでなければ不幸」という思い込みを解きほぐし、もっと自由に、もっと心のままに生きる視点を提示してくれる。
稲葉浩志のソロワークならではの哲学とユーモアが凝縮された、鮮烈な一曲である。

【当惑する】×『Tamayura』
稲葉浩志の「Tamayura」は、妖しげに響くピアノとギターのフレーズから幕を開ける。その旋律はどこか不穏で、深い闇に足を踏み入れるような緊張感を漂わせ、聴く者の心を強く掴んで離さない。
そこから広がるのは、和の情緒とロックのエネルギーが交錯する独特の音像。重くも鮮やかなサウンドが、聴き手を自身の内面へと導いていく。
タイトルの「玉響(たまゆら)」とは、“ほんの一瞬”“かすかなひととき”を意味する古語である。人生の短さや時間の儚さを象徴するこの言葉は、歌詞に込められた「時間を無駄にせず、束縛を越えて自由に生きよ」というメッセージと重なり、楽曲全体を包み込むテーマとなっている。
心の闇を直視する痛烈な描写から、宇宙的な解放感へと昇華していく「Tamayura」。それは、心の闇と光を描いた壮大な物語である。
『Tamayura』とは―“玉響(たまゆら)”に込められた人生の儚さ
冒頭から突きつけられるのは、胸を締めつけるような孤独と自己嫌悪だ。
不細工に揺れる 心が嫌になり 自由を知りたくて
手あたりしだいに やせっぽっちの体傷つけて
一人待ちこがれるsunrise
ただ流れだすのは ぬるい血ばかりで思わずcry
病める魂は出てきゃしない
どうしようもなく揺れ動く心の弱さに嫌気が差し、自由を求めてもがく姿が、目の前に突きつけられるように生々しく響いてくる。
しかし現実は残酷で、もがけばもがくほど虚しさが広がっていく。その情景には、苦しみの根源に必死で手を伸ばしても決して届かない―そんなやり場のないもどかしさが凝縮されており、聴く者の胸に鋭い痛みを刻み込む。
これは単なるネガティブな描写ではない。むしろ、人が心の奥底で抱え続ける「どうにもならない感情の闇」を真正面から描き出している。
その赤裸々なリアリティこそが、この曲をただのロックナンバーではなく、特別な存在へと押し上げている。
Aメロの混沌を切り裂くように差し込まれるBメロは、曲全体を貫く「自己の闇と向き合う」というテーマを明確に示していく。
今そこにある悲哀 今こそじっと見つめて
その正体を暴けよ
渦巻く混乱や痛みに押し流されていた心を立ち止まらせ、「逃げずに見つめろ」と突きつけるような力強さがここにはある。
そのフレーズが示すのは、感情に呑み込まれるのではなく、その奥に潜む原因を暴き出すこと―それこそが解放への第一歩だという鋭いメッセージだ。
その言葉は、聴き手を内面へと引き戻し、感情の源を見つめさせる。
サビでは、もがき続ける心の叫びが一気に解き放たれる。
どしたら変わる? どしたら笑う?
きっと簡単なスイッチだろう
でもそれが見つからないまま
人は涙にくれる
たまゆらのLIFE たまゆらのLIGHT
時間のオリを踏みだして
燃えつきて 超微粒子になれ
そして きらきらきら 久遠の空を舞う
変わりたいのに方法が見つからない―そんな普遍的な葛藤を抱えた声が、聴き手の胸を鋭く突き刺す。
そこから浮かび上がる「たまゆら」という言葉の響きは、人生の儚さを象徴しながらも、限られた時間をどう生き抜くべきかを問いかけている。
時間の檻を破り、束縛を脱ぎ捨て、やがて“超微粒子”となって宇宙に舞い上がる。その壮大な比喩は、個人の苦悩を超えて魂の解放へと導くビジョンを描き出している。
そして最後に歌われる「久遠の空を舞う」。久遠とは“永遠に続く時間”を意味する言葉であり、刹那の「たまゆら」と対をなす表現だ。
人生の一瞬を燃やし尽くしたその先に、永遠の広がりの中で舞う魂の姿が重なり、聴き手に大きな解放感と余韻を残す。
『Tamayura』レビューまとめ
「Tamayura」は、心の闇を直視し、その先に見える光を掴もうとする旅を描いている。
刹那を意味する“たまゆら”と、永遠を意味する“久遠”―相反する言葉が交わることで、人生の儚さと尊さが鮮やかに浮かび上がる。
限られた時間をどう燃やし尽くすか―その問いに向き合うとき、私たちはようやく「Tamayura」の本当の輝きに触れることができるのだろう。

【楽しい】×『ハズムセカイ』
泣き顔の理由を問いただすよりも、ただ「そばに来て」と差し出す一言から始まる「ハズムセカイ」。
哀しみや悔しさを無理に打ち消さず、そのまま受けとめて寄り添う視線に、聴く側の心も少しずつほどけていく。
歯切れのよいギターが軽やかに跳ね、稲葉浩志の声が鼓動に重なるように響き出す。そしてサビにたどり着いた瞬間―「キミがいるだけで世界が変わる」というフレーズが、沈んでいた空気に明るい風を通してくれる。
この曲は決して力ずくで励ます応援歌ではない。現実の痛みを知っているからこそ、軽やかな言葉と中速のグルーヴが、心の奥に自然な浮力を与えてくれる。
沈んでいた一日がいつの間にか揺れ始める。この曲は、そんなふうに日常にリズムを取り戻してくれるロックナンバーだ。
沈んだ日常を揺らす、やさしいグルーヴ―『ハズムセカイ』」
この曲の冒頭は、泣き顔に向けられた視線から始まる。
泣いてたでしょ そんな目でしょ それは
哀しいのか 悔しいのか 分からないけれど
ねえ知らないでしょ 自分のすごい才能を
ちょびっとだけでいいから そばに来ておくれ
そこにあるのは追及ではなく、理由を決めつけないまま受け入れるやわらかさ。相手の存在をそのまま包み込もうとする眼差しに触れると、聴く側の心も少しずつほどけていく。
変化を求めるのではなく、ただ「ここにいてほしい」と願う。その軽やかな頼みかけが、この曲全体のトーンをやさしく形づくっている。
サウンドもまた、その空気を後押しする。歯切れのよいギターと余白を残したリズムが、まだ大きく跳ね上がる前の助走のように鳴り、曲の立ち上がりに穏やかな温度を添えている。
サビに入ると、曲全体が一気に跳ね上がる。
ハズムセカイ ハズムココロ
キミがいるだけで ボクの世界は変わるよ
ハズムフィーリング ハズムカンバセイション
そして たまには触れあったりしてもいいでしょ
繰り返される「ハズム」の響きは、軽快さだけでなく、心のリズムを取り戻す力を持っている。
残業を終えて夜遅くに帰宅し、気力も体力もすり減ってソファに沈み込む瞬間。深いため息が漏れるそのとき、このサビが流れてくると張りつめていた心がふっと和らぐ。
「君がいるだけで世界が変わる」という直球のメッセージは、気持ちを無理に持ち上げるのではなく、自然に心の奥をふくらませていく。
現実の重さを抱えたままでも、心が自然に揺れはじめる。このサビにはそんな確かな浮力がある。
ブリッジでは、呼吸を整えるようにそっとトーンが変わっていく。
この浮き世で起きてること
あれこれ いろいろ 受け止めて
泣くも笑うも キミとボク次第
「浮き世」という言葉が、日常に潜む面倒や理不尽をやわらかく映し出す。
けれど続くのは突き放しではない。「泣くのも笑うのも自分たち次第」という視点の切り替えが、曲を単なる励ましで終わらせず、“現実を抱えたまま進む力”へと変えていく。
サウンドもここで余白をつくり、声のニュアンスを際立たせる。ラスサビへ向かう前の、深呼吸のようなひとときだ。
『ハズムセカイ』」レビューまとめ
この曲は、激しいサウンドで突き抜けるタイプのロックではない。けれど、その軽やかな力強さが、沈んだ日常をそっと前へ押し出してくれる。
泣き顔に寄り添うやわらかさと、現実の重さを受け止めながら進む力。その二つを同時に与えてくれるから、疲れた一日の終わりや、気持ちが空回りしそうな日にこそ再生したくなる。
聴き終えたとき、世界そのものは変わらなくても、心の鼓動は確かに変わっている―この曲にはそんな力がある。

【希望に満ちた】×『幸福への長い坂道』
「幸福への長い坂道」は、わずか2分半の短い楽曲である。
アコースティックギターを軸に、ピアノの柔らかな響きが重なり、淡々としたリズムで進んでいく。そのサウンドは派手な盛り上がりを避け、あたかも一場面を切り取ったかのような素朴さをまとっている。
歌詞に描かれるのは、長い坂を上り、汗を流しながら錆びた自転車をこぐ姿。その光景に重なるのは、“幸福”へとたどり着きたいと願う揺らぎと痛み、そして「素敵なことが始まる」と信じ続ける微かな光だ。
曲はその情景を浮かび上がらせたまま、ふっと宙に解き放つように終わる。聴き終えた後に残るのは、未完の物語を託されたかのような余白。その余韻がむしろ、「幸福」という言葉の重さをいっそう深く刻み込んでいる。
『幸福への長い坂道』―短い物語が残す“幸福”への余白
「空へと向かってのびる坂道」という冒頭の一節は、果てしない人生そのものを映す比喩として響く。
空へと向かってのびる 長い坂道のぼれば
その先に幸せがあるはずと いつか誰かに教わった
要らないものを捨てながら 汗をかいて
錆びついて悲鳴をあげる自転車をこいだんだ
登り切った先に何が待つのかは分からない。それでも「幸福があるはずだ」と信じて歩みを進める姿は、希望と不安の境界を行き来する私たち自身の姿に重なる。
その道のりは決して平坦ではない。錆びた自転車を必死にこぐ描写には、人生の重荷や痛みを抱えながらも、それでも前へ進もうとする意志が映し出されている。
シンプルな言葉の連なりの中で刻まれているのは、幸福は与えられるものではなく、痛みを抱えながらも自らの力でたどり着くものだという普遍的な真実である。
サビでは、根拠のない未来への期待が、淡い光のように歌われる。
ああ そして何か 素敵なことが始まる
そう 信じたんだ 遠ざかる意識の中で
確かな根拠はどこにもない。それでも遠のく意識の中で信じようとする声は、かすかな祈りのように響き続ける。
ここで描かれているのは、力尽きそうな瞬間にも希望を手放さない心の姿だ。現実の厳しさを抱えながらも、なお「始まり」を信じる。その揺らぎを帯びた希望こそが、人間らしい切実さを際立たせている。
華やかさではなく、静かで脆い願い。その控えめな光が、この曲全体を支える灯火となっている。
『幸福への長い坂道』レビューまとめ
この曲には派手さも劇的な展開もない。けれど、人生の重みや痛み、そしてその先に見たいと願う光が、短い時間の中に凝縮されている。
二分半でふっと途切れるからこそ、聴き手の心には大きな余白が残される。その余白に、自分自身の坂道や希望を重ねることができるのだ。
曲が終わったあとに残るのは、空へと伸びていく坂道の続き。その先にある“幸福”を描ききるのではなく、私たち自身に歩みを委ねてくれる。
未完の物語であるがゆえに、美しく、そして深い余韻を湛えながら心に響き続ける。

【張り詰めた】×『横恋慕』
「横恋慕」は、その名のとおり“禁じられた恋”をテーマにした一曲だ。
琴の響きがふと差し込むたび、空気に淡い陰影が広がり、押さえ込んだはずの衝動は、汗や視線の揺らぎとともにこぼれ落ちていく。
その危うい心の揺れを、乾いたロックサウンドと和のきらめきが絶妙に縁取り、背徳と憧憬が絡み合う妖艶な景色へと導いていく。
アルバム全体の流れの中でもひときわ緊張感を放ち、聴き手を深く惹き込む楽曲である。
『横恋慕』―光から影へ、妖艶に沈む瞬間
曲は冒頭から、じわりと汗が伝う肌や、不意にさらされる無防備な横顔といった、生々しい情景で幕を開ける。
首すじを ちろりと 汗が這って落ちる
思わず 見とれてる 無防備な顔さらし
oh キミはアイツのもの 知ってる
でも なりふり構わん テーブル蹴っ飛ばせ
視線を奪われた刹那、主人公の理性はほころび、抑えてきた衝動が静かに滲み出していく。
Bメロでは、相手がすでに誰かのものであるという冷徹な現実が突きつけられる。
それでも欲望の炎は衰えず、日常の秩序を蹴散らしてでも手を伸ばそうとする危うさが、より鮮明に浮かび上がる。
サビに入ると、抑えていた感情が一気に解き放たれる。
どんな罰でも 受けましょう とまらない横恋慕
見事 飲み下して見せよ きっかりハリ千本
今に落ちてゆくのは 燃えたぎる谷間
罰を受けても構わないという覚悟とともに、危うい恋情を飲み干すような声が響き渡り、もはや後戻りのきかない領域へと踏み込んでいく。
それに呼応するようにサウンドも厚みを増し、稲葉のボーカルはさらに熱を帯び、言葉の一つひとつに切迫感が宿っていく。
背徳と陶酔がないまぜになったその高まりこそが、「横恋慕」のサビを支配する緊張感であり、聴き手を抗えない渦へと引きずり込んでいく。
ブリッジでは、それまで抑え込まれていた緊張がほどけ、場面は一気に劇的な空気へと切り替わる。
ぬけだしちゃお こんなうるさい店から 映画のように 劇的にyeah
手をとりあって 悲劇の主人公 きどって愛の逃避行
エレキギターのリフに導かれる旋律は、現実からの逃避を夢想するように高揚し、危うさとロマンティシズムを同時に孕んでいる。
甘美な解放感に包まれながらも、その背後には破滅の影が潜み、サウンド全体がその二面性を鮮やかに映し出している。
『横恋慕』レビューまとめ
「横恋慕」は、禁じられた想いに揺れる心の奥を照らし出す楽曲だ。
だからこそ、表向きは冷静を装いながら胸の内に熱を抱える人、あるいは理性と衝動のはざまで揺れた経験を持つ人には、ひときわ深く響くだろう。
抑えを失った歌声の熱と、乾いたサウンドが織りなす緊張感が、背徳の甘美さを鮮やかに描き出している。
恋愛の甘さや明るさとは無縁に、この曲は感情の暗がりをまっすぐに見つめ、その中に潜む美しさを浮かび上がらせる。
危うい魅力に身を委ねたいとき、「横恋慕」は忘れがたい一曲として心に刻まれるだろう。

【そわそわする】×『SAIHATE HOTEL』
夕陽に照らされた高速道路は車でぎっしりと埋まり、旋回するヘリコプターが着陸態勢に入っていく。だが、高層ホテルの一室にいる主人公にとって、それらは“ぶ厚いガラスの向こうの無音の劇場”にすぎない。
外界のざわめきが遠のくほどに、内側では「君」を待つ胸の鼓動だけが大きく響きはじめる。
「SAIHATE HOTEL」は、その緊張感をサウンドと歌詞で鮮やかに描く。冒頭は静かな電子音に、床下から唸るベース、そしてダウンミュートで刻まれるギターが重なり、部屋をダークな緊張で満たしていく。やがて音像は軽快なバンドアンサンブルへと切り替わり、閉ざされた空気が一気に解き放たれる。
繰り返される「ボクハ待ツ じっと待つ」という言葉は、静止ではなく弾けそうな高鳴りの証。そのフレーズが響くたびに、最果てホテルの一室は孤独の箱から、恋の不安と希望が交差する舞台へと姿を変えていく。
『SAIHATE HOTEL』─閉ざされた一室に響く音と情景
冒頭は、外の喧騒と内なる静寂を対比させながら、“最果てホテル”という舞台を立ち上げていく。
夕陽に向かい みんな帰りたい でもぎっしりの高速道路
クワガタみたい ヘリは自衛隊 目の前横切り着陸体勢
ぶ厚いガラスの向こう 見えるのは無音の劇場
心臓はエレヴェイター
雑然とした景色をホテルの高層階から見下ろす主人公の視線には、現実のリアルさと同時に、どこか切り離された距離感が漂っている。
やがて厚いガラスに遮られた風景は音を失い、外界はひとつの無音の劇場のように姿を変える。街のざわめきが遠のくほどに、部屋の内側では鼓動だけがせり上がり、上下に揺れるエレベーターのように落ち着かなく脈打つ。
こうして日常から隔絶された空間が、“最果てホテル”という舞台となり、これから描かれる緊張と高鳴りの物語を予感させる。
サビでは、“待つこと”そのものがテーマとして浮かび上がる。ただ静止するのではなく、胸の奥で渦巻く緊張や期待を抱えながら、訪れる瞬間を受け止めようとする姿勢だ。
ボクハ待ツ じっと待つ 君の手がドアに触れるのを
ショパンのボリュームを慎重に下げよう
恋に落ちるということは 不安まみれで過ごすこと
ろくすっぽ夜も眠れない
みんなライトをともす
ここはSAIHATE HOTEL
まぶしいSAIHATE
その感情は甘さと同時に不安を伴い、聴く者に「恋の入り口に立ったときの落ち着かなさ」を鮮やかに思い出させる。
サウンド面でも、緊張の圧を解き放つようにバンドのエネルギーが広がり、聴き手を一気にドラマの中心へ引き込む。心の内で膨らむ高鳴りと音の広がりが呼応し、この曲に独特の高揚感を生み出している。
繰り返される“SAIHATE HOTEL”という言葉には、二つの意味が潜んでいる。
ひとつは、都会のざわめきから切り離された安全地帯としての“逃げ場”。厚いガラスに守られた部屋は、誰にも邪魔されないシェルターのように機能している。
もうひとつは、扉を開けば世界が変わる“臨界点”としての意味だ。
期待と不安がせめぎ合う境界に立つことで、恋における「傷つきたくない」と「飛び込みたい」という矛盾した感情が浮かび上がる。この二重性こそがサビを際立たせている。
最果てにあるはずのホテルが、むしろまぶしく輝いて響くのは、“避難所であり挑戦の場でもある”という逆説的な魅力を宿しているからにほかならない。
ブリッジでは、夕暮れに沈む街とともに、主人公の内面も心の奥へ沈み込んでいく。
街たそがれ ボクあこがれ 底なしの欲望に飲みこまれ
自由を無くし 生きてることに 気づかないけどかまやしない
これまで描かれてきた“待つことの緊張と高鳴り”が、ブリッジでは一転して「抗えない欲望」へと形を変える。恋という感情が持つ甘美さと危うさ、その両面を突きつける瞬間である。
サウンド的にもここは一時的にトーンが落ち、楽曲全体に濃い影を差し込む。静かな焦燥を挟むことで、ラストのサビへの高揚へとつながるコントラストを生み出している。
『SAIHATE HOTEL』レビューまとめ
「SAIHATE HOTEL」が特別なのは、ホテルの一室という限られた空間を通じて、誰もが抱く普遍的な心の動きを映し出している点にある。外界を断ち切る静寂と、内側で高鳴る鼓動。そのコントラストは、恋に限らず「新しい一歩を踏み出す前の緊張」にも重なっていく。
だからこの曲は、密室の物語でありながら、聴き手それぞれの記憶を呼び起こす鏡のように機能する。進学や就職、旅立ちや別れ─人生の節目に立つとき、人は誰しも“最果てホテル”の扉の前にいるのかもしれない。
その意味で、この曲は単なる恋愛の情景描写を超えて、「臨界点に立つ心のありよう」を刻んだ作品だ。
聴くたびに自分自身の“最果て”を見つめ直すきっかけを与えてくれるだろう。

【ぞくぞくする】×『I AM YOUR BABY』
「I AM YOUR BABY」は、アコースティックギターやブルースハープがカントリーの温もりを描き出し、そこにロックの推進力が加わることで、エンジンをかけて走り出すようなドライブ感に満ちたロックナンバーとなっている。軽やかさと力強さが同居し、聴く者の心を前へと押し出す。
歌詞は、信号や線路下、落書き、潮の香りといった街の断片を切り抜けながら、ただひとりの「君」へまっすぐ向かう姿を描く。
視界に映る景色がすべてスピード感を帯び、ロードムービーのワンシーンのように流れていく。
サビで繰り返される 「I am your baby(=私はあなたにすべてを委ねる存在)」 というフレーズには、無邪気さと覚悟が同時に刻まれている。「ぷわぷわの愛」という言葉は甘やかでありながら、その裏に燃えるような情熱を秘めており、聴く者を強く惹きつける。
この曲が響かせるのは、愛に突き進む衝動と、その瞬間を全力で生きる輝きである。ハンドルを握りしめたまま、どこまでも駆け抜けていくような爽快さがここにある。
『I AM YOUR BABY』―愛に突き進むスピード感あふれるロックナンバー
Aメロは、緑の矢印が静かに灯り、進むべき方向を示すところから始まる。
緑に光る矢印を見つめ 汗を拭い窓を開ける
交差点を真っすぐ抜け 君のもとへ
乱暴なバイカーに注意を払い 線路の下に潜り込む
派手な落書きやり過ごし そのままゆけ
車内にこもった熱気を振り払うように窓を開け、そのまま交差点へ滑り込む。街のざわめきや荒れた風景は速度にのみ込まれ、視界はただ「君」へと一直線に伸びていく。
ここにあるのは都会の情景ではなく、愛へ駆け出す衝動そのものだ。
Bメロでは、視界が街の風景から内なる衝動へと切り替わる。
前だけを見て加速していく 異常なまでに燃えるバイタリティー
どんな弾でもよけられそうな 今
燃え上がっているのは、常識を超えるほどの生命力だ。その衝動は、弾丸すらかわしてしまえるかのような無敵感をまとっている。
ここで響いているのは、単なる勢いやドライブの快感ではない。愛に向かって突き進むことが、自分を生かす原動力になっているという確信だ。
走れば走るほど、主人公の胸には「生きている」という実感が鮮やかに刻まれていく。
サビでは、曲のスピードが感情のピークと重なり合い、一気に視界が開けていく。
l am your baby どうにでもして 迷うことなき嵐の使者
ぷわぷわの愛が欲しくってまっしぐらに進もう
I am your baby 何が何でも 辿り着きたいと願う心
今夜はそれを愛と呼ばせてください
まっすぐに走り抜けてきた主人公の衝動がここで解き放たれ、言葉は一直線に響く。
「I am your baby」と言い切る無垢な声と、「迷うことなき嵐の使者」という荒々しい比喩、さらに「ぷわぷわの愛」という可憐な響きが重なり合い、激しさと優しさが同時にせり上がってくる。
直線的な疾走の中に、むき出しの純粋さと柔らかな温度が共存し、この曲にしかない独特の高揚感を生み出している。
そして「今夜はそれを愛と呼ばせてください」と歌い切る瞬間、走り抜けてきたこの衝動は“愛”という言葉に変わっていく。
『I AM YOUR BABY』レビューまとめ
「I AM YOUR BABY」は、ただ“疾走感のあるラブソング”として味わうだけではもったいない。
街の情景に自分の日常を重ねれば、曲はまるで心のスクリーンに映るロードムービーのように広がっていく。
孤独に胸が締めつけられる夜や、どうしても誰かを想わずにいられない瞬間、この楽曲はその切実さを温かく抱きしてめてくれるはずだ。

【疎外される】×『透明人間』
稲葉浩志ソロ『Peace Of Mind』の終盤を飾る「透明人間」は、聴き手を容赦なく闇の底へ突き落とす一曲である。
誰からも存在を認められず、名前を呼ばれることすらない。そんな孤独の痛みが、ナイフのように胸に突き刺さる。明るさも救いもここにはない。ただあるのは、無視され続ける存在の痛切な自覚と、暴発寸前の心の震えだけだ。
やがて曲は、幼い日の記憶に触れるかのように母親の姿を呼び起こしながら、それでも「どこかへ行きたい」と願う逃避衝動へと傾いていく。
そして最後に放たれるのは、世界を思い通りにねじ伏せたいという、願望と破壊が入り混じった絶叫である。そこには優しさや慰めの影はなく、行き場を失った魂の熱と歪みだけが焼き付けられている。
冒頭を包む冷たい空気は、教室や街のざわめきに紛れても誰からも気づかれない主人公の姿を映し出す。その後、張り上げられるボーカルと荒れ狂うギターが、やり場のない渇きと苛立ちを増幅させる。
まるで“透明人間”の影がサウンドに実体を宿し、こちらへ迫ってくるようだ。
『透明人間』―誰にも触れられない孤独が、ナイフのように胸を切り裂く
曲は静かに始まる。主人公は「透明人間」のように、教室でも廊下でも誰からも気づかれない存在として描かれる。
透明人間みたいに
どこでもゆける
うらやましいだろ
教室の中でも 廊下を走っても
みんな見てないみたい
その語り口には、自嘲めいた響きと「うらやましいだろ」という皮肉がにじむ。
誰にも見えないことは一見自由のようでいて、実際には解放ではなく、ただ視線を注がれないことの虚しさに過ぎない。
思春期の心に宿る“存在しないことの痛み”が、この冒頭の短い言葉に鋭く刻み込まれている。
続くフレーズでは、主人公は自分の状況を“自由”と呼ぶ。
なんて自由なんだろ 波のない海
けれどそれは、動きのない海に漂うような停滞の比喩だ。
表面は穏やかでも、実際には風も波もない閉ざされた世界。そこでは前に進む力も、揺さぶられる刺激も失われてしまう。
動けるはずなのに、どこへも行けない。そんな矛盾した自由が、かえって孤独の深さを際立たせている。
ここで物語は一気に切迫する。主人公は、自分の存在を呼びとめてくれる声を必死に求める。
だれかぼくの名前を呼んで
だれでもかまわないよ 早く
今日はやけに暑い日だよね
喉は渇いてる
伝言はありませんか?
誰でもいい、ただ名を呼んでほしい。その渇望は、炎天下で喉を焼かれるような乾きと重なり、どうしようもなく切実だ。
中でも印象的なのが「伝言はありませんか?」という投げかけである。名を呼んでほしいという願いよりもさらに小さな形で示される、この“伝言”という言葉。
直接でなくても、自分に届く“誰かの声”を求める心の現れだ。存在を確かめるための最低限の手段として、このフレーズは異様なほどに胸を打つ。
承認を願う心と、それが叶わない現実。その埋められない溝こそが、サビ全体を痛切な叫びへと変えている。
ラスサビに突入すると、曲は一気に臨界点へと達する。
だれかぼくの名前を呼んで
だれでもかまわないよ 早く
景色はぜんぶ ゆがんでゆくよ
熱にうなされて
おかあさん
僕はあの時 光をめざして
最高の世界を夢に見ながら
せいいっぱいあなたの海を泳いだよ
そしてもうどこかに行きたい
世界よ僕の思い通りになれ
いつか僕の思い通りに
思い通りになれ
視界が歪むほどの熱と混乱の中で、主人公は母の面影を呼び起こす。幼い日に光をめざして必死に泳いだ記憶が、一瞬だけ温もりをもたらす。だがその光もつかの間、心は再び闇へ傾き、「どこかへ行きたい」と逃避の声を上げてしまう。
その上に重なる稲葉の歌声は、祈りと渇望を同時に抱えた痛切な叫びだ。母への憧憬と、行き場を失った魂の衝動がないまぜになり、聴く者の胸を鋭く揺さぶる。その叫びに呼応するようにギターは荒れ狂い、音そのものが感情の裂け目を切り裂いていく。
やがて放たれるのは、世界を思い通りに変えてしまいたいという願望と破壊の絶叫。そこに救いはない。だが、声とギターが絡み合う瞬間、聴き手は確かに“透明人間”の心の奥底に触れる。絶望をさらけ出すことでしか届かない、鋭利な感情の真実がここに刻まれている。
『透明人間』レビューまとめ
「透明人間」は、光と闇の記憶がせめぎ合い、最後には世界さえ呑み込もうとするほどの衝動へと達する一曲だ。その過程を稲葉の声とギターサウンドが余すことなく映し出し、聴き手は自らの心の奥に潜む影と向き合わされる。
心が弱っているときには重すぎるかもしれない。けれど、誰しもが一度は抱いた「存在を確かめたい」という切なる願いを、この曲は鋭利な言葉と音で刻み込んでいる。だからこそ、聴き終えたときに残るのは恐怖ではなく、「確かに自分はここにいる」という痛烈な実感だ。
アルバム『Peace Of Mind』の中で最も危うく、そして最も人間的な歌。それが「透明人間」である。

【感動する】×『あの命この命』
なぜ人は、一つの命には涙を流しながら、無数の命の犠牲には目を背けてしまうのだろう。稲葉浩志の「あの命この命」は、その矛盾を静かに突きつける。
救われる命がある一方で、理由もなく奪われてしまう命がある。誰かを守るために、別の誰かを犠牲にせざるを得ない現実もある。数字や報道では語りきれないその重みの前で、聴く者は思わず立ち止まり、自分自身の感情と向き合わされる。
アコースティックギター一本に寄り添う声が繰り返すのは、ただ一つの問い。
「あの命この命、どちらがどれだけ重いんでしょう」
アルバム『Peace Of Mind』のラストに置かれたこの歌は、答えを示すことなく、静かな祈りを残して幕を閉じる。
その響きは時代を超え、聴く者の胸に深い余韻を刻み続けている。
消えゆくすべての中で、ただ残るぬくもり―『あの命この命』に宿る祈り
この曲は冒頭から、命に向けられる人の眼差しの揺らぎを描き出す。
36時間の手術の末に
最新の医学に救われた
一つの小さなその命に
誰もが涙を流してた
翌日 ある町に朝早く
最新のバクダンが落っこちて
あっけなく吹き飛んだ多くの命を
誰もが知らないまま時が過ぎる
ひとつの命が救われた瞬間には、涙と喜びが集まる。けれど、多くの命が奪われた現実は、いつの間にか時の流れに埋もれていく。
その落差に言葉を失い、聴く者は自分の心の在り方をそっと問われる。なぜ私たちは、目の前の小さな奇跡には歓喜しながら、遠くで起きる悲しみには沈黙してしまうのか。
稲葉浩志は、声を荒げることなく、アコースティックギターの静けさに寄り添いながら、この矛盾を淡々と描いていく。
その静けさこそが、むしろ聴く者の胸により深く響いてくる。
サビで繰り返されるのは、決して答えが出ない問いだ。
あの命この命 どちらがどれだけ重いんでしょう
いつかあなたとふれあった せめてあのぬくもりよ永遠に
「命の重さを比べることなどできるのか」―サビで投げかけられる問いに、稲葉浩志の歌声は訴えかけるのではなく、静かに寄り添ってくる。
そして、その問いのあとに続くのは「ぬくもり」という普遍的な言葉。
奪われていくもの、消えていくものがある中で、せめて手の中に残る温かさだけは永遠であってほしい。その祈りのようなフレーズが、聴く者の心に柔らかな余韻を残していく。
サビは高揚ではなく、むしろ静けさの中に力を宿す。
声の震えとアコースティックの響きが重なり合い、胸の奥に「人のぬくもりを忘れてはいけない」というメッセージを胸の奥深くに刻んでいく。
ブリッジに刻まれた短い言葉は、絶え間ない不安と向き合う人々の、終わりの見えない時間を映し出す。
あっというまに 日が暮れる
眠れないままに 日が昇る
ここに込められているのは、日常を奪われた者の視点だ。一日をやり過ごすことすら苦痛で、夜も眠れず、朝を迎えてしまう。
稲葉浩志は、このどうしようもない現実を飾ることなく書き記すことで、歌詞全体に「命の不平等」というテーマをさらに深く刻み込んでいる。
華やかな旋律も力強いバンドサウンドもない。だからこそ、このわずかな言葉を一層強く歌い上げることで、誰もが経験する「時間の流れ」を通じ、遠い出来事ではなく“自分の問題”として響かせる。
『あの命この命』レビューまとめ
「あの命この命」は、壮大なメッセージを掲げるのではなく、聴く者一人ひとりの心に静かに火をともすラストナンバーだ。
アルバムを閉じたあとも、その余韻は日常のささやかな瞬間に立ち上がる。大切な人を思い出したとき、ふとした温かさに触れたとき―この曲の問いが胸の奥から静かに蘇ってくるだろう。
音楽の力とは、忘れかけていた感情を呼び覚まし、日々に新しい意味を与えることにある。この曲は、その力を最もシンプルな形で示す稲葉浩志のバラードだ。
答えを探すのではなく、自分の中に芽生えた感情を確かめる時間として―ぜひ、この曲を手に取ってほしい。

このアルバムを通して感じたこと
『Peace Of Mind』を通して聴いていると、稲葉さんが「安らぎ」という言葉をどう捉えているのかが、少しずつ浮かび上がってくる気がする。
静かなアコースティックで始まったかと思えば、鋭く迫るロックにぶつかり、またやわらかなメロディに戻っていく。その起伏の中に「人の心のありのまま」が映し出されているようで、聴いていて妙に身近に感じられる。
アルバム後半に進むにつれて、空気はさらに濃くなっていく。「透明人間」が描く孤独は胸をえぐるほど切実だし、ラストの「あの命この命」では、命の重さに正面から向き合わされて息が詰まる。けれど、その重さを抱え込んでこそ、このアルバムは特別な輝きを放っているのだと思う。
劇的に気持ちを変えてくれるわけではない。けれど、聴き終えたあとにふっと深呼吸ができる─自分にとって『Peace Of Mind』は、そんなアルバムだった。
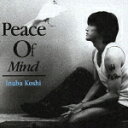
※本記事において引用している歌詞は、すべて稲葉浩志のアルバム『Peace Of Mind』に収録された楽曲からの一部抜粋です。著作権は各著作権者に帰属しており、当サイトは正当な引用のもとでこれを掲載しています。著作権に配慮して歌詞全文の掲載は行っておりません。






