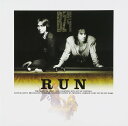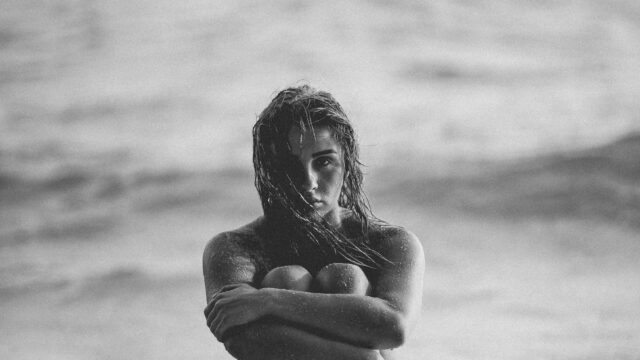B’z 6th Album『RUN』-全曲レビュー:がむしゃらだった自分を、もう一度抱きしめる-

UnsplashのSilas Baischが撮影した写真
走り続けることの苦しささえ肯定する音
B’zの6thアルバム『RUN』は、1992年のリリース以来、今も色褪せることなくエネルギーとメッセージを放ち続ける名盤だ。
攻めのロックサウンドと繊細なバラード、そして90年代の空気感を鮮烈にパッケージしたこの作品は、多くのファンにとってB’zの“原点であり到達点”とも言える存在だろう。
『RUN』は、どこまで行けるのか分からなくても、とにかく走り続けていたあの頃の自分をそっと呼び戻してくれる。胸を突き刺すような衝動と、その奥に潜んだ小さな弱さや迷いが、音の中で今も確かに息をしている。
がむしゃらだった過去の自分を肯定しながら、「まだ走れる」と今の自分に静かに教えてくれる。それがこのアルバムの何よりの魔法だ。
無理だと諦めていたことも、あの頃にはちゃんと意味があったのだと思わせてくれる。走り続ける苦しさも、立ち止まれない夜の孤独も、すべてがこの作品の中では肯定されている気がする。
聴き終えた後の静けさの中で、自分はこれからも走っていけると信じられる―だからこそ、このアルバムはいつまでも色褪せない。
Release:1992.10.28
※本記事では、B’zのアルバム『RUN』に収録された各楽曲について、歌詞の一部を引用しながら、その表現やメッセージについて考察しています。引用にあたっては、著作権法第32条に基づき、正当な範囲での引用を行っております。
表現される感情
【興奮状態】×『THE GAMBLER』
夢をつかむとき、人はどれだけ大胆にリスクを背負えるのだろうか。
B’zの6thアルバム『RUN』の1曲目「THE GAMBLER」は、そんな問いに真正面からぶつかっていく曲だ。
オルガンが静かに響き渡るイントロの空気を、松本孝弘のギターが鋭く切り裂いていく。そこから放たれるリフのサウンドが、一気に楽曲の緊張感を高めていく。
さらにホーンセクションが加わることでサウンドに華やかさが生まれ、稲葉浩志の豪快なシャウトが、聴く者の覚悟を試すように響き渡る。
運に身を委ねるのではなく、流れを変えてやろうとする意志が、この曲を一層力強いものにしている。
『RUN』は、B’zがシンセの枠を飛び出し、バンドとしての生のエネルギーで勝負したアルバムだ。「THE GAMBLER」はその先頭で、“挑む者だけが見られる景色”を力強く示している。
何を賭ける? 全力で挑む人へ贈る『THE GAMBLER』
Aメロは、この主人公の生き様を鮮やかに示す自己紹介だ。
僕はギャンブラー 麗しのギャンブラー
侍れ侍れ美しいものよ
信じる者に魂を惜しげもなくつぎこんだ
危うい賭けに躊躇なく飛び込んでいく主人公の危険さと、それを誇りのように掲げる強さ。無謀にも思える夢や欲望ですら、自分のもとに引き寄せようとする大胆さが感じられる。
「信じる者に魂を惜しげもなくつぎこんだ」という一節は、聴き手に“信じたものに賭ける覚悟”を問いかけているようだ。
信じたものにすべてを賭けるという純粋な覚悟から、勝負に生きる美学がはっきりと伝わってくる。
Bメロでは、主人公の覚悟がさらに鮮明になっていく。
ぐずってる暇があるなら 勝利の美酒に酔いましょう
自業自得の街道を 300km/h 走り抜けるぜ
立ち止まって迷うより、まず行動し、勝利したときにはその喜びを遠慮なく味わえという力強いメッセージが込められている。
どんな結果も誰のせいにもせず、自分が選んだ道の責任をすべて引き受ける潔さがはっきりと見える。
さらに、その道を300km/hという極端なスピードで駆け抜ける姿からは、結果がどうなろうと限界まで振り切って生きる破天荒さと、わずかな一瞬に全てを賭ける男の生き様が伝わってくる。
サビでは、この曲が伝えたい“勝負に出ること”の真髄がシンプルな言葉で突きつけられる。
Oh!何を賭ける?イチかバチかエブリデイ
ひっくりかえそう ダイスふろう
流れを変えてやろう
何を失う覚悟があるのか、日常を自分の勝負の場にできるのかと問いかけてくる。
「流れを変えてやろう」という一言に、この曲の核が凝縮されている。運に任せるのではなく、一度きりの勝負にすべてを賭けてでも、流れを自分の手で変えてやろうという強い意志。
流されるのではなく、賭けに出て自分が流れを変える側に立つ。Aメロ、Bメロで描かれた覚悟と行動力が、ここで、運命を自分で切り開く力としてはっきりと形になっていく。
ブリッジパートでは、世間の視線が主人公に向けられる。
問いかけを知らぬ人たちが にんまりまた噂する
どうせ儲け話なら もっと稼いで地球を買い戻せ
何かを本気で賭けて挑もうとする主人公を、遠巻きに見て面白がりながら噂する人々の冷ややかさが感じられる。
そんな人々の噂など気にも留めず、どうせ勝負に出るなら中途半端では終わらせないという主人公の破天荒さが一気に爆発する。
小さな儲け話なんかではなく、地球を丸ごと買い戻すくらい大きな夢に賭ける。そんな誰にも真似できない大胆さと、勝負に生きる美学がはっきりと刻まれている。
『THE GAMBLER』レビューまとめ
B’zが『RUN』で提示したのは、生の音と全力のエネルギーで勝負する“ロックバンドとしての覚悟”だった。その幕開けを飾る「THE GAMBLER」は、ただのハードロックナンバーではない。
信じたものにすべてを賭ける潔さ、迷いを断ち切って突き進む行動力、世間の冷たい視線をものともしない破天荒さ―この一曲に込められた“勝負に生きる美学”は、今も聴く者の背中をそっと押してくれる。
もちろん、現実にはリスクを考え、上手くいかなかったときのB案を用意しておくことも大切だ。それでも、この曲が教えてくれるのは、最後の一歩を踏み出す瞬間に必要なのは計算だけじゃなく“賭ける勇気”だということだ。
人生をイチかバチかで振り切る勇気をくれる一曲を、ぜひ味わってほしい。
ギターの轟音とオルガンの荘厳さ、ホーンの華やかさ、そして稲葉浩志の声が、きっと心の奥に眠っていた“まだ挑める自分”を呼び起こしてくれるはずだ。
あの黄金の列車に乗り込むのは、今この瞬間のあなたかもしれない。

【気を落とす】×『ZERO』
11th Single
Release:1992.10.07
せわしない生活の中で、心が渇き切ってしまう瞬間がある。
「ZERO」はそんな日常の苛立ちや行き場のない疲れを、ハードロックの衝動で一気に解き放つ一曲だ。
渋滞の赤いランプにじっと足止めされ、空っぽの冷蔵庫を前にため息をつく。何気ない日常の断片に、誰もが感じる孤独と虚しさが滲み出している。
だからこそ「ゼロになろう」という言葉は、逃げ出すためではなく、何度でも自分を立て直せるというメッセージとして響く。
心をまっさらにして、もう一度走り出したい日に。「ZERO」は今も、胸の奥で静かに鼓動を打ち、そっと背中を押してくれるはずだ。
『ZERO』─渇いた心をまっさらに戻す、再スタートの衝動
Aメロでは、何気ない日常の景色の中に、進みたくても進めない息苦しさと、自分でも止められない思考の渦に、ゆっくりと飲み込まれていく心の揺らぎが描かれている。
ぎらぎらした街をぬけ さっさと家に帰ろう
思わぬ工事渋滞で 赤いランプを眺めりゃ
また考えすぎのムシがじわり じわりと湧いてきて
僕は僕自身に 一日分の言い訳をはじめる
都会のまぶしい光にさらされ続けた心が、もう限界だと訴える。立ち止まった時間が、頭の中に余計な考えを呼び起こし、抑えていた不安や後悔に押しつぶされそうになる。
結局、自分を納得させるために一日の出来事を振り返り、言い訳を重ねてしまうそんな自分自身に、どこか冷めた孤独が漂っている。
そしてAメロで膨らんだ行き場のない思考は、Bメロで一気に危うい衝動へと飛び火する。
たちの悪いくせだね
このまま車ごと君の家につっこもうか
なんてことまで浮かんでくる
ただ疲れて帰りたいだけのはずなのに、頭の中には無謀で突拍子もない妄想が湧いてくる。極端な想像は、行き詰まった心がどこかに逃げ場を求めている証拠だろう。
誰もが心の奥に抱えたことのある衝動。現実では決して実行しないけれど、思わず頭をよぎるその瞬間を、嘘偽りなくリアルに表現している。
AメロとBメロで溜め込んだ日々の息苦しさや行き場のない衝動が、サビで一気にあふれ出す。
今あいたい すぐあいたい 砂漠の真ん中で
ねむりたい もうねむりたい 全部凍らせたまま
流れよう 流されよう この波に揺らされ
ゼロがいい ゼロになろう もう一回
「今あいたい すぐあいたい」という直線的な欲求の叫びには、誰かに救われたい、誰かと繋がりたいという切実さがそのまま表れている。
孤独に沈みきった心が「砂漠の真ん中」という比喩に置き換わり、乾ききった自分を誰かと一緒に潤したいという渇望が強調される。
その一方で「眠りたい」という言葉は、ただ物理的に眠りたいのではなく、すべてを凍らせて一度止めたい、もう考えなくて済む場所に身を置きたいという強いリセット願望を示している。
そして「流れよう 流されよう」というフレーズは、もはや自分の意思だけではどうにもならない心を、波に揺らされるように委ねてしまいたいという諦めと解放が同居している部分だ。
現実に押し潰され、思考に飲まれ、それでももう一度だけまっさらに戻って、新しく自分を始めたい。
そんな破壊と再生の衝動が、荒々しいハードロックサウンドと稲葉浩志の熱いボーカルに支えられ、サビで一気に解き放たれている。
曲の後半、溜め込んできた疲れと苛立ちが膨れ上がり、どうすればいいのかすら分からない混乱がむき出しになるのが、このブリッジパートだ。
どうすりゃいいのヘンになりそう ネオンで空が曇ってる夜は
何をどこまでじればいいか 君が僕に教えてよ
「ヘンになりそう」という言葉には、もう一人では整理しきれない心の荒れ模様がそのままにじんでいる。
ネオンに覆われた曇った空は、光の多さとは裏腹に、主人公の孤独をより濃く浮かび上がらせている。キラキラと眩しいはずの街の灯りは、むしろ心を覆い隠し、救いのない夜を強調する。
自分ではどうにもならない、曇った思考の渦の中で、唯一の光のように「君」が差し込む。それは、無防備な弱さを許してくれる存在を求める切ない願いだ。
このブリッジは、聴く人の孤独を揺さぶりながら、それぞれの“愛する人”をそっと呼び覚ましていく。
『ZERO』レビューまとめ
都会の喧騒にすり減った心も、どうしようもなく溢れる孤独も、この曲に預けてしまえばいい。
どれだけ足止めされても、何度でもゼロに戻って走り出せる。「ZERO」には、そのたびに勇気を分けてくれる衝動が息づいている。
心がまっさらに戻る音を浴びながら、また新しい自分を始めればいい。

【神経が高ぶる】×『紅い陽炎』
乾ききった心の奥に潜んでいた小さな痛みが、夏の陽炎に触れて静かに揺れ始める。
地面の熱気で空気がゆらめき、遠くの景色がぼんやりとかすむ―そんな“陽炎”は、この曲では触れようとしても形をとどめない儚い愛の象徴だ。
「紅い陽炎」は、触れれば消えてしまいそうな儚さと、抗えない情熱が交わる隠れた名バラードだ。
松本孝弘のギターが奏でるイントロの“泣きのソロ”は、最初の一音からすでに言葉を超えている。澄んだクリーントーンが胸の奥のひび割れをそっとなぞり、稲葉浩志の声と絡み合って、踏み込めば壊れると知りながら、互いに触れ合ってしまう恋の輪郭を描き出す。
稲葉浩志の張り裂けそうな熱唱に呼応するように、ギターはさらに深く泣き、間奏ではもう一度、抑えきれない感情を解き放つ。
そして最後には、すべてを歌い尽くしたあとの余韻まで、ギターの音色が静かに抱え込んでいく。
触れれば消える陽炎のように儚く、胸を焦がすように熱い―そんな危うい愛の美しさを、この一曲でぜひ感じてほしい。
輪郭を持たぬ愛が胸を焦がす『紅い陽炎』
Aメロでは、決して触れてはいけないと知りながらも、触れずにはいられなかった二つの心が、そっと近づく瞬間が描かれている。
渇きかけた心に
小さなひびひとつ
互いのそれを触れ合った
夏の日
それは真夏の、陽炎が地面の熱をすくい上げて揺らぐ昼下がり。
ひびの隙間から滲む寂しさは、ふいに同じ傷を抱えた誰かの心と触れ合い、互いの欠けた輪郭をなぞるように熱を帯びていく。
揺らめく空気に溶けるように、形を持たない想いが、胸の奥にそっと火を灯していく。
Bメロでは、心のひびに落ちた火種が、抑えようとしても抑えきれない“確かな炎”に変わっていく瞬間が描かれている。
消えゆく季節に ふたり
逆らうように
炎を産んで
季節が移ろい熱が失われていくはずの夏の終わりに、ふたりだけがその流れに逆らってしまう。
ほんの小さなひびから生まれた寂しさが、季節に逆らって熱を宿し、ふたりの胸の奥にそっと火をともし、静かに広がっていく。
サビでは、抱き締めれば遠ざかり、遠ざけるほど近づいてしまう―そんな矛盾を飲み込みながら、ふたりが抑えきれない衝動に身を任せ、激しく乱れていく官能的な一瞬が描かれている。
抱き締めるほど君は
消えてしまいそうで
戸惑いの中 熱く
乱れ羽ばたいた
抱き締めるほどに君は陽炎のように輪郭を失い、触れれば触れるほどすり抜けていく儚さに胸が軋む。
それでも離せない想いが戸惑いの中で熱を孕み、理性を引き裂くように溢れ出していく。「乱れ羽ばたいた」という短い言葉には、理性も言い訳もすべてを振り切って、衝動が一気に爆ぜる荒々しさが潜んでいる。
ふたりの呼吸を荒くなり、閉じていた心の奥で眠っていた熱が、火花のように弾けていく。
ブリッジパートでは、進むことも引き返すこともできないまま、揺らぐ葛藤を吐き出している。
このままか これ以上か
愛の形 何か欲しい
触れれば壊れるはずの想いが炎に変わり、衝動に乱れたその先で、形を持たないまま揺らいできた関係に、許されないと知りながらも「愛の形」という確かな輪郭を求めてしまう。
『紅い陽炎』レビューまとめ
ひび割れた心に触れた小さな熱が、季節の流れに逆らいながら、揺らぐ陽炎のように形を持たないまま燃え広がる。
抱き締めれば遠ざかり、遠ざけるほどに惹かれてしまう矛盾を呑み込み、理性さえほどけて乱れるその先で、ふたりは許されないと知りながらも愛の確かな輪郭を欲してしまう。
掴めそうで掴めない―触れた瞬間に壊れてしまう熱を、私たちは誰もが胸のどこかでひそかに抱えているのかもしれない。
だからこそ、この曲が灯す小さな炎は、聴くたびにあなたの奥でそっと宿り、いつまでも消えそうで消えない余熱として、また心を焦がすのだろう。

【希望に満ちた】×『RUN』
何もない場所から始まった夢が、いつしか誰かと肩を並べて走る物語になる。
B’zの「RUN」は、ただのロックナンバーではない。
「よくまあここまで俺たちきたもんだな」この一節に込められたのは、バンドとして積み重ねた時間と、共に歩んだ仲間への感謝、そして聴く人それぞれの人生に寄り添う大きな肯定だ。
イントロでは、美しいアルペジオにドラムが重なった瞬間、そこに重厚なホーンの音色が響き渡る。その壮大な音の広がりが、聴く人の胸を揺さぶる。荒野を走り抜けるようなこの曲は、誰かと笑い合いながら、時に傷つきながらも前に進んできた自分自身を思い出させてくれる。
B’zがこの曲で歌った絆と希望は、時を超えて今も新しい。何度でも走り出せる力を、胸の奥に灯してくれるナンバーだ。
どこまでも走れる。止まりそうな心を動かしてくれる『RUN』
Aメロは、無名だった頃から積み上げてきた時間への誇りがにじむ始まりだ。
よくまあここまで俺たちきたもんだなと
少し笑いながらおまえ 煙草ふかしてる
何もないところから たよりなく始まって
数えきれない喜怒哀楽をともにすれば
Aメロを聴くと、B’zが歩んできた道のりが、そのまま自分自身の物語にも重なる気がしてくる。
何もない場所から始まって、頼りなく進んだ日々。誰かと笑い合いながら、数えきれない喜びや悲しみを分かち合ってきたことを思い出させてくれる。
煙草をふかす仕草の向こうに見えるのは、肩肘張らない信頼の風景。自分もまた、誰かと一緒にここまで来たんだ―そんなささやかな誇りと感謝を、そっと思い出させてくれるAメロだ。
Bメロの言葉に触れたとき、自然と心に誰かを思い浮かべる人もいるはずだ。
時の流れは妙におかしなもので
血よりも濃いものを作ることがあるね
血のつながりがなくても、時間を重ねることで特別な絆になる人たちがいる。
それは友達かもしれないし、職場の仲間かもしれないし、新たに家族になった人かもしれない。
喜びも怒りも悲しみも一緒に越えてきた時間が、気づけば“血よりも濃い”つながりを作りだ出していく。そんな人とのつながりの不思議さと尊さを、静かに感じさせてくれるフレーズだ。
サビは、たとえ何もない場所でも、誰かと笑い合えれば、どこまでも走っていけることを思い出させてくれる。
荒野を走れ どこまでも 冗談を飛ばしながらも
歌えるだけ歌おう 見るもの全部
なかなかないよ どの瞬間も
苦しいときも、孤独なときも、冗談ひとつで前に進める強さが人にはちゃんとあるんだと教えてくれる。
目の前の景色や何気ない日々、そのすべてがもう戻らない宝物なのだろう。ありふれた瞬間さえも、かけがえのない小さな奇跡だと気づかせてくれる。
走り続けることに疲れたとき、立ち止まりそうになったとき、「RUN」のサビはいつも静かに背中を押してくれる。
泣いて、笑って、そしてまた一歩を踏み出す。その先に、誰もがたどり着ける場所がきっとある。
ブリッジでは、「特別じゃない存在である人間」に価値を与えるのは、出会いだというメッセージが伝えられている。
人間なんて誰だって とてもふつうで
出会いはどれだって特別だろう
だれかがまってる どこかでまっている
死ぬならひとりだ 生きるなら ひとりじゃない
だれかがまってる どこかでまっている
死ぬならひとりだ 生きるなら
どんなに平凡で小さな自分でも、誰かと出会うだけで、人生は特別になる。
生きていく中で、誰だって孤独に立ち止まる夜がある。でもこのフレーズを聴くと、遠くにいても誰かが自分を待ってくれていると思えてくる。
たとえまだ出会っていなくても、名前を知らなくても、世界のどこかで自分を待つ誰かがいる。だからこそ、生きるなら、ひとりじゃない。
このパートは、そんな力強い約束をそっと胸に刻んでくれる。
『RUN』レビューまとめ
この曲は、自身の歩みを思い出させながら、聴く人それぞれの物語に静かに寄り添ってくれる。
誰かと笑い合い、支え合いながら進んできた時間があるからこそ、今の自分がいる。出会いのひとつひとつが特別で、どんなに小さくてもその奇跡は胸の奥に残り続ける。
立ち止まりたくなる夜もある。それでも遠くにいる誰かを思いながら、もう一歩だけ前に進んでみる。そんな力を、静かにくれるのがこの歌だ。
荒野を走れ。どこまでも。
また笑いながら走り出せる自分でいるために、この曲はいつだってそばにある。

【激怒】×『Out Of Control』
「Out Of Control」の意味は「制御不能」。まさにそのタイトル通り、縛り付けられた息苦しさと、どこにもぶつけようのない苛立ちを、感情のままに爆発させる一曲だ。
骨太なロックへ大きく舵を切ったアルバム『RUN』の中でも、「Out Of Control」は特にその転換点を象徴する存在だ。
荒々しくギラついたギターリフと稲葉浩志の挑発的なシャウトが、週刊誌や暴走するメディア報道への苛立ちを、爆音で蹴散らすように響き渡る。
間奏では、松本孝弘のギターソロとオルガンの火花を散らすような掛け合いが、曲に抑えきれない衝動を吹き込んでいる。
思い通りにならない世の中。覗かれ、操られ、噂される息苦しさ。そんな鬱屈を音の熱で燃やし尽くし、すべてを解放してくれるのが「Out Of Control」だ。
制御不能の疾走感が全身を突き抜ける─『Out Of Control』
A〜Bメロは、日常のささやかな一幕から始まる。
Oh 目を擦りながら週刊誌 ぱっと開ければ出るでしょ
惚れた腫れたひとのこと 見ちゃう自分もこまりもんだ
もう大きくなったんだから 他に書くことあるだろうと
ぼやいても怒鳴っても無駄 ペンは剣よりも強いんだってさ
週刊誌に並ぶのは、惚れた腫れたのゴシップばかり。ロクでもないことばかり書き立てる週刊誌への苛立ちと、分かっていながらページをめくってしまう自分への情けなさが、稲葉浩志のぼやき混じりの歌声に滲む。
「もう大きくなったんだから 他に書くことあるだろう」と吐き捨てながらも、「ペンは剣よりも強いんだってさ」と、報道の力のやっかいさを苦々しく突きつける。
くだらない記事に振り回される鬱陶しさと、そんな現実から目を背けられない自分へのムカつき。
そうして日々積み重なる小さな苛立ちが、サビでついに抑えきれずに噴き出していく。
ぼくたち
Out of control がんじがらめよ なんでそうなるの
Don’t you love me? 今は自分をタナに上げて
Drive me crazy つばを飛ばして言ってやる
I don’t like you no!
そして、聴く人が胸の奥に飲み込んできた小さな苛立ちとも共鳴し、その心にも火をつけていく。どうしようもなく縛られて、身動きが取れないまま、心の奥が制御不能になる感覚。
「Don’t you love me?(僕のこと愛してないのか?)」なんて言葉に、優しさなんか欠片もない。きっと誰もが、人のことを責めて、自分は棚に上げる。キレイごとばかりじゃ何も変わらない。
「Drive me crazy(気が狂いそうだ)」黙って溜め込んでいた怒りを全部ぶちまけ、最後の「I don’t like you no!(お前なんか大嫌いだ)」で抑えていた感情を一気にぶん投げる。その叫びがたまらなく痛快だ。
見たくないのに結局覗いてしまう自分が嫌になる。くだらない噂に振り回されている自分にもうんざりする。
「Out Of Control」は、言えないまま溜め込んだ心に刺さった小さな引っかかりを、あとかたもなく燃やし尽くしてくれるロックナンバーだ。
『Out Of Control』レビューまとめ
噂話に振り回されて、見たくもないものを覗いてしまって、結局は自分で自分を縛って苛立つ。そんなくだらない日々に、「もういいだろ」と言わんばかりに火をつけるのが、この曲だ。
何もかも思い通りにならない世の中なんて知ったことじゃない。黙って飲み込むくらいなら、この一曲で全部ぶちまけて、灰にしてしまえばいい。
抑え込んできた自分なんか、最後に丸ごとぶん投げてしまえ。それくらいでちょうどいい。それが「Out Of Control」だ。

【興奮した】×『NATIVE DANCE』
「NATIVE DANCE」。直訳すれば“本能の踊り”。
飾らず、嘘をつかず、心の奥に眠る野生の衝動を、そのままリズムに乗せて解き放つ。このタイトルには、心を裸にして向き合おうとする、そんな率直なコミュニケーションへの願いが込められている。
この曲は、まるで聴き手を太古の祝祭に連れ戻すかのように、温かく、どこか原始的に響く。軽快なリズムにホーンやオルガンが重なり合い、どこかネイティブアメリカンを思わせる民族的なコーラスが寄り添う。
“アーイ アーイ…”と繰り返される声が、曲全体を柔らかく包み込みながらも、不思議な中毒性を生む。そして中盤、忘れられないのが稲葉浩志の雄叫びだ。ギターソロへ突入する直前、理性を切り裂くように放たれる「アワワワ…」のシャウトは、まさに野生に戻る瞬間だ。言葉にならない叫びが、息を呑むほど自然に松本孝弘のギターソロにバトンを渡し、聴き手の胸の奥を一気に解き放つ。
飾りすぎてたみたい」「何も隠さないから」―嘘のない言葉と、むき出しの叫び、そして解放のギターがひとつに絡み合い、誰もが胸の奥にしまい込んだ“ありのままの自分”を、そっと誰かに見せたいと願う小さな勇気が呼び覚ましてくれる一曲だ。
心を裸にするサウンド―『NATIVE DANCE』がくれる小さな勇気
Aメロは、曲全体のメッセージのはじまりを描いているパートだ。
飾りすぎてたみたい
無理してたわけじゃない
喜ぶ顔だけを
見たがってたアオい自分
主人公がどこかで無理をしてきた自分に気づいていることがわかる。そして、誰かのために良い人であろうとする行動が、本当の気持ちと少しずつズレていったことも見えてくる。
それでも“アオい”という一言には、未熟さだけでなく、純粋で不器用だった過去の自分への優しい眼差しもにじむ。
相手を傷つけないように、嫌われないように、本音を隠してでも相手を笑顔にできればそれでいい―そんな健気な思いが、滲み出ている。
その青さを脱ぎ捨てて、どんな風に何も隠さない自分へと戻っていくのか。そんな「飾りすぎてた自分」を乗り越えようとする、その一歩目が、このBメロに表れている。
ホレたから
なおさらに時間かかったけど
一度あなたに見てもらう
必要があった
ありのままを
ただ好きだからこそ、本当の自分を見せるのには、余計に勇気が必要だ。恋心が大きくなるほど、自分の弱さや格好悪い部分は見せられなくなる。
「一度あなたに見てもらう必要があった」この一節は、嘘のない自分を相手にさらけ出すことでしか、この恋は本物にならないと決意する声だ。
どんなに時間がかかっても、嘘を脱ぎ捨てた自分を、この人にだけは知ってほしい。好きだからこそ揺れる不安と、それでも一歩踏み出そうとする必死さが息づいている。
そしてBメロでやっと決めた「ありのままを見せる」という覚悟が、サビで一気にむき出しになる。
ちゃんとみてボクの最高の涙
何も隠さないから
理由がわかるなら抱き締めて
野生に戻るよ NATIVE DANCE
強がることも隠すことも、もういらない。弱さだと思っていた涙さえ、今の自分にとっては誇れる証なんだと叫ぶ。
怖くてもいい、震えてもいい。本音を隠さないことだけが、いまの自分にできるすべてだ。遠まわしの嘘も、分かり合えないふりも、もういらない。言葉にできない想いの奥まで、まるごと受け止めて、嘘じゃない温もりでそっと包んでほしい。
誰かの前でだけ無防備になって、余計な言葉も飾りもすべて脱ぎ捨て、本能のままに自分をさらけ出す。その一瞬こそが、「NATIVE DANCE」のすべてだ。
涙も声も体も―全部を使って本音をぶつけ合う、その勇気を思い出させてくれるサビだ。
サビでむき出しにした心を、ラスサビではさらに大きく羽ばたかせている。
ちゃんとみてボクの最高のステージ
何も隠さないから
キライならキライと合図して
それからはじまる
あなたへの努力は いつまでも
惜しむつもりはないよ
お互いの裸の声だけが
導いてくれる
NATIVE DANCE
隠してきた涙をさらけ出した主人公は、いまやその弱さごと抱えて、胸を張ってステージに立っている。
嘘をつくくらいなら、嫌われたほうがいい。好きなら好き、嫌いなら嫌い―すべてをさらけ出した先でしか、本当の関係は始まらない。
相手とぶつかり合いながらも、一緒に歩きたいという願いがここにある。裸の心をぶつけ合った先にこそ、ふたりだけの歩幅で寄り添い続けていく未来が待っている。
『NATIVE DANCE』レビューまとめ
誰かの前でだけ、本当の声をさらけ出せる瞬間がある。
『NATIVE DANCE』は、その小さな勇気を思い出させてくれる一曲だ。強がりも飾りも脱ぎ捨てて、裸の声だけでぶつかり合うとき、はじめて心は繋がっていく。この曲は、その当たり前だけど一番難しいことを、忘れないように刻んでくれる。
聴くたびに、自分の中の“野生”がそっと目を覚ます。それが『NATIVE DANCE』だ。

【当惑する】×MR. ROLLING THUNDER
荒涼とした空気を切り裂くように、遠い誰かの孤独を思い起こさせる英語のコーラスで幕を開ける「MR. ROLLING THUNDER」は、その一声から聴き手を広大な大地と孤独の旅へと誘う異色のロックナンバーだ。
“ローリングサンダー”とは、ネイティブアメリカンの祈祷師を指すとも言われる。若き稲葉浩志がひとり旅で触れたアメリカの自然と文化、その壮大さと、人間の欲望への問いかけが力強いバンドサウンドに刻み込まれている。
Aerosmithの「Love In An Elevator」に影響を受けたとも言われ、その類似はしばし批判の対象にもなる。それでもB’zは、その引用を真似事で終わらせることはしない。
骨太なギターを中心に据えたサウンドに、ホーンの厚みを重ね、自分たちなりのアメリカン・ハードロックを響かせている。
誰が泣いているのか─荒野に響く『MR. ROLLING THUNDER』
Aメロからすでに、「MR. ROLLING THUNDER」が問いかけるテーマが生々しく立ち上がる。
長いドライヴに疲れて そびえる岩の間をかけ上がった uh
僕は真っ赤な大地の聖なる ワレメの中から 生まれた きっと
延々と続くハイウェイを走り、赤く乾いた大地にそびえる巨大な岩の間を駆け抜ける光景が目に浮かぶ。
「真っ赤な大地の聖なるワレメの中から 生まれた きっと」この挑発的な言葉が、この曲をただの旅の歌に終わらせない。
大地を裂くその亀裂は、母なる自然の胎内のようでもあり、同時に人間が資源を切り取り、欲望を刻む傷跡のようでもある。
自分はそこから生まれた―そう歌う稲葉浩志の言葉には、自然とつながる人間の小ささと、どこまで自然を切り裂き奪い尽くすのかという痛みを帯びた問いが、ひそやかに宿っている。
Bメロでは、舞台が大地から空へと広がる。
太陽の下で祈りを捧げ ヴィジョンを求め踊り続ける
とがった稲妻が 低い雲に隠れて見守っている
ネイティブアメリカンの儀式を思わせる祈りの光景が重なる。ここでいう“ヴィジョン”とは単なる幻ではなく、人間が自然と対話し、自分の内側を探りながら、現実の中で迷い、もがく自分を見つめ直すための啓示のようなものだろう。
太陽と雲、稲妻に見守られながら、何かを問い、何かを得ようとする姿は、厳しい現実の中でどうにか希望を探し、それでも前に進もうとする人間の小ささと力強さの両方を映し出している。
サビは、曲全体の核心を突く問いと希望の結晶のようなパートだ。
誰が泣いているのか 教えてよ MR.ROLLING THUNDER
嵐の海で迷ってる 僕らは何処に向かっているのか
黒い髪をなびかせて 踊る風の声を聞いてる
雨のち晴れだと
「誰が泣いているのか」という呼びかけは、誰か特定の存在ではなく、嵐の中で迷いながら生きる僕ら自身の姿を指しているのかもしれない。
大地に生まれ、空に向かって祈った人間が、それでもどこへ向かえばいいのか分からず、
荒れた海を漂うように迷い続ける。そんな孤独が、激しい音の向こうで脈打っている。
それでも、髪を風になびかせ、自然と一体になって耳を澄ます姿には、何かを感じ取り、どこかに光を探そうとする人間の静かな願いがある。
そして最後に置かれる「雨のち晴れだと」という言葉。荒波の向こうにかすかに覗く晴れ間。どれだけ迷い、嵐に翻弄されても、人はわずかな光を信じて進むしかない。
そんなかすかな夜明けの断片が、この曲のサビを支えている。
『MR. ROLLING THUNDER』レビューまとめ
大地の裂け目から生まれ、太陽の下で祈りを捧げ、空を見上げても、人はいつだって答えを探しきれないまま、嵐の海を漂っている。
それでも風の声に耳を澄まし、荒々しい雷鳴の奥に、かすかな光を探し続ける。
「MR. ROLLING THUNDER」は、そんな人間の孤独と欲望、そして胸の奥に残る小さな願いを、熱を帯びたギターと渇いた叫びに宿した一曲だ。
タイトルの“ローリングサンダー”は、荒々しく転がる雷鳴そのものであり、人の内側にくすぶる問いを何度でも呼び覚まし、果てしなく響き続ける声なのかもしれない。

【穏やか】×『さよならなんかは言わせない』
別れの言葉を越えて、もう一度会えることを信じさせてくれる曲がある。
「さよならなんかは言わせない」は、稲葉浩志自身の大学卒業式をモチーフに生まれた、前向きな別れ歌だ。
キャッチーなミディアムテンポに乗せて、枯れたギターが胸を締めつけるように響く。松本孝弘による“泣きのギターソロ”はB’z屈指の名演と評されるほどメロディアスだ。
そして何より、この曲の余韻を深く刻むのが、アウトロを排し、ラストのサビをあえてアカペラで締めくくる演出だろう。「さよならなんかは言わせない」— 繰り返されるこの一節が、ギターの余韻を背にして歌声だけで響き渡るとき、別れは新たな約束へと形を変える。
別れ、旅立ち、そして再会。
一度聴けば、誰の胸にもあの日の春が甦ってくるはずだ。
別れを約束に変える歌─『さよならなんかは言わせない』
Aメロでは、潮風と港が別れの物語を静かに映し出している。
潮風は強く僕の頬をなでている
君を故郷に送る船が もう着くころ
別れを告げることなく遠ざかっていく相手を、主人公はどこか離れた場所から想っている。
相手を直接見送ることもなく、潮風を感じながらその船を想う姿には、言葉にできない寂しさと、会えなくなる現実への切なさが漂っている。人混みや賑わいは描かれず、あるのは潮風の音と、別れを前にした静かな時間だけだ。
Bメロでは、主人公の胸の内がより生々しく言葉になる。
そんなに遠くに行くわけじゃないのに 馬鹿だよね
別れることがただ悲しいことにしか思えないから 見送れない
自分でもどうしようもない寂しさと、相手を思う気持ちの大きさが伝わってくる。
本当は笑って送り出したいのに、それができない。「別れることがただ悲しいことにしか思えないから」という一節には、強がりや美談を手放した、誰もが抱える素直な弱さがにじんでいる。
だからこそ、見送ることもできず、潮風の中でただ立ち尽くす主人公の姿が心に刺さる。
サビでは、別れの寂しさを受け止めながら、それを「また会える」という約束に変える力強い言葉が歌われている。
さよならなんかは言わせない
僕らはまた必ず会えるから
輝く時間を分けあった
あの日を胸に今日も生きている
曲中で何度も繰り返される「さよならなんかは言わせない」というフレーズには、離れてもつながっていたいという主人公の願いと祈りが込められている。
そして、ただ思い出を懐かしむのではなく、かつて分け合った時間を「今を生きる」力に変えている。だからこそ、このサビには儚さではなく、どこか前を向く眩しさがある。
別れを拒絶するのではなく、別れを受け入れたうえで「さよなら」と言わせない―その真っ直ぐで少し不器用な強さが、この曲を聴く人の背中をそっと押してくれるのだろう。
曲のラストに置かれたアカペラパート、声だけで締めくくるこの終わり方が「また会える」という約束を一層強く胸に刻ませる。
さよならなんかは言わせない
淋しそうに太陽が沈んでも
小さな星で愛しあった
君は今もきっと笑っている
一日の終わりに感じる切なさと孤独を抱えながらも、遠く離れた君が笑っていると信じる─そんな想いが、楽器に頼らない稲葉浩志のまっすぐな歌声だけでそっと届けられる。
別れを思うときの心細さと、再会を信じる強さ。その両方が、静寂の中でいっそう色濃くにじんでいく。
だからこそ、このアカペラで終わる一瞬の静けさが、「さよならなんかは言わせない」という言葉を、ただの別れの否定ではなく、再会を願う祈りへと変えていくのだろう。
『さよならなんかは言わせない』レビューまとめ
別れの寂しさを正面から受け止めながら、「また会える」という約束へと変えてくれる─「さよならなんかは言わせない」は、そんな優しさと力強さを併せ持つ一曲だ。
胸を締めつける“泣きのギターソロ”が別れの切なさを響かせ、ラストのアカペラがその想いを声だけでそっと届ける。
弱さと希望を抱えた言葉が、潮風のように静かに胸に吹き抜けていく。別れに揺れる心細さも、再会を信じる小さな希望も、すべてが歌詞とメロディに刻まれている。
だからこそ、春や旅立ちの季節だけでなく、ふと立ち止まりたくなる瞬間にも、この曲は静かに寄り添い続けてくれるはずだ。
「さよならなんかは言わせない」―その言葉は、今日も誰かの胸で小さく灯り続けている。

【孤独】×『月光』
静寂を照らす“月光”のイントロ。
夜の息づかいを纏いながら響くシンセとアルペジオの音色が、青白い光をそっと灯し、心の奥に潜む孤独や諦めを静かに浮かび上がらせる。
松本孝弘のギターソロから生まれたという曲名が示すとおり、その音色はただの伴奏ではなく、月の光のように淡く、ときに鋭く心の奥を射抜いてくる。
ささやくように始まる稲葉浩志の歌声は、言葉にならない想いを胸の奥に沈めながらも、やがて抑えきれない激情を一気に解き放ち、夜空を裂いてゆく。
荒ぶる感情を抑えきれないまま夜空に解き放たれる松本孝弘のギターソロの鋭さと熱量が、稲葉浩志の胸の奥から絞り出されるシャウトと重なった瞬間、「月光」はただの幻想ではなく、むき出しの本音が溢れ出す現実へと変わっていく。
静寂の中で抑え込んできた想いを、ギターが荒々しくかき乱し、歌声がその渦に飛び込む。二人の音が交わることで生まれるのは、抑制と衝動がせめぎ合う一瞬の輝きだ。
夜の静寂と、胸の奥で荒ぶる感情。幻想と情熱が、交わるようでいて交わりきれない―「月光」は、そんな不完全ささえも美しいと思わせてくれる名バラードだ。
『月光』― 幻想と現実が交錯する名バラード
A〜Bメロは、抑えきれない想いが夜の静寂に滲む瞬間をそっと描き出している。
眠りにおちてゆく その横顔を
むさぼるように見つめ
胸の響き 悟られぬよう
青く染まる部屋を抜け出した
眠りに落ちていくその横顔を、ただ見つめるだけでは足りず、むさぼるように目で追ってしまう。
胸の奥で鳴り響く熱を悟られないように、青白い月光に染まる部屋をそっと抜け出すその背中には、触れたいのに触れられないもどかしさと、叶わぬ愛と知りながらも手放せない切実さが滲んでいる。
夜の静寂に潜む欲望と、どうしようもなく孤独な影。この静けさがあるからこそ、後に訪れる激情がひときわ強く、胸の奥を揺さぶってくる。
サビでは、相手のすべてを奪い尽くしたいという激しい独占欲が、言葉の端々から静かに溢れ出している。
すべてを盗みたい かすかに漏れる息まで
なのにいつかは離れて行くと男は呟いている
目に見えない“息”までも欲するその渇望は、愛情の枠を越えた熱を宿している。
けれど続くのは、「なのにいつかは離れて行くと男は呟いている」という静かな諦めの言葉。
どれほど求めても、いずれは離れてしまう運命を知りながら、それでも欲せずにはいられない矛盾した想いが、静かな呟きの中にひそんでいる。
寄り添いきれない二人の姿が、月光に照らされるように淡く浮かび上がる。
ブリッジパートでは、静かに抑え込んできた感情が、一気にうねりをあげて目を覚ます。
波のうねりのような 正直なわがままを
もっとぶつけてくれ ごまかしはしない
あなたを抱き締めよう
波のように寄せては返す心の揺れを、もうごまかさないと決めた瞬間。遠慮も嘘もいらない。すべてをさらけ出してほしいという願いが胸に迫る。
そして稲葉浩志が放つ「あなたを抱き締めよう」という一言。
それはささやきではなく、胸の奥で荒ぶっていた想いをすべて解き放つかのように、熱を帯びたシャウトとなって夜空に響き渡っていく。
たとえこの気持ちが相手に届かなくても、どうしても繋ぎとめたい―そんな衝動が、この曲を感情の頂点へと押し上げていく。
『月光』レビューまとめ
「月光」は、相反するものが同じ夜空の下でそっと寄り添う一曲だ。
波のように寄せては返す想い、奪いたいほどに求めてもすれ違ってしまう距離。
触れたいのに届かない。離れてしまうと分かっていても、どうしても繋ぎとめたい。そんな矛盾を抱えたまま、ふたりの心は月の光に照らされ、夜の静寂に溶けていく。
完璧には重なりきれない不完全さ。けれど、その不完全さこそが、美しく、儚く、今も夜の奥で淡く光っている。

【幸せ】×『Baby, you’re my home』
走り続けたその先に、帰る場所がある。
6thアルバム『RUN』のラストを飾る「Baby, you’re my home」は、そんな当たり前でいて、誰もが時に見失いそうになる“home”の存在をそっと思い出させてくれる一曲だ。
素朴なアコースティックギターと手拍子、どこか懐かしいブルースハープの音色。そして稲葉浩志のまっすぐで穏やかな歌声が、夜道のヘッドライトのように心を照らす。
「帰ろう まっすぐ君の胸に」
何度も繰り返されるこのフレーズに導かれて、リスナーはいつの間にか、自分だけの“home”を思い浮かべている。
疾走感あふれるアルバムの締めくくりに、この温かさがあること—それこそが『RUN』という作品の大きな魅力だ。
まっすぐ君の胸に — 帰路を照らす温もり『Baby, you’re my home』
Aメロの始まりから、「Baby, you’re my home」が描く世界が一気に立ち上がる。
窓を流れる景色を ぼんやり見つめて
君のことだけ考える oh
せつない夜に何度も寝返り打ちながら
ぬくもりを求めて家路についたよ uh
忙しなく過ぎていく日常の中、車窓を眺めながら浮かんでくるのは、たった一人の大切な人の面影。
アコースティック・ギターの柔らかな響きに包まれて、胸の奥に残るのは、誰もが心のどこかに抱く帰りたい場所への切ない想いだ。
流れる景色とともに、“君の胸こそがhome”という歌のテーマが、優しく語られている。
Bメロで歌われるのは、君の全部を丸ごと受け止めたいというまっすぐな覚悟だ。
あふれる笑顔も 大粒の涙も
すべてが愛しい それだけさ
他に何もない
「それだけさ」という小さな言葉が、逆にすべてを語っている。
愛しさに理由はいらない。飾りも要らない。ただ“君がいる”。それ以上でも以下でもない、ありのままの姿を抱きしめたい。そんな主人公の気持ちが、優しく胸に響く。
サビでは、“帰ろう”という言葉が、聴く人の心にまっすぐ届いてくる。
帰ろう まっすぐ君の胸に
明かりを見失わないで oh
僕らは これからきっとうまくいくよ
もうすぐたどりつく
Baby, you’re my home
「明かりを見失わないで」という言葉は、目には見えないけれど、たしかに心に灯る優しさの灯火だ。
どれだけ遠回りしても、暗い道に迷い込んでも、その胸に辿り着けさえすれば、すべてが報われる。
「僕らは これからきっとうまくいくよ」根拠なんていらない。この言葉の奥にあるのは、誰かを信じる小さな勇気と、信じてくれる誰かの胸のぬくもりだけだ。
そして最後にもう一度告げる—「Baby, you’re my home」
流れる景色の向こう側に必ずある、小さくて確かな場所。その場所を思い浮かべながら、このサビは静かに、前に進むための背中をそっと押してくれる。
『Baby, you’re my home』レビューまとめ
どこにいても、誰といても、心の奥にだけは残しておきたい場所がある。
「Baby, you’re my home」は、その場所を思い出させてくれる静かな灯りだ。
声にならない寂しさも、言葉にできない願いも、そっと受け止めてくれる。走り疲れた夜の隙間に、この曲が流れるだけで、もう一度だけ信じてみようと思える。
どこまで遠回りしても、戻れる場所がある。それだけで、自分の中のどこかが少しだけやわらかくなる。
もし、帰りたい場所が遠くに感じる夜があるなら、誰かの胸にそっと甘えたくなる瞬間があるなら、そんなときにこそ、「Baby, you’re my home」を聴いてみてほしい。

このアルバムを通して感じたこと
このアルバムを聴くと、思い出す景色がいくつもある。無理だと分かっていても走り続けていた頃の自分、何かに追いつきたくて、でも何に追いつきたいのかも分からなくて、ただ夜の街に繰り出していたあの感覚。
『RUN』には、あの頃の自分が抱えていた焦りや不安がそのまま詰まっているように思う。でも不思議と、聴き終えた後に残るのは苦しさじゃなくて、「あの頃の自分も、ちゃんと意味があったんだな」という小さな肯定だ。
がむしゃらに進むしかなかった日々を思い返すと、もうあんな風にはなれないかもしれないって少し寂しくなるけど、このアルバムがあると、今でもまだどこかに走り続ける力が残っている気がする。
ただのロックでも、ただの思い出の曲でもない。大人になった今の自分にとっても必要な音だと、聴くたびに思い知らされる。
『RUN』は、自分が立ち止まりそうになる瞬間に、そっと背中を押してくれるアルバムだ。だからきっと、これからも何度でも聴き返すんだと思う。
※本記事において引用している歌詞は、すべて松本孝弘/稲葉浩志によるB’zのアルバム『RUN』に収録された楽曲からの一部抜粋です。著作権は各著作権者に帰属しており、当サイトは正当な引用のもとでこれを掲載しています。著作権に配慮して歌詞全文の掲載は行っておりません。