B’z 21st Album Album『NEW LOVE』全曲レビュー|“新しい愛”で、自分の積み重ねを更新してゆく。
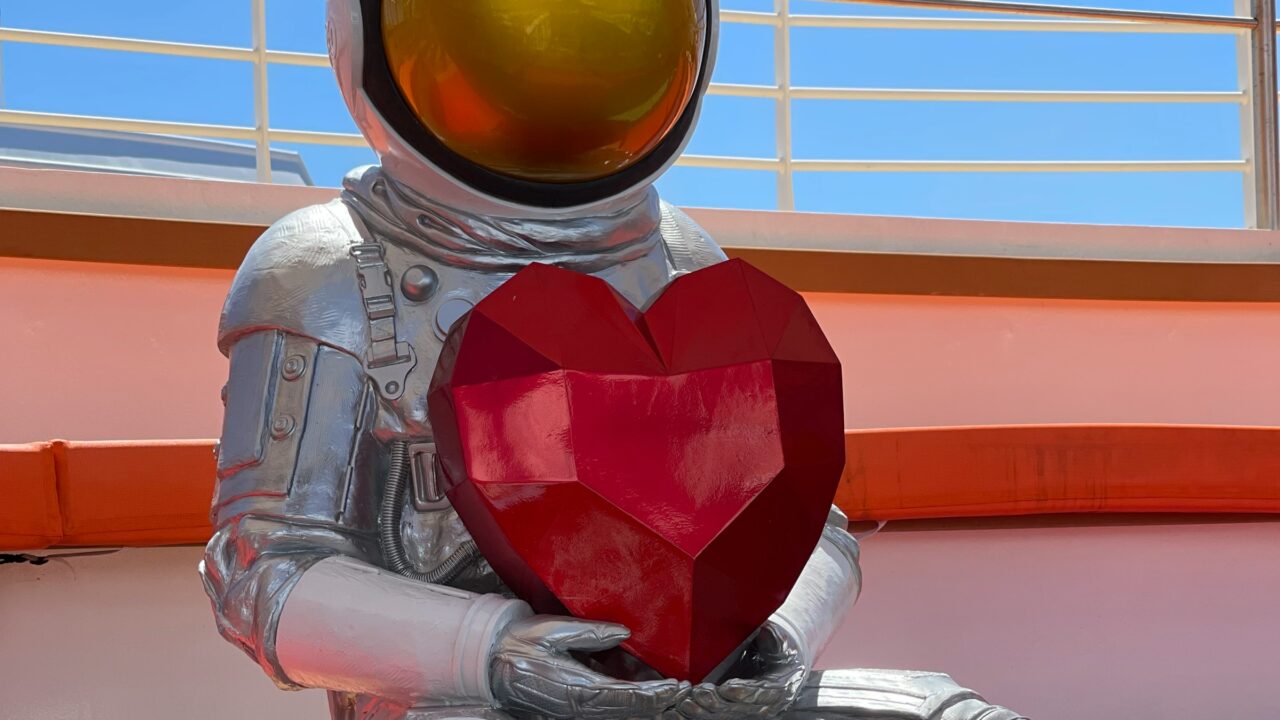
UnsplashのFernando Jorgeが撮影した写真
『NEW LOVE』が伝える、“生きることを愛し直す”というメッセージ。
“新しい愛”というタイトルは、恋の物語ではなく、自分と向き合いながら前へ進む力を示す言葉だ。迷いの中でも、ほんの少し角度を変えて今日を選び直す——そんな温かい再出発の気づきを与えてくれる一枚である。
転んだ経験も、心の傷も、歳月の重みも。そのすべてを音に変えて前へ進む姿に、聴く者はきっと自分の物語を重ねる。いくつになっても「自分を更新し続ける力」を信じさせてくれるサウンドが、ここには鳴り響いている。
変わらないものを手放し、変わりゆく自分を肯定する。挑戦、挫折、再生、そして穏やかな希望。聴き終える頃には、世界が少しだけ“新しい愛”に包まれて見えるだろう。
B’zは、いまも変わらずロックを鳴らしている。けれどそのロックは、もはや若さの象徴ではなく、生きるということそのものになっている。
痛みも、迷いも、愛してきた記憶も——そのすべてを抱えたまま、新しい自分へと踏み出す。
それこそが、B’zがこの時代に鳴らした“NEW LOVE”のかたちだ。
Release:2019.5.29
※本記事では、B’zのアルバム『NEW LOVE』に収録された各楽曲について、歌詞の一部を引用しながら、その表現やメッセージについて考察しています。引用にあたっては、著作権法第32条に基づき、正当な範囲での引用を行っております。
表現される感情
【平然とした】×『マイニューラブ』
アルバム『NEW LOVE』の幕開けを飾る「マイニューラブ」は、派手な爆発ではなく、静かな決意から始まる一歩目だ。
スネアの乾いた響きと、澄んだ輪郭を持つギターリフが、淡々と前へ進むリズムを描く。過剰に盛り上げることなく、それでも確かに空気を変えていくそのサウンドは、眠気の残る朝に差し込む光のように心を照らす。
うまくいかなかった恋の痛みを抱えながら、それでも「Ride on time」とつぶやいて前に進む。“時の流れに乗っていけ”というその言葉には、過去を引きずらずに歩き出す大人の潔さがにじむ。そんな静かな推進力が、この曲全体をやさしく押し出していく。
稲葉浩志の声は、過去を振り切る強さではなく、傷を抱えたまま進む誠実さを帯びて響く。愛しすぎたあの日の記憶をそっと胸に残したまま、「学んで、目線を変えて」歩き出すその姿に、聴く者は自分の再スタートを重ねてしまう。
派手さはないのに、体の奥から確かな熱が湧き上がる。静かに空気を温めながら、アルバム全体を動かし始める——そんな爽快なロックナンバーだ。
『マイニューラブ』過去を引きずらずに歩き出す大人の潔さ
この曲は、「思いの強さが報われるとは限らない」——その現実を朝の光の中で受け入れる場面から始まる。
いくら思いが強かろうと
良い塩梅に愛されない
現実を知った朝のSunlights
骨身に沁みて痛い
Ride on time ここにゃいられない
そこにあるのは、嘆きではなく、事実を見つめ直す冷静さだ。
夜の熱が引いたあとの澄んだ空気のように、痛みは激しさを失い、骨の奥にゆっくりと沁みていく。
やがて、過去に留まらず今この瞬間に乗って進もうとする意志が立ち上がり、痛みを抱えたまま前へ進む大人の潔さが浮かび上がる。
ここで物語は「別れの歌」から「再出発の歌」へと静かに転じていく。この穏やかな変化こそ、「マイニューラブ」の始まりを象徴している。
サビでは、これまで抱えてきた痛みが、前進のエネルギーへと変わる瞬間が描かれている。
新しい恋のようなもの
見つけに行こうよ
愛しすぎちゃったあの人は
もう戻っては来ない
正解は他にある
マイ・ニュー・ラブ
「新しい恋のようなもの」という表現に込められているのは、恋そのものよりも“もう一度、誰かをまっすぐ見つめられる自分”を取り戻したいという想いだろう。
「正解は他にある」という言葉に込められた前向きな含みが、曲全体の光を決定づけている。
“マイ・ニュー・ラブ”は、新しい恋そのものを指すのではなく、新しい視点、そして自分自身への愛情を示す言葉だ。それは、過去を否定するのではなく、経験を抱えたままもう一度歩き出す自分を肯定する歌でもある。
静かな温度を保ちながら、確かな希望が息づき始める——その瞬間に、「マイニューラブ」というタイトルの意味が最も鮮やかに立ち上がる。
『マイニューラブ』レビューまとめ
もう一度、誰かをまっすぐ見つめられる自分を取り戻す——その静かな決意が、痛みを推進力に変える。
過去を抱えたままでも、視点をほんの少し新しくすれば、世界は明るさを取り戻す。それは大きな宣言ではない。カーテンの隙間から差し込む朝の光のように、静かで確かな始まりでいい。

【精力的】×『兵、走る』
静かな立ち上がりを破るように、“Hey-hey-hey-ho”のコールが響いた瞬間、空気が震え、景色が動き出す。
泥の風、汗の煙――匂い立つ言葉が“走る背中”をまぶしく浮かび上がらせ、気づけば自分もその声に突き動かされている。
この曲の核にあるのは、「挑む権利」と「まだ終わりじゃない」という確かな意志。その言葉が力強く胸を叩き、もう一度前へ踏み出す勇気を与えてくれる。
タイトなリズム、鋭く刻むギター、そして熱を帯びたヴォーカルがひとつになって疾走する。全身で加速していくような、純度の高いエネルギーが脈打つロック・ナンバーだ。
歓声が火を灯す――この曲は、いま立つ場所がまだ通過点にすぎないことを示し、胸の奥に眠る「進め」という衝動を力強く呼び覚ましてくれる。
「まだ終わりじゃない」―『兵、走る』が呼び覚ます“進み続ける衝動”
Aメロが描いているのは、誰かの全力が胸を突き動かし、気づけば声があふれ出している――そんな、自分の中のエネルギーが外へ解き放たれる瞬間だ。
泥の風と汗の煙
走るあなたが見える
その姿に希望を託し
僕らは思わず叫んでいた
綺麗ごとではない闘いの現場。泥にまみれ、汗が立ちのぼる、そのリアルな質感がこの曲の根底にある“生々しい挑戦”を象徴している。
誰かの走る姿が、見つめる者の心を震わせ、思わず声を上げさせる。
挑む者と見守る者――その鼓動がひとつに重なる瞬間が、ここに息づいている。
Bメロでは、誰かを応援していたはずの“僕ら”が、その姿を通して、挑戦は特別な誰かのものではなく、自分にも確かに与えられた権利なのだと知らされる。
そして気がつく
皆限界まで挑む権利がある
それは、“選ばれた者”への賛歌ではない。“生きているすべての人”に向けた、挑戦への呼びかけだ。
応援歌から自己宣言へ――視点が反転する瞬間。聴く者を“観る側”から“挑む側”へと引き寄せる、この曲の核心にあるフレーズである。
サビでは、この曲のテーマである“挑戦”が、最も力強く突きつけられる。
ゴールはここじゃない
まだ終わりじゃない(終わりじゃない)
止むことのない歓声
アナタは先の方
ずっと先の方(先の方)
追いつきたいなら今はtry(try!)
「ゴールはここじゃない」「まだ終わりじゃない」――この二つの否定は、絶望ではなく希望のかたちとして響き渡る。
達成の瞬間にも立ち止まることなく、次の挑戦へと意識を向け、“終わらない走り”を肯定していく。
さらに、「止むことのない歓声」というフレーズが印象的だ。それはスタジアムの熱狂であり、同時に心の奥で鳴り続ける声でもある。外からの応援と内側の意志が溶け合い、走り続ける力へと変わっていく。
「アナタは先の方」という距離感には、憧れと悔しさ、そして希望が交錯する。その背中を追いかけるように、稲葉浩志のヴォーカルは熱を帯び、松本孝弘のギターが鋭く燃え上がる。
全身で加速していくようなサウンドが、“try”というひと言を現実の衝動へと変えていく。
『兵、走る』レビューまとめ
ゴールを遠ざけるのではなく、いまの一歩を前へ押し出す――この曲は、そんな純粋なエネルギーに満ちている。息が上がった日ほど、そのサウンドが体のギアをもう一段上げてくれるはずだ。
聴き終えたあとも胸の奥に残るのは、「まだ終わりじゃない」という鼓動。
そのリズムが、あなたを再び走らせてくれる。
…でもその前に、スタバでひと息つこっと!☕️

【集中】×『WOLF』
『WOLF』は、孤独を恐れず、本音で勝負する覚悟を刻みつけるように走り抜ける一曲だ。
歯切れの良いカッティングとタイトなグルーヴ。ファンク寄りの質感がロックの骨格に噛み合い、B’zらしい推進力の中に“風を切る”感覚が宿る。
さらに、ブリッジで余計なメロディを挟まず、ギターソロを前面に据えた構成も秀逸だ。松本孝弘のソロはまるで風そのもののように駆け抜け、歌の熱を途切れさせずに最後のサビへ導いていく。勢い任せではなく、狙いを定めて噛みつくような音運びが、“狼”というタイトルにふさわしい鋭さを刻んでいる。
そのサウンドのすべてが、「覚悟とは、どんな逆風の中でも自分の言葉で吠えること」だと教えてくれる。――偽りを纏うくらいなら、本音だけ吠えて生きていく。
その声は、夜の荒野にまっすぐ響き渡っていく。
風を切り、荒野に吠える。『WOLF』が刻む孤高の覚悟
Aメロは、主人公が迷いを振り切って走り出す瞬間を描いている。
速いクルマが好きなのさ
疑いない性能
痛いくらいに風を切り
すべてを忘れ
速さを求めるのは刺激のためではなく、思考よりも先に感覚を研ぎ澄ませるための手段なのだろう。
「疑いない性能」という言葉には、信頼を外ではなく自分の内側に置こうとする意志が凝縮されている。誰かに保証されることよりも、自分の感覚と判断を信じることで前に進んでいく。
痛いほどのスピードが、過去や迷い、社会のノイズをすべて置き去りにしていく。それは逃避ではない。余計なものを削ぎ落とし、痛みを抱えたまま“今、この瞬間”へ意識を研ぎ澄ませていく。
Bメロは、主人公が外の世界へ踏み出す前に、静かに自分と向き合う場面を描いている。
鏡の前ボタンを留め oh yeah
覚悟をきめてドアをあけよう yeah
鏡の前でボタンを留める仕草は、単なる身支度ではなく、自分の内側と向き合い、覚悟を整えるための儀式のよう。恐れや迷いを押し込みながら、これから向かう現実に立ち向かう姿勢を確認している。
ドアの向こうに待つのは、愛や競争、孤独が渦巻く“荒野”のような世界。たとえ、どんな風が吹こうとも、本音だけで進む覚悟を携えて、現実の中へ踏み出していく。
サビでは、主人公の生き方そのものがまっすぐに宣言される。
俺は荒野 甘えりゃ game over
愛を語るにゃ風が強い
Like a ローラーコースター
止まぬいざこざ
揺れる心抑えつけて
君の目見て本音だけ吠える ah woo
自身を守ってくれるもののない荒野を生き抜くためには、他人や環境に頼らず、自分の力だけで立ち続ける覚悟が必要だ。
「甘えりゃ game over」という言葉には、敗北とは他者に負けることではなく、自分を偽ることだという信念が滲む。現実の風は冷たく、優しさや愛を語るにはあまりに過酷だが、その逆風の中でも誠実であろうとする。
「Like a ローラーコースター」という比喩が示すように、人生は止まることなく浮き沈みを繰り返しながら進んでいく。その不安定さの中でも、自分の弱さも恐れも飲み込み、ただ“君”の目を見つめて本音だけを放つ。
理屈を超えて狼のように声を上げる“ah woo”は、誇示ではなく誠実の叫びだ。どんな環境でも、自分の言葉で生き抜こうとする主人公の覚悟が、ここで鮮やかに鳴り響いている。
そしてその叫びは、同じような逆風の中を歩く人の胸にも、確かに火を灯していく。
『WOLF』レビューまとめ
『WOLF』は、強くあろうとするほどに滲み出る、人間らしい優しさを鳴らしている。
孤独を恐れず、本音で立つことは簡単じゃない。ときに傷つき、誤解され、それでも前へ進まなきゃいけない瞬間がある。そんなとき、この曲は背中を押すんじゃなく、同じ荒野の風を共に受けてくれるように響く。
自分に嘘をつかずに生きたいと願う人の心をまっすぐに受け止めてくれる。そういった生き方によって、ときには人を離れていくこともあるだろう。
この曲は、そんな人のそばで静かに牙を光らせながら、“それでいい”と語りかけてくれる。
大切な人の“目”に、真実の自分を映したい。その願いと覚悟が貫かれた、孤高で誠実なB’zのロックナンバーだ。

【生き生きとした】×『デウス』
雨が上がった瞬間、視界が一気に開ける。『デウス』は、その一瞬の空気感と感覚を爽やかなロックサウンドで描いた一曲だ。
タイトルの「Deus」はラテン語で“神”。しかしここで語られる神は、救いを与える存在ではなく、前を向くための象徴に近い。曇り空のその先に、自分の手で光を見つけようとする意思が滲んでいる。
サウンドは、軽快なロックの中にブルースの息吹がやわらかく溶けている。青く澄んだ空気の中、力強いビートが大地を押し上げ、ギターが風を切るように響く。
重さと軽さ、熱と爽やかさが同居するその音の層が、雨上がりの風景をそっと浮かび上がらせていく。
そしてその音の中で、心は少しずつ晴れていく。曇っていた気持ちに光が差し込むように、胸の奥で新しい鼓動が鳴り始めるはずだ。
青に染まりながら、もう一度走り出す『デウス』
A〜Bメロでは、雨上がりの空が広がり、閉塞した気分から抜け出す瞬間が描かれる。
雨は上がり 雲は散って 青の支配
ジリジリと滲む汗 踊る鼓動
スピード上げていけばもう湾岸線
風に溶けよう
空が青く染まっていく光景は、ただの天気の変化ではなく、心の奥に差し込む光の象徴だ。曇りを払い、視界が開けていくその過程で、心より先に体が前へ動き出していく。
「スピードを上げていけばもう湾岸線」という描写は、郊外や街中を抜けた瞬間に、一気に海沿いの視界が広がる感覚を映し出している。そこには、閉ざされていた世界がふいに開けるような、息づかいが感じられる。
雨が上がり、光が差し、空が青に染まるように——心もまた、静かに晴れていく。
そしてこの曲のサビが伝えるのは、立ち上がる力は誰の中にも眠っているという、普遍的なメッセージだ。
嗚呼、突き抜けようぜ
泣いちゃいられない
この道はどこへと続く
誰でももう一度走り出せる
愛はまだギラギラしてるかい
神様、Oh yes I’m ready
「嗚呼、突き抜けようぜ」――この冒頭の呼びかけは、自分自身へのエールでもあり、聴く人に“もう迷うな”と語りかけるような強さを持っている。感傷を否定するのではなく、その感情を燃料に変え、心の奥にある迷い・停滞・不安を一気に突き抜けていく。
“行き先”なんて分からなくていい。
ここで歌われる“愛”とは、夢でも、音楽でも、人でも、自分でもいい。まだ心の奥で消えずに灯る何かがあるなら、きっとその光が、自分だけの道を照らしてくれる。
“ギラギラ”という言葉には、熱と軽やかさが同時に息づいている。それは、この曲全体に流れる爽やかさの中の強さを象徴するフレーズだ。晴れ渡る空のように、まっすぐで、迷いのないエネルギーがそこにある。
「神様、Oh yes I’m ready」――それは、誰かに救いを求める言葉ではなく、自分の内にある光を信じて踏み出す決意だ。
外にいる神ではなく、自分の中で再び動き出す力そのものが、「デウス」というタイトルに込められているのだろう。
『デウス』レビューまとめ
雨上がりの空のように、心もまた何度でも晴れ渡る。
『デウス』は、迷いの跡さえ光に変えて、もう一度走り出す勇気を思い出させてくれる、清々しいロックナンバーだ。
疲れて立ち止まった心に、そっと風を吹き込むような優しさと、前へ進ませる力強さがある。聴くたびに、心の景色が少しずつ新しく塗り替えてくれるはずだ。

【幸せ】×『マジェスティック』
『マジェスティック』は、日常の呼吸のように穏やかで、心の奥をそっと温めてくれるバラードだ。紅茶の湯気やささやかな会話——そんな何気ない時間に宿る温もりを、丁寧にすくい上げた一曲である。
タイトルの“Majestic”とは、「堂々たる」「荘厳な」「気高い」という意味を持つ。山や大聖堂のような壮大なものに使われるこの言葉を、あえて“君の声”に冠するところに、この曲の核心がある。
日常を生きる大切な人の声こそが、気高くて尊い。タイトルには、そんな存在への確かな敬意が込められている。
聴き終えたあと、きっとあなたは誰かに優しい一言をかけたくなるだろう。その一言が、明日を変えるのかもしれない。
“君の声に王冠を” 日常を祝福へ変える『マジェスティック』
A〜Bメロでは、紅茶を飲みながら他愛のない話を交わすという、ごく日常的な情景が描かれている。
ちょっと聞かせておくれよ
きみの話 紅茶を飲んで
面倒くさがらないでよ
今日会った人 笑っちまった事
ため息ふうっと漏れる
そんな場面ひとつさえも愛しい
特別な出来事は何ひとつないのに、誰かと他愛のない話を交わすことで、心の奥がふっと温まっていく。相手を急かさず、ため息さえも受け止めるように寄り添う。その穏やかな眼差しの中で、何気ない声や仕草が愛しく輝き出す。
日常の片隅に潜む尊さをそっとすくい上げ、人と人が向き合うときにだけ生まれる“ぬくもりの奇跡”を描き出している。
サビでは、楽曲全体のテーマである“日常の中の尊さ”が、いっそう大きなスケールで広がっていく。
晴れても降っても
君の声はマジェスティック
繰り返す日のあちこちに潜む奇跡
振ってごらんよ
折れない魔法のスティック
シンフォニーのように
言葉は震え響き出す
天気の移ろいは、人生の揺らぎそのものを映している。晴れの日も、雨の日も、どんな瞬間にも意味があり、誰かの声がその日をそっと輝かせる。
たとえ言葉にならなくても、その声があるだけで、世界は少し優しく変わっていく。
「魔法のスティック」は、想いを伝えるための小さな勇気を象徴している。完璧な言葉じゃなくていい。その人らしい声で誰かに想いを届けたとき、胸の奥に眠っていた気持ちが音楽のように震え出し、世界が少し温かくなる。
その瞬間こそが、この曲が歌う“奇跡”なのだ。
『マジェスティック』レビューまとめ
今日、湯気の立つカップを前に、ひと呼吸だけ深く吸ってみてほしい。完璧でなくていい。言葉をひとつ選び、そばにいる人に手渡してみる。
それだけで、いつもの部屋の色が少しやわらぐことに気づくはずだ。この歌は、壮大さを遠くに探さず、いま目の前の声にこそ、確かな価値があると教えてくれる。
“マジェスティック”は、そんな日常の声や言葉を、そっと静かな輝きへと変えてくれるバラードだ。

【触発された】×『MR. ARMOUR』
『MR. ARMOUR』が伝えるのは、“生身で向き合う勇気”というシンプルで力強いメッセージだ。
タイトルの“Armour(鎧)”は、素直な気持ちを覆い隠す心の壁のようなもの。主人公は、その壁の向こうで意地を張る相手に向かい、「もう隠れなくていい、心でぶつかってほしい」とまっすぐに呼びかける。
サウンドの軸を貫くのは、松本孝弘のファンキーで切れ味鋭いギターリフ。一音ごとに火花が散るような勢いで、リズムを前へ押し出していく。そして、鋭さと温かさを併せ持つ稲葉浩志のボーカルが、その躍動を血の通った感情へと変えていく。
攻めと優しさが共存する、中毒性の高いロックナンバー。聴くたびに、自分の小さな世界を抜け出し、もう一度“生身で確かめ合う”感覚を取り戻させてくれる。
理屈よりも実感を、批評よりも関係を。鎧を脱ぎ捨てたその先に、惚れ直すほどの近さが待っている。曲が終わる頃には、きっと——自分の距離感が少しだけ新しくなっていることに気づくだろう。
惚れ直すほどの近さへ—『MR. ARMOUR』が描く、心の距離
A〜Bメロでは、稲葉浩志らしい鋭さとユーモアが交錯する。
つべこべ言うのは あなたの自由
それで今日も気晴らしできるの
私をいじって存在示すなら
もうちょいスタミナみせて
Hey, Mr.Armour ちっちゃい世界に
いつまで 住んでるつもり?
素直になれない不器用さを抱えたまま、軽口や皮肉で自分を守ろうとする相手。そんな姿に彼女は、少し笑いながらも「もうごまかさないで、本音を見せて」と挑発するようなまなざしを向ける。
その視線には、責め立てる響きよりもむしろ、“本当のあなたに会いたい”という優しさと願いがにじむ。
閉ざされた心と、そこに触れようとする温もり。そのせめぎ合いが、このパートに生々しい息づかいを宿している。
サビでは、これまで抑えていた感情が一気に解き放たれる。
ダサい鎧を脱ぎ捨てて
生身でぶつかってよ
言い訳だらけの毎日を
変えてみればいいじゃない
「ダサい鎧を脱ぎ捨てて」——この一行が、この曲の核心を象徴している。
鎧とは、虚勢や見栄、そして傷つくことを恐れる心の防具。その鎧を「ダサい」と言い切ることで、相手を突き放すのではなく、同じ場所に立ち、“素直になろう”と促している。
そこには、責めるでも見下すでもない、等身大の優しさと静かな覚悟がある。
考えすぎないそのシンプルな一言が、張りつめた空気を軽やかにほどき、曲全体に解放の明るさを広げていく。
『MR. ARMOUR』レビューまとめ
『MR. ARMOUR』は、他人にではなく、自分自身に向けて「鎧を脱げ」と語りかける曲でもある。
心を守るために重ねた言い訳をそっと降ろしたとき、きっと誰かとの距離だけでなく、自分の中の世界も少し広がっていく。
その瞬間にこそ、B’zが描く“生身の強さ”が息づいている。

【遊び心のある】×『Da La Da Da』
『Da La Da Da』は、アルバムの中でもリフの骨格と感情の起伏が最も鮮明に立ち上がる楽曲だ。
硬質なリフで幕を開け、稲葉浩志のエネルギーがほとばしるボーカルが、その上を駆け抜ける。そこにストリングスが重力と陰影を添え、ハードロックの直線性とオーケストラの厚みが交錯する。
強靭で、重厚で、それでいて呼吸ができる。——その絶妙なバランスこそ、この曲の核心である。
歌詞の「きらわれちゃったとしても それがなに?」という一行に、この曲のメッセージは凝縮されている。
迎合や好感度に疲れた心が、他者評価の外に出て“自分の芯”を取り戻していく。「人生はでかい」「人生はもっと深い」というフレーズが、短期的な評価のノイズを軽やかに飛び越えていく。
英雄になれなくてもいい。誰かの期待に応えられなくてもいい。そんな開き直りが、実は前へ進む力に変わっていく。この曲は、人生の完璧主義を手放すためのロックであり、B’zがいま鳴らす“等身大の自由”そのものだ。
『Da La Da Da』承認より信念。言葉では届かない場所へ。
A〜Bメロは、人と人との距離感をとても正直に描いている。
人間同士抱き合うこともあれば ooh
いがみ合うこともあるそれが普通 yeah
あっちでもこっちでもいい顔してるのは
そら限界あるでしょ ah
優しさと衝突の両方を抱えた“人間のふつう”をそのまま認めること。理想ではなく、現実の温度から立ち上がるこの導入が、楽曲全体の人間らしさを決定づけている。
重いテーマを軽やかに見せる言葉のリズムが、この曲を“生きている人間の歌”として響かせている。
そこには、完璧ではないからこそにじむ温度と誠実さがあり、そのまま次のサビで鳴る「解放の瞬間」への布石になっている。
サビに込められているのは、他人の評価に縛られた心を一気に解き放つ力。
きらわれちゃったとしても それがなに?ah
そんなことよりもブラザー
人生はでかい
Da la da da da
誰かの目に怯えながら生きる時代を、まっすぐ突き抜けていく。
「そんなことよりもブラザー」という言葉が、その強さをやわらかな温もりに変えていく。敵ではなく、同じ世界を生きる仲間へと視線を向けたとき、そこには確かなつながりが生まれる。
“Da La Da Da”という言葉には、明確な意味がない。けれど、まさにそこに意味がある。
言葉にしないことで、聴く人それぞれが自由に呼吸できる“余白”が生まれている。
そしてその余白こそが、この曲が放つ最大のメッセージ——言葉を離れたところでも、音楽はそっと心に寄り添っている。
『Da La Da Da』レビューまとめ
この曲は、強さと優しさのあいだで鳴っている曲だ。
人にどう見られるかではなく、自分がどう生きたいか。そのシンプルな問いを、まっすぐなリフと声で突きつけてくる。
聴くたびに、心の奥で固まっていたものが少しずつほどけていく。完璧じゃなくていい。うまく言葉にできなくてもいい。この曲がそっと背中を押してくれる。

【悲しい】×『恋鴉』
『恋鴉』は、聴く人の胸に沈んだ“終われない恋”の記憶をそっと呼び覚ます一曲だ。
ミドルテンポのリズムにワウギターが絡み、まるで夕暮れにひとり鳴く鴉の声のように揺らめく。その音のうねりが、胸の奥に沈んだ感情の名残を代弁しているかのようだ。
この曲の主人公は、群れを離れた一羽の鴉のように孤独だ。過ぎ去った恋を笑い飛ばすこともできず、自分でも持て余すほどの未練と正面から向き合っている。
それでも、ただ沈みきるわけではない。太陽や流れ星といった“上を見上げる言葉”を心の中に散らしながら、わずかでも光を探している。そのかすかな上昇の気配が、曲全体にあたたかさを灯している。
松本孝弘のワウギターは、この曲のもうひとりの語り手だ。イントロでは歌をなぞるようにうねり、メロディの中では感情を噛みしめるように鳴いている。
『恋鴉』は、未練を“弱さ”ではなく“生きている証”として描く。ワウが泣き、リズムが運び、心は抱えた痛みのままでも、少しずつ光のほうへにじみだす。
黄昏色のサウンドに、そんな静かな希望を託したロックナンバーだ。
愛の冷たい余韻、鳴くギター——『恋鴉』が描く終われない恋の生々しさ
冒頭は、昼の喧騒と夜の静寂のあいだ——世界が切り替わる夕暮れの瞬間に、過去に取り残された“今”をそっと描き出している。
取り憑かれたようにひとりで
鳴き続けている夕暮れの鴉
群れは皆うちに帰ってく
その空に声は響き渡った
“鳴く”という行為には、言葉を超えた感情の吐露が滲んでいる。
それは、ただ孤独を嘆くのではなく、胸の奥でくすぶり続ける“恋の残りかす”が、まだ言葉にならぬままあふれ出す瞬間だ。
その声は悲しみよりもむしろ、消えきれない想いの証。響き渡った余韻が空を満たし、忘れられない感情がまだ息づいていることを、そっとリスナーの胸に刻んでいく。
サビでは、消えない想いを抱えながらも、光を目指そうとする心の叫びが響いている。
恋の滓がまだ残っている
辛いくらいに溜まっている
いつになったらこの俺は
太陽まで飛んでいけるの
冷たい魔法を解いておくれ
「滓(かす)」という硬い響きが、簡単には拭い去れない現実の重さをまとっている。
愛しき記憶と痛みが心の底で固まり、時間が経っても溶けずに沈んでいる。その鈍いざらつきだけが、今も胸の奥で重たく息をしているのだろう。
どこか遠くへ抜け出したいという、かすかな衝動を抱きながらも、“冷たい魔法”が主人公を引き止めている。
それは、恋の記憶がもたらす麻痺のような感覚だ。忘れたくても、体の奥にこびりついた温度の名残。その思い出からは、もう体温を感じることはできないのに、なぜか冷たさだけが、確かに残っている。
それでも彼は、その冷たさの中でまだ確かに息をしている。そこにこそ、この曲が描く“終われない恋の生々しさ”がある。
凍えた翼を震わせながら、それでも光を目指す——そんな心の儚さと強さと描いている。
『恋鴉』レビューまとめ
『恋鴉』が描くのは、痛みを抱えたままでも前を向こうとする人の姿だ。
冷たくなった記憶の中にも、確かに息をしている感情がある。
それは弱さではなく、今も誰かを想えるという生の証。凍えた翼を震わせながら、それでも空を見上げるその姿に、私たちは自分の中の“まだ終われない気持ち”を見つけるのだろう。

【思いにふける】×『Rain & Dream』
『Rain & Dream』は、夢を語るための歌ではない。どんなに小さな夢でも、今日という一日の中で形にしていく力をくれる曲だ。
かつての忠告や迷いを思い出しながらも、自分のペースで前に進む。誰かに評価されるためではなく、今日できることをひとつ積み重ねる。
その姿勢が、雨の中でもしなやかに歩き続けるような力強さを放つ。大げさな希望ではなく、日常の中にあるささやかな挑戦をそっと肯定してくれる。
『NEW LOVE』の中でも最長の6分20秒を誇るこの楽曲は、ブルースの色気と現代的なスピード感を併せ持つ。エアロスミスのギタリスト、ジョー・ペリーのサウンドが加わり、
楽曲全体に厚みと野性味を与えている。
特筆すべきは、歌が終わったあとの長尺ギターソロだ。演奏そのものが、最後の言葉の続きを語るように展開していく。荒々しいペリーのギターと、松本孝弘の艶やかなトーンが溶け合い、ふたりの対話が“夢を形にしていく”過程を音で描き出す。気づけば、最後の一音まで引き込まれている。
この曲がいちばん響くのは、少し疲れた夜や思うように進まない日にちがいない。派手な前進ではなく、心の中で小さく前を向くための音楽。叩きつける雨のように激しく、夢のように力強い。
『Rain & Dream』は、今日のひとつを大切にし、確実に現実へと変えていくためのロックだ。その6分20秒が、日々を重ねていくことの尊さを、力強く鳴らし続けてくれる。
『Rain & Dream』“日々を積み重ねる力”を与えてくれるブルース・ロック
曲の幕開けは、まるで記憶のページをそっと開くような瞬間から始まる。
お前ときたら
浮かれやすいから
この先せいぜい気をつけろ
わりと真顔で
卒業の日に
言ってくれた 先生 お元気ですか?
あれから何年経ったろう
流され続け今
その忠告の声を思い出すたびに、時間の重みとともに、自分の変化が静かに浮かび上がる。そこにあるのは、若さへの苦笑や懐かしさではなく、「あの頃の自分にどう応えるか」という問いかけだ。
稲葉浩志の声は決して張り上げず、語りかけるように柔らかい。松本孝弘のギターはその旋律をなぞるように寄り添い、過去の記憶をひとつの風景として描き出していく。リズムはゆるやかに重く、止められない時間の流れを肌で感じさせる。
このパートは、過去と現在の自分をつなぐための助走のようなものだ。記憶をたどりながら、いま立っている場所を確かめる。
やがて、この静かなまなざしが“夢を形にしていく”物語を動かし始める。その最初の一歩が、ここに刻まれている。
サビでは、曲全体のテーマがいよいよ姿をあらわす。
生温い rain
濡れる夜が続こうと
怖れはしない
たわいない dream
今日もひとつだけでいい
かなえてみせましょう
そして何か変わる
主人公は、降り続く雨を拒むことなく、むしろその中に身を置く。困難を避けるのではなく、受け入れて前へ進む——その姿勢が、この曲の根幹にある。
ここでの“雨”は、ただの悲しみや試練の象徴ではない。それは、冷たく突き刺すような豪雨でも、激しく打ちつける嵐でもない。生温い雨——肌にまとわりつく不快さとともに、現実の重みをじわりと感じさせる雨だ。
それでも、その中で呼吸を整え、歩幅を小さく保ちながら進んでいく。この“粘りの前進”こそが、サビに込められた強さであり、この曲が伝えようとする生き方そのものだ。
『Rain & Dream』レビューまとめ
『Rain & Dream』は、特別な出来事を歌っているわけではない。けれど、聴くたびに“今日をどう生きるか”を静かに問いかけてくる。
うまくいかない日も、思うように進めない夜も、この曲があればまた立ち戻れる。
焦らず、一歩ずつ。その積み重ねの先に、自分だけの夢がかたちになっていく。

【やる気がある】×『俺よカルマを生きろ』
『俺よカルマを生きろ』は、転んでも立ち上がる人間の“再起”を鳴らすロックナンバーだ。
タイトルにある“カルマ”とは、仏教でいう「業(ごう)」——過去の行いが今や未来に影響を及ぼすという因果のこと。
一般的には「悪い報い」として語られることが多いが、この曲で描かれるカルマはその逆だ。これまでの選択や失敗を、自分の一部として受け入れ、そこからもう一度歩き出す意志を象徴している。
つまり「カルマを生きろ」とは、過去を背負いながらも前へ進む覚悟を持つこと。そしてその覚悟を、B’zは真正面からロックの熱に変えている。
サウンドは、冒頭から最後まで一直線に突き進むエネルギーに満ちている。派手な転調も複雑な構成もない。シンプルなビートと硬質なサウンドだけで曲を押し出す潔さがあり、その“まっすぐさ”こそが、この曲の精神を代弁している。音の粒ひとつひとつに、迷いを振り切るような力強さが宿っている。
人生の敗けや痛みを切り離さず、そのまま引き連れて生きる強さ。カルマとは罰ではなく、歩んできた道の証であり、自分を形づくる軌跡だ。影を抱えてもなお笑い、また一歩を踏み出す。
その瞬間にこそ、この曲の真価が鳴り響く。
逃げずに背負え。『俺よカルマを生きろ』過去を力に変えて
A〜Bメロで描かれるのは、季節の流れに取り残されながら、自分の無力さをそっと噛みしめる瞬間だ。
誰かのいい人奪いきれずに
痛めつけられた夏の終わり
あっという間に新しい男(ひと)と
暮らしてると聞いたのはその冬
全部失くしたと膝をついた時
笑いがこみ上げた
恋の終わりや敗北の中で、ただその現実を受け入れるしかない人間の“呼吸”。失うことさえ笑えるほどに、すべてを突き抜けた強さがそこにある。
絶望の果てに生まれたその解放感が、「カルマを生きろ」というテーマへと静かにつながっていく。そこには、確かに“生きるリズム”が鳴り始めている。
そしてその音は、傷ついた心の奥で小さく灯り、もう一度歩き出すための鼓動へと変わっていく。
サビでは、抑えていた感情が一気に解放される。それは“立ち直る”というより、“もう倒れる場所さえない”という覚悟に近い。
どんなにヨレヨレ傷だらけでも
走り続ける
俺よカルマを生きろ
痺れる自業自得の道
戻るもんか
敗北の先でしか生まれない輝きがある。誰かに赦されることも、励まされることも待たずに、自分の選んだ結果を丸ごと背負って前へ進んでいく。
「戻るもんか」は、過去を否定する言葉ではない。後悔や痛みを抱えたまま、それでも前に進むという自己肯定の宣言だ。この一言に込められた強さが、聴く人それぞれの“カルマ”を照らし出す。
そしてその光は、眩しい理想の輝きではない。傷だらけの現実の中で、それでも消えずに灯り続ける熱だ。泥を踏みしめながらも前へ進む――それが「俺よカルマを生きろ」という生き方なのだろう。
『俺よカルマを生きろ』レビューまとめ
『俺よカルマを生きろ』は、きれいな成功よりも、泥だらけでも前へ進む人の背中を照らすロックだ。
失敗の跡がまだ生々しく残る人、過去を振り返って動けなくなっている人、それでも明日を選びたいと願う人。
完璧じゃなくてもいい。立ち止まってもいい。それでも生きていく意志さえあれば——その瞬間、あなたもきっと“カルマを生きている”。

【希望に満ちた】×『ゴールデンルーキー』
『ゴールデンルーキー』は、過去の自分が置き忘れてきたまっすぐさを、今の自分にもう一度取り戻させてくれる一曲だ。
無邪気さや憧れを否定せず、同時に社会の現実や思いどおりにいかない場面にも目を向ける。そのうえで、一歩を踏み出すことの価値を教えてくれる。現実と希望を同じ画角に収めながら、聴き手の中に眠る“信じる力”を呼び起こすメッセージが通っている。
サウンドは、前へ進むエネルギーと温もりが共存するのが印象的だ。力強いビートでありながら、決して急かすことがない。全体を包む空気は穏やかで、ポジティブな余韻を残す。ギター、ベース、ドラムが一体となって描くグルーヴには、B’zが長年培ってきた王道ロックの芯が息づいている。
新生活の朝や、仕事で落ち込んだ夜、夢の締切に追われる日——どんな瞬間にも、この曲は寄り添ってくれる。現実の冷たさを受け止めながら、それでも希望を見出す強さを思い出させてくれる。
“生きることの肯定”を、いまの時代にまっすぐ届けるロックナンバー。聴くたびに、自分の中の初心がそっと目を覚まし、また前へ進む勇気をくれる。
『ゴールデンルーキー』――現実と希望をつなぐ“まっすぐさ”
この曲のAメロは、『ゴールデンルーキー』というタイトルにふさわしく、若さを肯定するまなざしから始まる。
ゴールデンルーキー
日がな一日遊び呆けるのは
若さゆえの使命イノセントデイズ
責められはしない
勇気がもらえるのなら
漫画の主人公に
憧れるがいい妄想ならフリー
不可能などない
日々を遊びや憧れで埋めてしまう時間も、決して無駄ではない。むしろ、その中にこそ未来へ踏み出すためのエネルギーが眠っている——そんなメッセージが感じられる。
鍵となるのが「イノセントデイズ」という言葉だ。直訳すれば“無垢な日々”“汚れのない時間”だが、ここで描かれているのは、損得や効率よりも純粋な衝動で動ける瞬間。誰に評価されるでもなく、ただ「やってみたい」と思える心のエネルギーのことだろう。
現実を見据えながらも、心の中で何かに憧れることを恥じない——そんな自由な姿勢が、この曲の希望のメッセージを自然に導き出している。
サウンドもそのテーマに寄り添うように軽やかで、現実と理想、冷静さと情熱の両方を抱きしめるようなバランスで鳴り響く。前へ進む力よりも、“今の自分を肯定していい”という温もりだ。
Bメロでは、物語の視点が“今”から未来へと静かに広がっていく。
今想像してみて
明日、明後日、10年後
何が見える
明日、明後日、そして10年後――時間のスパンを少しずつ伸ばしながら、聴き手に自分自身の未来を思い描かせるような構成になっている。
ここで大切なのは、具体的な答えを提示することではなく、想像するという行為そのものだ。Aメロで肯定された無邪気さや憧れが、このパートで初めて「未来を描く力」に変わっていく。
サビでは、短い言葉の中に、稲葉浩志が伝えたかった“生きることの意味”が凝縮されている。
生きてる事自体がHOPE
忘れないでいて
これからはこの世界を
動かすのは君
印象的なのは、希望を外側の出来事や結果ではなく、“生きているという事実そのもの”に見いだしている点だ。夢の実現や成功の瞬間ではなく、呼吸し、悩みながらも前に進む――その過程にこそ価値があると伝えている。
葉浩志の言葉は、今ここに立っている自分をまるごと肯定してくれる。
このサビが導くのは、誰かに励まされる物語ではなく、自分が世界を動かす側に立つ意識だ。それは命令ではなく、信頼に満ちたまなざしから生まれる温かなエール。聴く人の内側に眠る力を、静かに目覚めさせるような優しさがある。
松本孝弘のギターは、その言葉を支えるようにまっすぐな旋律を奏で、サウンド全体が光を帯びて広がっていく。曲が終わるころには、胸の奥に清々しい余韻が残り、心の輪郭が少しだけ明るくなる。
“生きることの肯定”を、これほどシンプルな言葉と音で描いた瞬間はそう多くない。
希望を探すのではなく、生きることそのものが希望――そのメッセージが、まっすぐに心へ響いてくる。
『ゴールデンルーキー』レビューまとめ
背伸びしても届かない日。努力が報われない週。理由のない焦りに追われる季節。——そんなときこそ、この曲を聴いてほしい。
就活で迷う人も、仕事や家庭の中で立ち止まる人も、長く走り続けて少し息切れした人も。「いまの自分を責めずに、もう一度前を向きたい」と願うすべての心に、この歌は寄り添う。
この曲は、力強い号令ではなく、現実を見つめながら“自分の中の力”を思い出させてくれる歌だ。結果よりも、その途中で踏みしめた時間をちゃんと肯定してくれる。だから聴き終えたあとには、静かに火が灯るような温かさが残る。
通勤の朝でも、帰り道の夜でもいい。たった5分で、今日の自分をもう一度立ち上がらせてくれる——そんな一曲だ。

【神経質】×『SICK』
『SICK』は、アルバムの中でもひときわ濃度の高いグルーヴを放つ一曲だ。鳴った瞬間に引きずり込まれるようなリフが、全体を牽引する支配的なリズムとして機能している。
なかでも圧倒的なのは、Mohini Deyのベースだ。リズムを支えるだけでなく、リフと絡み合いながら前へ押し出していく。彼女のプレイには技術の先に“体温”がある。ひとつひとつの音に呼吸のような揺らぎがあり、その躍動が曲の「痛みと快感」の往復を、聴く者の身体にも移してくる。
歌詞では、恋愛における依存と嫌悪が共存する心の揺れが描かれる。「好きなのに離れたい」「離れても忘れられない」――そんな人間の根源的な矛盾が、リズムのうねりと重なっていく。感情が乱れるたびに音が膨張し、また収縮する。ベースの脈動がそのまま心拍のように響き、聴く者は“生理的なリアル”へと呑み込まれていく。
考えが堂々巡りして抜け出せない夜、『SICK』は苦しさを消すのではなく、その痛みを堂々と鳴らしながら、混乱を言葉に変えてくれる。
惹かれるほどに傷つき、離れたくても離れられない。その不安定さを否定せず、むしろ肯定するように――この曲は、心を解放へと導く音楽へと変わっていく。
『SICK』——惹かれるほどに痛い、愛と依存の境界線。
『SICK』の冒頭は、恋の依存が芽生える瞬間のように張りつめている。
そばにいても離れていて
最後に泣かされるのはいつも私
なのにどうしても無しにできない
いったいどうなることが幸せなのか
深い海の底に落ちてゆく思考
近くにいても遠くにいても、結末は変わらない。傷つくと分かっていても、手放せない。
理性では理解しているのに、感情がそれを許さない——そんな“逃れられない関係”の呼吸が、この導入には漂っている。
Mohini Deyのベースが感情の脈を刻み、その低音は心拍の乱れのように耳の奥で脈打つ。抑えたテンポの中でわずかに揺れるその音が、主人公の内側で膨らみ続ける不安と熱を描き出している。
沈黙の奥に潜む熱。『SICK』はここから、ゆっくりと心の底へ沈んでいく。
A〜Bメロで抑えていた感情が、サビで一気に解き放たれる。
好きだから嫌い
ていうか大嫌い
破裂しそうな自律神経
痛みと快感
そしてまた痛み
目眩がするほど悩ましいよ
こんな世界だけが私を生かす
音の層が重なるたびに、理性が少しずつ剥がれ落ち、感情がむき出しのまま飛び出してくる。
このサビの爆発は、単なる高揚ではない。苦しみと快感が同時に膨らみ、もはやどちらがどちらか分からなくなるほどの混乱が支配している。
愛おしさは痛みに変わり、痛みは再び快感へと転じていく。その循環が曲の中で脈を打ち続け、嫌悪や苛立ちさえも、生きている証のように響いてくる。
惹かれるほどに痛い。その矛盾こそが『SICK』という名の意味であり、愛と依存の狭間で息をする私たちのリアルそのものだ。
『SICK』レビューまとめ
『SICK』が刺さるのは、感情の制御をどこかであきらめている人だ。忘れたいのに思い出してしまう、離れたいのに声を探してしまう。そんな矛盾を抱えた心が、この曲の鼓動と共鳴する。
苦しさの中にだけ確かな生がある——。その危うい真実を、壊れかけた感情の歪んだ輪郭で映し出し、聴く者に“まだ生きている”という痛みを突きつけてくる。
そんな痛みの美しさを見せつけるロックナンバーだ。

【やる気がある】×『トワニワカク』
若さは過去の称号ではなく、今日の態度で決まっていく。
『トワニワカク』は、止められない年月に真正面から抗いながら、ただ抗うだけではない“しなやかな意志”を描いている。
それは単なるアンチ・エイジングの賛歌ではなく、「現実を受け入れながらも、自分を更新し続ける」という人生そのものへの姿勢表明だ。
いつまでも若くありたい——その願いを、恥じることは何もない。B’zはそんなあたりまえを、ハードロックの香りと現代的なクリアトーンで描き出していく。
朝、鏡の前で一呼吸置くとき。通勤の車内、街のざわめきの中。もう少し頑張ってみようと思う夜。そんな日常のさりげない瞬間に、この曲は静かに“再起動のスイッチ”を押してくれる。
“誰かを想う”ことで、自分の若さや意志がもう一度立ち上がっていく。
そしてこの歌は、若さとは、時間に抗うことではなく、愛を携えて今日を選び直す勇気そのものなのだと教えてくれる。
『トワニワカク』若さは過去じゃない、意志だ。
A〜Bメロは、B’zが描く“若さの哲学”の出発点だ。
止められない年月が
体をあちこち蝕んで
こればっかはwe can’t stop
冷凍保存するっきゃない
溢れかえるカラフルなニュース
溺れながら泳ぐ現代社会
目を閉じ耳を塞ぎ
どこまで頑張れるの
激流に逆らう魚のように
歯を食いしばる
時間の流れを止めることはできない。身体の変化も、誰にでも訪れる現実だ。
ニュース、SNS、世間の声——。色とりどりの刺激に飲み込まれながらも、それでもなんとか呼吸を保とうとする。
この曲は、そんな状況に悲壮感を置かない。むしろ軽やかに、ユーモアを交えながら「それでも自分を保ちたい」と歌う。それは開き直りではなく、現実を受け入れることで生まれる強さだ。
流れに逆らって進む魚のように、人はどんなに小さくても、自分の意志で泳ぎ続ける。
「生きるとは、抵抗をやめないこと」——その信念が、この曲全体を貫いている。
“永遠に若くありたい”という願いを、単なる理想ではなく、現実の中での決意へと変換していく。
止まらない時間、溺れるような情報、そして抗う自分。そのすべてを抱きしめながら、この曲は、その呼吸と覚悟を、確かな熱で描いている。
サビは、この曲の心臓部だ。そこにあるのは、誰もが心の奥で抱いている「いつまでも自分らしくありたい」という、とても人間的で正直な願い。
永遠に若く永遠に美しくありたい
純粋な願い誰にも恥じることはない
今宵も愛しいキミに会いたい
それは決して、外見の若さや表面的な美しさを求める話ではない。むしろ、生き方そのものをしなやかに、美しく保ちたいという願いに近い。
疲れや不安を抱えながらも、小さな努力を積み重ねて、今日をもう一度立て直していく。その姿勢こそが“若さ”なのだろう。
そして、曲の最後にそっと差し込まれる“誰かを想う気持ち”。それが、この歌全体の温度を決定づけている。
若さを保ちたい理由は、自分を飾るためではなく、大切な誰かにもう一度会いたいから——そんな小さな愛情が、日々を進ませる力になっている。
願いと愛情を等しく抱きしめながら、“永遠に若くありたい”という言葉を理想ではなく決意の言葉へと変えていく。
若さとは時間の問題ではなく、誰かを想いながら生きることができる意志だということを教えてくれる。
『トワニワカク』レビューまとめ
この曲がまっすぐ届くのは、年齢や周囲の視線に心が揺れるとき、情報の洪水に息継ぎを失いかけたとき、そして“誰かのためにもう一歩だけ前へ”と思えた瞬間だ。
鏡の小さな変化にため息をついた人、通勤の雑音で自分のペースを見失いそうな人、言い訳をやめたいと腹の底で思っている人——そのすべてに、必要な分だけの強さと温度を手渡してくれる。
理想を掲げる歌ではない。小さな努力で今日を立て直すあなたの背中を、確かに押す歌だ。

このアルバムを通して感じたこと
歳を重ねるほど、“正解”よりも“納得”を選ぶようになってしまう。
怒らず、嘆かず、でも甘えない。「強くあろう」ではなく、「誠実でいよう」と思わせてくれる楽曲たち。聴くうちに、心の中にあった言い訳が音に溶けて消えていく。
そして“NEW LOVE”という言葉の意味が、聴くほどに腑に落ちてくる。新しい恋ではなく、新しい生き方。自分を嫌いにならないための、小さな選び直しの連続。
「うまくいかない自分」も含めて愛し直す作業を、この13曲はずっと伴走してくれる。その地味で、けれど確かな一歩を、誇らしく思わせてくれる音楽だ。
『NEW LOVE』を聴き終えても、世界は何も変わらない。変わるのは、こちら側の姿勢だけ。ちょっとだけ顔を上げて、ほんの少し歩幅を前へ。
そのわずかな変化を積み重ねる力を、このアルバムは確かに届けてくれた。
※本記事において引用している歌詞は、すべて松本孝弘/稲葉浩志によるB’zのアルバム『NEW LOVE』に収録された楽曲からの一部抜粋です。著作権は各著作権者に帰属しており、当サイトは正当な引用のもとでこれを掲載しています。著作権に配慮して歌詞全文の掲載は行っておりません。






