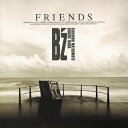B’z 4th Mini Album 「FRIENDS」-切ない冬に心を温めてくれる物語-

UnsplashのIgor Fursovが撮影した写真
“時間を共に過ごすということ”
アルバム全体がひとつの物語となっているコンセプト・アルバム。
松本さんのギターが描きだす繊細で感情豊かな音の世界と、稲葉さんのボーカルで語られる切なく美しいある冬の物語。
アルバム全体を通して聴くことで、一つの映画を観ているような感覚をリスナーに与えてくれる。冬の静かな夜や、何かを振り返りたいときに特にフィットする作品になっている。
心にそっと寄り添う優しさで、その切ない過去をそっと包み込んでくれるだろう。
Release:1992.12.09
※本記事では、B’zのアルバム『FRIENDS』に収録された各楽曲について、歌詞の一部を引用しながら、その表現やメッセージについて考察しています。引用にあたっては、著作権法第32条に基づき、正当な範囲での引用を行っております。
表現される感情
Prologue.Friends
『FRIENDS』の幕開けを飾るインストゥルメンタル曲。
穏やかなテンポで奏でられる、ストリングスによる美しいメロディライン。そして余白のあるアレンジ。
そんなサウンドの特徴が「プロローグ」としての役割を果たし、これから始まる物語へリスナーを心地よく、自然に引き込んでいく。
SCENE1.いつかのメリークリスマス / 思いにふける
B’zの楽曲の中でも屈指の名バラード。
SCENE1のテーマは「回想」
大切な過去の記憶は、時間が経っても色褪せることなく輝きつづける。
美しく切ないメロディと、愛情と儚さが共存する歌詞。1992年の発表以来、今もなお、特別なクリスマスソングとして愛され続けているバラードだ。
オープニングに流れるオルゴールの音は、楽曲に独特の温かさとノスタルジックな雰囲気をもたらしている。オルゴールの澄んだ音色は、クリスマスの夜の静かな景色や、やわらかいイルミネーションの明かりを想起させる。
この幻想的で、少し夢のようなイメージが曲の始まりに置かれることで、リスナーを物語の世界にゆっくりと引き込んでいく。
稲葉さんのボーカルは、やや抑えめで、語りかけるような表現が印象的だ。声の温かみと微かな切なさに加え、サビでは少しずつ感情が高まり、聴き手の心に染み渡るような歌唱が、バラードとしての深みを強めている。
松本さんのアコースティックギターは、メロディックなアルペジオをベースに、サウンド全体の温かみを演出しながらも、エモーショナルなギターソロによって、切なさとその余韻をリスナーに伝えている。
A〜Bメロでは、とても幸せな瞬間が鮮やかに描写される。
“ゆっくりと12月の あかりが灯りはじめ
慌ただしく踊る街を 誰もが好きになる”
僕は走り閉店まぎわ
君の欲しがった椅子を買った
荷物抱え電車のなか
ひとりで幸せだった”
主人公が愛する人のために、何かをすることで感じた幸福感が伝わってくる。
そして「椅子」というアイテムが、日常的でありながらも、親密な愛情の姿を表している。椅子は長く使われる家具であり、長く使うことで愛着が増していく。このプレゼントは単なる「イベント」で終わることなく、日常の一部として残り続ける。
これからも共にいる未来を願い、その時間を共有できる椅子をプレゼントとして選んだのかもしれない。
2番のサビでは、愛の本質に気づき、恋愛から愛情へ変化していく成熟した心情が描かれている。
“いつまでも手をつないで
いられるような気がしていた
何もかもがきらめいて
がむしゃらに夢を追いかけた
君がいなくなることを
はじめて怖いと思った
人を愛するということに
気がついた いつかのメリークリスマス”
永遠に一緒にいられるかのように感じていたほど、無邪気で幸せな関係。日々が美しく、現実以上に輝いて見える恋愛初期の陶酔感や幸せな錯覚。
そんな愛がもたらす喜びと同時に、失うことへの恐怖にも気付いてしまう。
感情が深くなり、「君」の存在が自分にとって、より重要になった瞬間が歌われている。
ブリッジパートでは、言葉にできないほどの感情がこみ上げるシーンが表現されている。
“部屋を染めるろうそくの灯を
見ながら離れることはないと
言った後で急に僕は
何故だかわからず泣いた”
部屋を照らすのは「ろうそくの灯」。この灯りは、儚さや幻想的な美しさを象徴している。
愛が深まるほどに生じる不安と、いつまでも一緒にいたいという強い願い。不安を取り除き、未来のすべてを思い通りにしたいと思っても、それは誰にも叶えられない幻想だ。
「理想の未来」というゆらめく灯は、伸ばした手の少し先でゆっくりと消えていったのだろう。
そしてエンディングでは、過去と現在が交差する瞬間がロマンチックに描かれている。
“立ち止まってる僕のそばを
誰かが足早に
通り過ぎる荷物を抱え
幸せそうな顔で”
たとえ現在が、そのときに望んだ未来でなくとも、そう望んだ記憶はきっと永遠であり、いつまでも人の心を苦しくも、温かくもさせる。
「立ち止まっている僕」がふと目にする現在を生き、前に進んでいる人のクリスマスの情景は、自身の楽しかった時や、愛した人との幸せな瞬間を思い起こさせる。
その幸福がもう手に入らない現実に、心が切なくなりつつも、その情景にどこか心が満たされ、温かくなっていく。
「いつかのメリークリスマス」は、リスナーに「美しい思い出の儚さ」を静かに伝えてくれる。心に温かな共鳴を感じるクリスマスソングだ。
SCENE2. 僕の罪 / もどかしい
SCENE2のテーマは「再会」
タイトルにある「罪」とは、かつて「ふたりの未来」ではなく、最終的に「それぞれの未来」を求め、君を手放してしまったことだろう。
また、一度別れを選びながらも、その決断を覆そうとする自己中心的な自身の感情に対する内省的なニュアンスも含まれている。
再会が新しい始まりになる可能性はあるものの、それが「完全な愛の回復」「夢のような未来」を約束するわけではない。そんな感情や状況に戸惑い、悩む主人公のストーリーが歌われたバラードだ。
過剰に装飾されたサウンドはなく、曲全体がシンプルなアレンジで編成されている。松本さんのギターのカッティング音も、穏やかな空間を作り出しており、物語のドラマ性が自然に心に響くように展開されていく。
稲葉さんのボーカルは、内省的で揺れ動く感情が表現されている。静かなトーンを保ち歌うことで、自分自身への問いかけのような雰囲気を強調しながら、内面の葛藤を伝えている。
Aメロでは、後ろめたさを感じながらも、その衝動に抗えず君に連絡をしてしまう。
“やめた煙草に手を出すように
君に電話をかけている僕は”
主人公の孤独、未練、そして迷いが凝縮されたシーンだ。
Bメロでは、そんな戸惑いを感じながらも、自分の素直な気持ちが溢れ出している。
“居心地いい場所だけを
さがして歩くやつなのか
こころの隙を縫いながら
言葉があふれてくる「会いたい」”
この感情は「甘え」や「逃げ」なのだろうか。そんな風に考える自分自身と、それを否定する自分自身との間で、感情は揺れ動く。
その答えが分からないまま、それでも「会いたい」という言葉が、短くも力強く、切実な感情を表現している。
2番のBメロでは、再会したことへの高揚感で満たされている。
“やりたいことをやるためだと
それぞれの道を選んで
別れたことをもうすっかり
忘れてしまいそうな時が続くよ”
感情が理性を上回る瞬間。「ふたりの未来のため」そんな過去の決断があっという間に崩れてしまうほどの圧倒的な「今」を感じているシーンだ。
サビでは、そんな感情を「罪」として受け入れようとしている。
“I know,I know わかってる
まだまだ 時は十分に過ぎてない
僕だけのフライングだね
(Oh, can’t you see? こぼれる涙はあなたのせい)
Don’t you know? 知ってるはず
完全に 僕の罪なんだ
罪がはじまってくりかえす”
「わかってる」と繰り返すことで、逆に感情を制御できない心情が浮き彫りになっている。
過去の選択と後悔、今の感情と行動との間で揺れ動いている心。また、同じ過ちを繰り返してしまうのではないかという恐怖。
そんな自分の弱さに向き合おうとする姿勢が表現されている。
ブリッジパートでは、どうするべきか迷ったままで「君」を取り戻そうとする、そんな気持ちに違和感を覚えている。
“しっかり君をつかまえろと
誰かが僕に囁くけど
何かが違うと感じるのは
僕がただ臆病なだけのなのか”
再び、傷つけてしまうこと、 傷つくことへの恐れ。本当に、相手の心配や未来まで背負って生きていくことはできるのだろうか。
そんな気持ちのままで、それでも「君」を求めてしまう気持ちの意味を自分自身に問いかける。
ときに「こうするべき」「こう感じるべき」という思い込みが自分の気持ちを曇らせる。それでも、自分の気持ちを直視して、「ありのままの自分」に正面から向き合う勇気が必要だ。たとえそれが、十分な冷却期間を設けていないような完璧なタイミングではなくとも。
それに何の不安もなく、心穏やかに物事を考えられる完璧なタイミングなんて、きっと永遠に来ないのだから。
過去の愛への後悔と罪悪感。再会の喜びと不安の交錯。自分の弱さを見つめる切なさ。
主人公の揺れ動く感情を通じて、そこに自分の経験を重ね合わせることで、自分自身の気持ちについて深く考える。そんなきっかけをリスナーに与えてくれる。
2-2.. Love is …
「SCENE3.恋じゃなくなる日」のメロディを基にした静かで美しいインストゥルメンタル。
この曲は、「僕の罪」から「恋じゃなくなる日」へリスナーの感情の橋渡しを担っている。
『FRIENDS』の物語の中の登場人物たちの時間の経過を、インストゥルメンタルで抽象的に表現することにより、リスナー自身が想像を膨らませる余地を与えてくれている。
そして次の「恋じゃなくなる日」のイントロのインパクトを最大化している。
SCENE3.恋じゃなくなる日 / 落ち着かない
SCENE3のテーマは「葛藤」
「恋が愛に変わる」という一般的なテーマとは少し異なり、抱いてる感情が恋ではなくなった瞬間への戸惑いや、そこに宿る微妙な感情の変化が歌われている。
恋愛感情が終わりに向かっていることに気付きながらも、まだ整理しきれない心。過去の思い出や、情感の全てを含んだ美しさを「君」から感じることで、気持ちは揺れ動き、葛藤する。
「恋が終わり、新しい関係へと進む」というアルバム全体の物語の転換点となる曲だ。
イントロのドラムの力強いアタックと効果的に鳴るシンバルのアクセントが、曲のエネルギーを引き立てている。また、シンセサイザーやギターのエモーショナルなサウンドが、複雑な心情や、その感情の爆発をリスナーに予感させるよう響いている。
1番のAメロでは、再会の高揚感が落ち着き、二人の間には静かな時間が流れている。
“冬の海辺をあてもなく歩いて
二人で貝殻集めて
人もまばらな橋の上のベンチで
いつまでも波音を聞いている”
この歌詞からは、穏やかというには少し寂しさが漂う冷めた空気を感じることができる。
1番のBメロでは、苛立ちすら薄れてしまった現実。かつての感情を取り戻せない切なさや空虚さが描かれている。
“言いたいことが からだの奥で渦巻いているけど
言葉にできないそのことに 今はいらだつこともないよ”
伝えたい思いが、心の中で複雑に絡み合っている状態。
感情を無理に言葉にする必要はない。もちろんそれはそうなのだが、かつては、そのもどかしさにいらだち、 たとえ言葉が的確なものではなくても、君に自分の思いを伝えるエネルギーがあったはずだ。
2番のBメロでは、お互いが相手を傷つけないように、注意深く接している様子が描かれている。
“ほんの少し 離れて歩く 傷つかないように
ほんの少し 口数を減らしている 大事なものなくさないように”
二人の間に漂う微妙な緊張感。かつての自然な親密さは、すでに失われてしまっている。
ブリッジパートでは、壊れると分かっている関係に足を踏み入れる自分自身の矛盾や葛藤が歌われる。
“恋という形のために壊れるものがあること
知っているのに会いたくなるのは 恋だから 愛だから それとも”
それとも、の後にはどのような言葉が続くのだろう。このフレーズでは、この問いに対する明確な答えをあえて歌わず、感情の曖昧さを維持している。
そして最後のサビ。 自分の気持ちを完全に整理できない葛藤や切なさを、力強さと繊細さの両方で伝える稲葉さんのボーカル。「綺麗で」など感情に直結する言葉に、より深い感情を込めていることが伝わってくる。
“僕らが追ってる夢は 本当は同じかもしれないけど
恋はいらないとつぶやく僕は ただのひとりよがりだろう
真夜中 舗道で突然その腕を組んできた 君はとても綺麗で
そのまま僕はじっと空を見上げている 恋じゃなくなった日の空を”
同じ夢を追っているように見えても、二人がその夢に対して持つ価値観や優先順位、そして歩みの速度は異なる。お互いが夢に向かう関係性と恋愛感情を深めていく関係性の両立は、きっと出来ないと主人公は判断したのだろう。
「恋はいらない」というつぶやきには、恋愛感情を断ち切ろうとする意志が感じられる。ただ、それに伴う喪失感を受け入れる覚悟は出来ておらず、どこか自分を納得させるための防衛的なつぶやきのように聞こえる。
そして、突然腕を組んでくるという「君」の無防備で予想外の行動が、その美しさを際立たせる。その美しさと現実の重さからなのか、視線を空に向け、自身の感情を真夜中の空へと放り込んでいく。
アウトロでは、その複雑な感情を引き継ぎ、言葉にできない感情や内面の葛藤、そんな「感情そのもの」を松本さんのギターソロが描き出している。
出口のない優柔不断から抜け出し、この喪失を受け入れてしまえば、これ以上、無駄に関係を先延ばししなくていい。そうとわかっていながら、人は葛藤する。
関係を続けるべきか、断ち切るべきか、という決断の瞬間の切なさ。この物語は、揺れる人間関係を丁寧に描き、どちらを選んでも痛みが伴うその感情を鮮明に伝えてくれる。
SCENE4.SEASONS
アコースティックギターのみで構成されるシンプルなインストゥルメンタル。
アコースティックギターの繊細な表現力で、移りゆく季節の美しさや儚さを表現している。その抽象的な情景が「恋じゃなくなる日」 からの時間経過、物語の背景や季節感をリスナーに自由に想像させてくれる。
そして、物語の緊迫感を保ちながらも、一息つくことができる時間をリスナーに 与えてくれている。
そして次の「どうしても君を失いたくない」をフラットに、ニュートラルな心持ちで聴くことができる。
SCENE5.どうしても君を失いたくない / 穏やか
SCENE5のテーマは「解決」
時間の経過は、主人公に「君」の存在の大切さを再認識させた。ひとりになり、時間を自由に過ごし、自分の思い通りのリズムで夢を追いかけたのだろう。
しかし、それが最善の人生ではなかったことに気がつく。なんでもない時間を共に過ごす。そこには、なにか目的とか目標があったわけじゃない。そんなふうにただゆっくり過ごす時間そのものが、きっと自分にとって大きな救いだったのだろう。
タイトルの「どうしても」という言葉には、主人公が迷いを乗り越え、形を問わず君の存在を心に留め続けるという確固たる意志が感じられる。
ピアノとストリングスが主体となり、そこに松本さんのギターが繊細に絡みあう。適度に抑制されたサウンドの表現が、曲全体に洗練された雰囲気を作り出している。楽曲の持つそんな上品さが、主人公の「大切な存在を失いたくない」という思いを丁寧に描き出している。
稲葉さんの表情を使い分けたボーカル。力強さと切なさが物語のクライマックスに、熱を持って響きわたり、リスナーの心を揺さぶってくれる。
1番のAメロでは、日常という流れの中で、時間が容赦なく進み、季節が巡っていく様子が描かれている。
“狂いなく季節はくりかえし 新しい冬がまた来る
凍りつくような空気に包まれ 今日もめまぐるしく 僕は暮らす”
「狂いなく」というフレーズには、たとえ人々がどんな願いを持っていようと、そんなことを全く気に止めることなくそのサイクルを続ける自然の普遍性が描かれている。
そういった時の流れとは対照的に、主人公の日常には変化がなくなり、新鮮さが失われているように感じる。
2番のBメロでは、愛の変化や別れの意味について考える心情が描かれている。
“恋じゃなくなることは 人を裏切ることになるのか
愛を貫くことの結果は ひとつなのか”
愛の結果が「成功」だけで終わるわけではないという現実。「失敗」は裏切りなのか。それとも、次のステップのために必要な経験だったのか。
その愛に費やした時間は無意味だったのか。それとも「愛した」という事実自体に価値があるのか。
結果は決してひとつではなく、愛のかたちや状況、当事者たちの選択によって多様なパターンが存在するはずだ。
ブリッジパートでは、愛の終わりに直面しても、完全に関係を断ち切るのではなく、その先の未来を見据える姿勢が描かれている。
“二人のことに蓋をして生きるとか 激しく憎みあって忘れるとか
僕らの行き先がどこかに あるはずだ”
理想的な結果にたどり着かなくても、その愛が無意味だったということには決してならない。前向きに未来を見つけようとする力強さが含まれているフレーズだ。
そして最後のサビでは、柔らかい優しさを感じさせならがも、力強い成熟した感情が表現されている。
“どうしても君を失いたくない 胸の奥から叫んでる
戻ることのない流れの中で 心燃やした人だから
いつかいっしょに海に行こう 波の音を聞きたい
あの日の砂の上で踊ろう 過ぎゆく日々に手をふって”
「別れたくない」「いつまでも一緒にいたい」という執着を超えた感情。鮮明な美しい記憶と過去への感謝。もし再び会える未来があったら、というほのかな希望。
海とあの日の砂の上、過去の場所と未来の時間が繋がり合い、交差するシチュエーション。主人公が、そのどちらも大切にしながら新しい一歩を踏み出していく感情の循環と成長が描かれている。
そして曲のエンディングでは、街という変わらない大きな流れに「君」が溶け込んでいく様子が描かれている。
“追憶のかけらは うっすらと白く 世界を包んでいる
君は目覚め出かけてゆく 変わらない街のひとごみの中に”
「かけら」という言葉には、小さくとも鮮明で大切なものというニュアンスが感じられる。また「うっすらと」という表現からは、そんな思い出がどこか懐かしく、優しく、美しいかたちで心に残っていることが示されている。
人生の一場面を切り取ったその瞬間には、切なさだけでなく、希望が微かに漂う。冬の朝の澄んだ空気の向こうには新しい日が昇り、まだ見ぬ未来が広がっていく。
この曲は、愛や別れに関する自分自身の価値観を見つめ直すきっかけになるはずだ。さまざまな感情を味わいながら、そっと心が浄化されていくような感覚を得ることができるだろう。
6. いつかのメリークリスマス (Reprise)
「いつかのメリークリスマス」のメロディを基にしたピアノの独奏によるインストゥルメンタル。
アルバム結末を繊細に彩る美しい曲だ。回想と余韻の強調し、リスナーに内省の時間を提供することで、『FRIENDS』という作品全体の深みを一層引き立てている。
過ぎゆく日々に手を振って
※本記事において引用している歌詞は、すべて松本孝弘/稲葉浩志によるB’zのアルバム『FRIENDS』に収録された楽曲からの一部抜粋です。著作権は各著作権者に帰属しており、当サイトは正当な引用のもとでこれを掲載しています。著作権に配慮して歌詞全文の掲載は行っておりません。