INABA / SALAS No.:BMCV-8060『Maximum Huavo』-レビュー|感情に響くアルバムの魅力とは?-
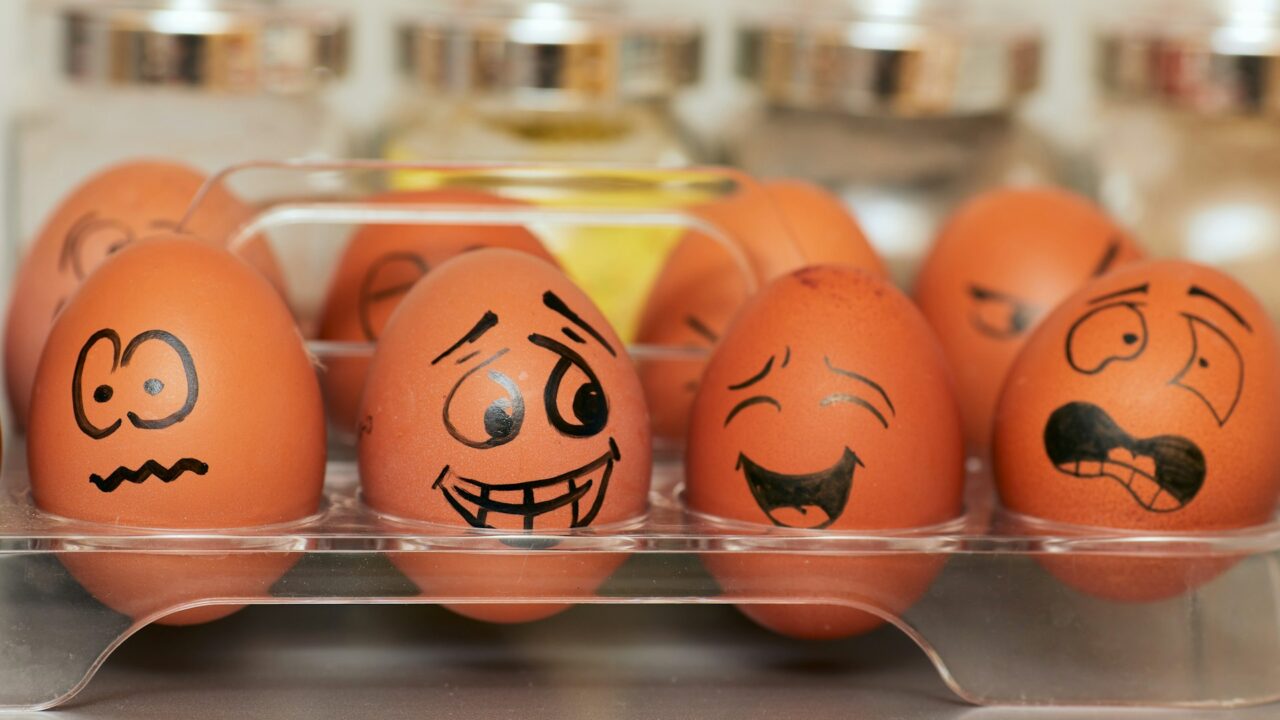
UnsplashのОлег Морозが撮影した写真
“命が目覚める音がある。”
INABA/SALASによる2ndアルバム『Maximum Huavo』は、ジャンルや常識を軽やかに飛び越え、ただただ「生きている」音が詰まった衝動の記録である。
ファンクやロック、バラード、エレクトロといった形式を取りながらも、曲のひとつひとつが理屈ではなく感情で響いてくる。激しさも、繊細さも、喜びも、哀しさも、すべてがむき出しでぶつかってくるようなアルバムだ。
特筆すべきは、アルバムタイトルに込められた意味だろう。「Huavo(ファボ)」は、スペイン語で卵を意味する「Huevo(ウェボ)」をもじった造語である。卵は命のはじまりであり、内に秘めたエネルギーと可能性の象徴。そのスペルを変えることで、ただの卵ではなく、熱くエネルギッシュな存在、殻を破って飛び出すような創造性、そしてジャンルや常識に縛られない自由な精神を感じさせる言葉へと変貌している。
「Maximum(最大限)」と組み合わさることで、このアルバムは、限界まで高められた命と創造の衝動を表現するタイトルとして完成している。
実際、収録されている楽曲すべてに、その意味が全身から溢れ出ている。稲葉浩志のボーカルは鋭くも情感に満ち、Stevie Salasのギターは本能のままにうねり、吠える。ジャンルで語ることすら無意味に感じるほど、音の一音一音が感情の振動そのものとして響いてくる。これらはもはや“聴く”というより“浴びる”音楽だ。
『Maximum Huavo』は、音楽をただ流すものではなく、立ち止まって向き合うべき“生命のかたまり”のような一枚だ。
その一音に、あなた自身の衝動が重なる瞬間が、きっとある。聴くだけじゃない、“生きる音楽”に出会いたいなら、ぜひこのアルバムを手に取ってほしい。
Release : 2020.04.15
※本記事では、INABA/SALASのアルバム『Maximum Huavo』に収録された各楽曲について、歌詞の一部を引用しながら、その表現やメッセージについて考察しています。
引用にあたっては、著作権法第32条に基づき、正当な範囲での引用を行っております。
表現される感情
【危惧する】×「Mujo Parade ~無情のパレード~」
INABA/SALASの「Mujo Parade ~無情のパレード~」は、アルバム『Maximum Huavo』の1曲目にふさわしい、鮮烈なグルーヴで幕を開ける楽曲だ。
ファンキーで軽快なギターリフ、浮遊感をまとったシンセサイザー、そして稲葉浩志の突き抜けるようなハイトーンボイスが交差するこの一曲には、“踊りたくなる音楽”の楽しさと、“現実を突きつける言葉”の鋭さが同居している。
愛に欲望、お金、すべてに踊らされる時代。 それでも“踊れ”と繰り返すこの曲は、ただの風刺ではなく、ユーモアと自己認識に満ちた「共犯者としての賛歌」なのかもしれない。
華やかなパレードの裏で、僕らは何を見落としているのか?
Aメロでは、逃げ出したくなるような現実が表現されている。
Hey oh 素面じゃいられないもう
Hey oh こんな世の中ではもう
現代社会に対する違和感やあきらめに似た疲労感。
「素面じゃいられない」という表現には、「正気では向き合えないほど、今の世の中は息苦しい」という想いが込められているのだろう。
Bメロでは、愛情まで金額で評価される社会を強烈に皮肉っている。
オドリマショオドリマショ 愛情は給料何ヶ月分?
そんな社会の歪みを、あえて“踊る”というポップな動詞で軽快に包み込んで表現している。
ここでの“踊り”は、本来の喜びの動作ではなく、「無情なシステムの中で、知らず知らずのうちに踊らされている私たち自身」を暗示しているのかもしれない。
サビでは、楽曲タイトルの核となるテーマが、最も明確に表現されている。
グロい欲望溢れ彷徨う
無情に続くパレード
意味ない目標掲げ八百長
そいつに一票入れたのはオレ
冒頭の「グロい欲望」という言葉からは、隠しきれない本音やエゴがあふれ出している様子が浮かびあがり、それは彷徨い、出口の見えない「無情に続くパレード」へとつながっていく。
「意味ない目標」とは、本質や意志を伴わず、数字や形式ばかりが先行する空虚なゴールのことだろう。そして八百長のような、最初から結果が決まっている世界の中で、自分も気づかずに勝ち負けを判断しながら、誰かを選んだり支持したりしてしまっている。
そんな風に、つらい社会の中で振り回されながらも、自分もその流れに加わってしまっている—そんな矛盾した気持ちが表現されているのだろう。
見せかけの努力・目標・成功に対する鋭い風刺であると同時に「本当に意味のあることは何か?」というメッセージをリスナーに突きつけている。
ブリッジパートでは、もがく現実、満たされない心—そんな「無情」の根源が表現されている。
高い値札に
心が満たされる
成功者の証求めただもがくもがく
今更後戻りはできないって言い聞かす
消費社会における価値観の歪みを的確に突いている。
高価なモノが満たしてくれる満足感は本物ではなく、あくまで「満たされた気がする 」だけの虚構。
その“見える価値”を追い求めるあまり、どれほど苦しくても、やめられない。「もがく もがく」という言葉の反復は、出口のない焦燥感や、努力という名の自己消耗を象徴している。
ブリッジでは、視点が“内面=個人の葛藤”へと深く沈んでいる。この内面化があるからこそ、楽曲は単なる社会風刺では終わらず「私たち一人ひとりのリアルな感情や選択」まで射程に入った作品となっている。
■ まとめ
華やかなパレードは、時に真実を覆い隠す。明るく踊るその足元に、虚しさや諦め、そして誰かの痛みが転がっているかもしれない。
それでも、この曲は言う。「踊れ」と。無情な社会に飲み込まれていく感覚を笑い飛ばすように、自分もその構造に加担している事実すら引き受けながら、それでも足を止めずに進む意思こそが、今を生きる強さなのだと。
“気づくこと”からすべてが始まる—その覚悟と優しさに満ちた、現代のパレードソングだ。
「誰のための目標なんだろう?」そんなふうに、見えないルールや空気に疲れを感じている人には、この曲の風刺と共感のバランスが刺さるだろう。

【精力的】×「U」
運命的な出会いをテーマに、心がざわめく瞬間や、まだ言葉にならない感情のうねりを、強烈なグルーヴで描き出すロックファンクナンバー。
稲葉浩志のロックの熱量とエッジを保ったエモーショナルな歌声が、ファンク的に「ノる」だけでなく、ロック的に「ぶつかる」—そんな二面性を与え、この曲に圧倒的なドライブ感を与えている。
「U」というシンプルなタイトルが、逆に“あなた(YOU)”の存在の大きさを際立たせている。
感情をストレートに表現しながらも、どこか余白のある言葉選び。出会いという奇跡の瞬間を音で感じさせてくれる一曲だ。
最小にして最大のタイトル
リードイン〜Aメロでは、“千年に一回”という非現実的なスケールの中で、その出会いがどれほど心に深く刺さっているかが表現されている。
千年に一回の出会いってあるの
別れるたびに鮮やか
その残像 マジで who are you?
遠く離れても
僕を乱す人
ありふれた日常の中で起こった、奇跡のような出会い。
離れてもなお、頭から離れない“あなた”の存在は、恋の余韻というよりも混乱と中毒に近い。心が掻き乱され、自分でも気づかないうちに深く惹かれてしまっていることへの戸惑いがにじむ。
別れというのは寂しさを伴うが、ここでは“鮮やか”と表現されている。つまりそれは、離れるたびにその人の存在がより強く、鮮明に刻まれていくということだろう。
感情が整理できないまま、頭の中に居座り続ける“あなた”の残像。“who are you?”という直接的な言葉には、戸惑いと衝撃がにじんでいる。
サビでは、恋に落ちた者の心の奥底がむき出しになっている。
あなたは燃え上がるブラックホール
吸い込まれちゃえば僕はもうゼロ
それでも目をそらせない
どうか消えないで
燃え上がるブラックホール。美しくも危険な存在。その中に飛び込めば自分が“ゼロ”になってしまう—つまり、自己を失うほどの没入と依存。
“それでも目をそらせない”という言葉からは、愛しさと恐れが混じった覚悟のような感情が垣間見える。
そして最後の「どうか消えないで」は、この恋がどれほど切実で、かけがえのないものであるかを静かに物語っている。
■ まとめ
「U」という一文字に込められたのは、言葉にならない感情のざわめき。
抗えない引力に引き寄せられ、自分を見失いそうになる—そんな恋の瞬間を、ロックとファンクの熱量で鮮やかに描いた一曲だ。
言葉では言い表せない感情に、音だけが答えてくれる瞬間がある。
思い出すたびに心を揺らす“あなた”がいる。そんな記憶をそっと照らしてくれるのが、この「U」という一曲なのかもしれない。

【熱狂的】×「KYONETSU ~狂熱の子~」
ギターの弦が切れても、それでも音を出しながら、音楽と一緒に朝を迎えた。誰にも見せられない衝動と、形にならない夢。
「KYONETSU ~狂熱の子~」は、そんなかつての“青春の熱”を呼び覚ますロックファンクだ。
稲葉浩志のヴォーカル、スティーヴィー・サラスの暴れるようなギター。そこに重なる、跳ねるベースラインの躍動感と、叩き込むようなビート。さらにうねるシンセが空間を彩り、抑えきれない衝動と、夜のエネルギーを見事にサウンドへ昇華させている。
そんなサウンドが「忘れていたはずの自分」に再び火を点ける。
「ネムッチャイケナイ」その一言は、かつての自分に背中を押されるようなエネルギーを与えてくれる。
誰かの言葉に救われるのではなく、“あの頃の自分”が今の自分を奮い立たせてくれる。そんな逆転のエネルギーが【KYONETSU ~狂熱の子~】には溢れている。
眠れなかったあの夜の熱は、まだ音の中で生きている
A〜Bメロには、誰にも見せられなかった青春の本音が込められている。理不尽な大人の言葉、孤独な部屋、壊れかけのギター。だけどその中で、確かに「音楽」は生きていた。そんな情景が目の前に浮かぶような、濃密な序章だ
弦が切れようが気になんない
穴あいたギター音鳴んない
永遠の詩に酔いしれて踊ろう alone, alone, alone
誰かの気に障り
音を下げろと怒鳴る
余計なものをかき消す世界 世界世界世界
音が鳴らなくたって構わない。それでも“永遠の詩=音楽”に酔いしれて、ひとりで踊っていたい。
ここにあるのは、技術や完成度ではなく、もっと根源的な「音楽への衝動」だ。
「誰に聴かせるわけでもない、自分だけの音楽」が、青春の夜に静かに燃えていた。そんな姿が浮かんでくる。
“alone”を繰り返す語尾は、孤独をなぞるというより、むしろその孤独の中に「自由」を感じている印象。大人になった今振り返ると、あの時間は確かに“狂熱”だったのかもしれない。
そして、外の世界との摩擦や違和感。まるでどこにも正解がないような、思春期特有の閉塞感が滲んでいる。
自分が大事にしているテンション、自分だけの「熱」。それが“うるさい”“迷惑”と見なされ、押し込められていく。
特に「余計なものをかき消す世界」という言葉には、周囲に合わせることが正解とされる社会への鋭い抵抗が込められているように感じられる。“自分にしかない部分”を、周囲に合わせて抑えこみ、「目立つな」「黙ってろ」と言われる日々。
抑え込まれた自分の“熱”を、音として、リズムとして、叫びとして解放していく姿が浮かび上がる。
サビでは、そんな「今しかない」─心の火を信じるメッセージが伝えられている。
火は消えちゃいない
今ここしかない
全ての始まり
もしかしたらゴール yeah
その気になれよ
ネムッチャイケナイ
かつて心の奥に宿っていた“火”は、消えてなどいない。それは大人になっても、日々に追われても、ずっと胸の中にくすぶり続けている熱だ。
「今ここしかない」という一言には、青春特有の刹那的な美しさと、何かを始めるための強烈な一歩目の衝動が詰まっている。
そして「全ての始まり/もしかしたらゴール」という言葉は、“始まり”と“終わり”が同居しているような、人生の一瞬の尊さを感じさせる。
走り出せば、そこがスタートであり、ゴールでもあるかもしれない。
■ まとめ
「KYONETSU ~狂熱の子~」は、ただ踊れるだけのファンクロックではない。忘れかけていた衝動や、胸の奥でくすぶり続けていた“熱”を思い出させてくれる一曲だ。
それは、かつて音楽に救われた夜を思い出したいときや、あの頃の自分にもう一度会いたくなったときに、そっと背中を押してくれる存在でもある。
再生ボタンを押すたびに、自分の中の“狂熱の子”が目を覚ます。そしてきっと気づくだろう。─あの夜の火は、まだ消えちゃいない。

【落胆した】×「Violent Jungle」
些細なことでイラつく。誰かの声に苛立ち、無関係な誰かに怒りをぶつけたくなる。そんな小さな感情の揺らぎが、いつの間にか“暴力”に変わっていく。
INABA/SALASの「Violent Jungle」は、日常に潜む衝動と、それを正当化しようとする社会の姿を、ファンキーなグルーヴで炙り出す一曲だ。
耳馴染みの良いリズムの裏に隠された、リアルな怒りと葛藤の物語。このレビューでは、その歌詞が映し出す社会風景と、音楽がもたらすカタルシスの力に迫っていく。
切り捨ててでも、生き残る世界で。
Aメロが描く、“すぐ隣にある暴力”。
「騒ぐ子供にちょっと注意したら」──この一文から始まる物語は、特別な事件ではなく、どこにでもあるご近所の風景だ。けれど、その次の瞬間にはもう、「短気な隣人は急に怒鳴り散らし」「拳を振り上げ」ている。
ほんの小さな苛立ちが、瞬時に暴力性を帯びて爆発する。このAメロには、現代社会の恐ろしい速さと近さがリアルに映し出されている。
騒ぐ子供にちょっと注意したら
短気な隣人は急に怒鳴り散らし
奥さんが諌めても拳を振り上げ
唾を飛ばして呪いの言葉を浴びせる
「唾を飛ばして呪いの言葉を浴びせる」というフレーズには、理性を失った人間の剥き出しの本性が見え隠れしていて、耳に残るというより、胸に刺さる。
注目したいのは、この場面に極端な悪役がいないことだ。“短気な隣人”とされてはいるが、きっかけは子供の騒音であり、注意した側にもある種の「正しさ」がある。
つまりこの曲が描いているのは、「誰かの正義が、誰かの暴力に変わる瞬間」だ。
このAメロは、現代に生きる私たちが見て見ぬふりをしている“街の本音”を、鋭く切り取った一節だといえる。
Bメロでは「誰もが感じている本音」が表現されている。
もういいから 煽らないでよ
もういいから落ち着いてよ
何もできない。ただただ「やめて」と願うしかない。そんな無力さと諦めのにじむ言葉だ。
「もういいから」という言い回しには、疲れきった感情や、言葉が届かない世界への諦めすら感じられる。稲葉浩志がこのフレーズを感情を抑えた口調で歌うことで、大げさに叫ばない静かな悲鳴のような効果を生んでいるのが印象的だ。
Bメロでは“社会に巻き込まれる誰か”が、私たち自身の目線にぐっと引き寄せられる。ここで楽曲は、「加害者」と「被害者」の視点を交錯させながら、誰もが“ジャングルの住人”であることを浮き彫りにしていく。
このBメロは短いが、その分強烈な共感を残す。
“誰かを責める曲”ではなく、“誰しもが共鳴してしまう曲”として、「Violent Jungle」の本質がにじみ始めるセクションだ。
そして、サビで叫ばれるのは、私たちの“正しさ”の行き先だ。
電光石火で炸裂しちゃう正義感
理解できないてわけじゃないけどちょいトゥーマッチ
弱肉強食の世界ゆえにしょうがない?
でもその先はバイオレント
Wow-oh-oh, we are living in the jungle
Wow-oh-oh, we are living in the jungle
自分の中にある“これは正しいはずだ”という衝動が制御できなくなる瞬間。他人のその怒りを否定しきれない。
“誰か”ではなく“自分”の中にある暴力性すらも対象にして、「正しさ」も「暴力」も、もしかしたら背中合わせなのかもしれない─そんなヒリつくような自覚を、この曲のサビは音に乗せて突きつけてくる。
「しょうがない」で終わらせてしまう瞬間に、どれほどの暴力が正当化されてきたのか。最終行の「でもその先はバイオレント」は、もはや結論ではなく警告に近い。そんな冷徹な真実を、明るくファンキーなサウンドに乗せて伝えるところにこの曲の皮肉がある。
“we are living in the jungle”というフレーズは、あまりにもキャッチーだ。手拍子をしたくなるし、ライブで観客と一緒に叫びたくもなる。だがその言葉が意味するのは、この社会がジャングルのように混沌とし、力や感情でしか物事が動かなくなっている現実だ。
サビまでは、怒りや暴力に対して一定の距離感があった「Violent Jungle」。
しかしこのブリッジでは、聴き手を突き放すようなむき出しのサバイバル意識が顔を出す。
自分の領域守るためさ
多少の理不尽ならねじ伏せよう
泣いてもらおう 切り捨てよう 生き残ろう yeah
「自分の領域守るためさ」─この一言には、人間関係でも社会でも、何かを守るには戦わなければならないという、現代人の本能的な防衛意識が集約されている。
相手が間違っているかどうかではなく、“自分が傷つかないこと”を優先する価値観。正義でも共感でもなく、ただ“勝つこと”“優位に立つこと”が求められる世界。
それが今、私たちの周りに広がっている「ジャングル」なのかもしれない。
まとめ
きっと誰もが、自分の正しさを信じながら、誰かを傷つけてしまう。きっと誰もが、守りたいもののために、理不尽を飲み込んで生きている。
「Violent Jungle」が描くのは、特別な誰かの話ではない。都市の喧騒の中、ふと顔を出す、自分自身の影だ。
拳を振り上げる代わりに、音に身を委ね、怒りを叫ぶ代わりに、リズムと一緒に心を解き放っていく。
このジャングルで、どう生き延びるか。その答えを探しながら。

【希望に満ちた】×「Boku No Yume Wa」
ミディアム・テンポの軽やかなグルーヴに乗せて、ふとした幸福を描き出すの「Boku No Yume Wa」。
煌めくシンセサウンドと、稲葉浩志の透明感あふれる歌声が織りなすこの楽曲は、ただのラブソングではない。汗を拭う間もなく駆け抜ける日々のなかで、かけがえのない存在に気づく─そんな小さな奇跡を、そっと手渡してくれる一曲だ。
この記事では、「Boku No Yume Wa」が映し出す心の風景を丁寧にひもときながら、聴き手の感情に寄り添う魅力を掘り下げていく。
Boku No Yume Waとは?─心に灯る、ささやかな奇跡
Aメロの冒頭に響くフレーズでは、夢中で走り続ける日々の輝きと、その裏にある純粋な情熱が鮮やかに映し出されている。
汗も拭わずに時間も忘れて
駆け上がってゆく
愛しい人生いずれ完成
星屑を追って
輝きを増す日々
それよりも眩しいものがある
“愛しい人生いずれ完成”―そんな希望に満ちた言葉は、未来に向かうエネルギーを静かに、しかし力強く伝えてくる。星屑を追いかけるように、一日一日が輝きを増していく。けれど、この曲はそこで終わらない。
ただ前に進むだけでは気づけなかった“かけがえのない存在”を予感させる、優しくも切実な序章となっている。
サビでは、走り続けた先でふと立ち止まり、心に広がる一つの確信が表現されている。
Wait 気付いてしまったんだよ
ああ 僕の夢は君
Hey ずっと追いかけて
届きそうで届かぬ人
走り続けた日々の先にあったのは、遠い夢じゃなく”君”だったのだろう。
“僕の夢は君”。シンプルだけれど、この短いフレーズが持つ重みは計り知れない。もどかしくて、でも、ただそれだけで満たされるような存在。
稲葉浩志の声が、透き通るシンセの海に溶けながら、そっと胸に触れる。焦がれるような想いも、静かな幸福も、すべてを抱きしめる、そんな感情が表現されている。
ブリッジでは、戻れない時間の中で、それでも手を伸ばす。過去を悔い、未来を信じたいと願う、いちばん人間らしい瞬間をそっと描き出している。
思えばずっとそばにいた
なのに見過ごしていた
今からでもまだ
遅くないと言っておくれ
胸を締めつけるような後悔。遠くばかりを見ていた過去。気づくには、あまりにも時間がかかりすぎたかもしれない。
それでも、ただ願うのではなく、すべてを受け止めて、それでも前に進みたいという切実な思い。そんな人間らしい弱さと強さの間に揺れる瞬間が、そこにある。
まとめ
本当に大切なものは、いつだってすぐそばにある。
でも、気づくには時間がかかる。傷つきながら、迷いながら、それでも歩き続けた先で─ようやく見つけるものがある。
「Boku No Yume Wa」は、そんなかけがえのない瞬間を、そっとすくい上げる歌だ。派手な演出はいらない。ただ、心の奥にある温かいものにそっと触れてくれる一曲だ。
忙しさに追われ、夢中で走り続けている人。誰かを大切に思いながらも、その気持ちを言葉にできずにいる人。そんなあなたにこそ、この曲はやさしく寄り添ってくれるはずだ。

【ぞくぞくする】×「Demolition Girl」
「デモリション(demolition)」とは、“解体”や“破壊”を意味する言葉。
そして『Demolition Girl』は、その名を冠した「彼女」が、感情のマグマを燃やしながら突き進んでいく―そんな物語を音と歌詞の両面から描き出す、攻撃的でグルーヴィーなハイテンポ・ロックナンバー。
イントロから鳴り響く重厚感のあるベースのうねり、シンセとギターがぶつかり合うサウンドの疾走感が、リスナーを一気に曲の世界観へと引き込んでいく。
破壊と優しさが共存するとき、愛は鋭く響く
A〜Bメロは、サビというエンジンを駆動させるための強烈なガソリンだ。
Hey 愛情が噴火してあふれてら
Ah 七色にギラついたマグマ
忖度なんか無いよ情け容赦ないよ ah
抑えきれない愛のエネルギーが、まるで火山のように地中から吹き上がる。怒り、喜び、悲しみ、憧れ―あらゆる感情が混ざり合い、ギラつく光となって燃え上がっている。
そして、他人にどう思われるかなんて気にしない、手加減なんて一切しないという強い自己主張と覚悟。文脈の中で意味を捉えるなら、優しいふりをするくらいなら、不器用でも本音をぶつけるといった感じだろうか。
そんな激しくも純粋な姿勢が表現されている。
そしてサビで、楽曲のエンジンが最大出力で回り出す。火が点いた感情は一気に加速し、外の世界へと放たれていく。
デモリションガール you never stop
人生は一回きり pop, pop,pop
この世界を起こしてよ
目よ回れ
誰よりも愛を知るあなたにゃワケない
無関心、諦め、思考停止のまま漂う世界を「叩き起こしてくれ」と希望を託す。起こしてよという言葉には「目覚めさせる」「揺さぶる」「変化を引き起こす」という様々な意味が込められているのだろう。
「目よ回れ」この異質なフレーズは、常識がひっくり返るような混乱、目が回るようなスピードとインパクトといったイメージを感じさせる。
そして「誰よりも愛を知るあなたにゃワケない」この一節で、破壊と愛が結びつく。
愛があるからこそ、壊すことを選ぶ。その矛盾が、彼女の切実さと美しさを浮かび上がらせている。
軽快なリズムと鋭い言葉のコントラストが、まさに『Demolition Girl』という曲そのものの二面性―ポップとヘビー、愛と破壊、優しさと激しさを鮮やかに表現している。
ブリッジでは、それまでのロックグルーヴから一転して、語り口調で主人公の本質に深く迫る場面となっている。
何があったか知らないが
失望と希望の両方が
その目の奥に湛えられている(hey!)
きみの目指すゴールは
なんだか危ない匂いだ
人生に楽を望むことほど
バカなことはないという
その渋くて苦い真実を真っ向から受け入れる
辻褄が合っていないようであっている
掴みどころがなくてそれでいてシンプル (hey!)
ようするにまぁあれだきみは最高な不条理の塊だ
『Demolition Girl』というエネルギッシュな楽曲の中で、唯一“立ち止まって語る”時間。
現代社会では、分かりやすさ、一貫性、共感できるストーリーが求められがちだ。でも実際の人間は、そんなに単純ではない。矛盾も迷いも怒りも抱えて生きている。
この語りは、それを「それでもいい」と肯定してくれる。
ここに宿る“不条理の美しさ”。「説明なんかつかなくても、きみは最高だ」というメッセージは、リスナー自身の不器用な感情や過去にそっと寄り添ってくれている。
完璧じゃなくてもいい。正しくなくてもいい。複雑で、矛盾して、掴みどころがなくても、そこには確かな“美しさ”がある。
この曲は、デモリションガールの物語であると同時に、それを聴く私たちの物語でもある。
不器用で、矛盾だらけで、でもまっすぐに生きようとしている人すべてに向けて、「そのまま突き進んでいいよ」と語りかけてくれるこのパートは、感情を爆発させるだけでなく、包み込むような愛のかたちを提示している。
まとめ
『Demolition Girl』は、激しさや鋭さだけでなく、その奥にある優しさや不器用な愛のかたちまでを描ききった楽曲だ。
壊すことも、迷うことも、矛盾することも、全部ひっくるめて―それでも進もうとする彼女の姿に、私たちはどこかで自分を重ねる。
リズムに乗ってもいい。歌詞を噛み締めてもいい。ただスピーカーを震わせて爆音で鳴らしてもいい。
この曲の強さは、どんな聴き方をしても、感情の核にちゃんと届いてくれることだ。
もしあなたの中に「うまく言葉にできない想い」があるのなら、きっとこの一曲が、あなたの感情の代弁者になってくれるだろう。
“壊すことでしか愛せない”その姿が、こんなにも美しく響く。『Demolition Girl』は、心の奥を揺らしながら体をも突き動かすダンサンブルなロックソングだ。

【生き生きとした】×「IRODORI」
日々の暮らしに潜む不安や、出口の見えない現実。それでも、どこかに“自分らしい色”を見つけようとする。
「IRODORI」は、そんな揺れる心にそっと寄り添い、静かな勇気を与えてくれる。
稲葉浩志の真っ直ぐな歌声と、スティーヴィー・サラスのファンク×ロック×ポップが融合したグルーヴ。耳を通して心に届くその音楽は、困難な時代を生きるすべての人にとっての“彩”になるはずだ。
どんな色に染まっても、自分らしく生きるための歌
A〜Bメロでは、日常の中にある小さな挫折や行き詰まりが、淡々とした口調で描かれる。自分の存在がうまく社会や他者に接続できていないという孤独感や閉塞感をストレートに言葉にしている。
先週受けた面接の
返情は以前として来ず
夜更のバイト先の厨房冴えぬ風貌
早朝路上毎度すれ違うあなたに
残念ですが思いは届かぬ
ここで描かれるのは、まさに“色のない”日々。「彩り」どころか、灰色のような日常。しかし、この無彩な世界こそが、後に“彩りを取り戻す”物語の起点となっていく。
このA〜Bメロがあるからこそ、後半で歌われる「絵になるように生きてみる」「何色に染まっても輝く」が、より強く胸に響く構成になっている。
サビでは、自分を否定せずに受け入れようとする決意が込められている。
迷って遠廻りしても
泣きべそかいても
絵になるように生きてみる
ここで言う「絵になる」とは、誰かにとって美しく見える、というよりも、自分自身の人生を“彩りのあるもの”として描いてみようという意志表明だ。
迷いながらでも、涙を流しながらでも、自分なりの色で前に進む。完璧じゃなくても、それでも「今ここに生きている自分」を肯定してみる。
そうしたメッセージが、短くも力強いこのサビに凝縮されている。
ブリッジパートは、曲全体の流れの中で感情の折り返し地点を担っている。
それまでに描かれてきたのは、「報われない日常」「自由の喪失」「自分らしさを貫く苦しさ」といった、現実の厳しさ。
ここで初めて、それらを“彩(いろどり)”として肯定的に捉えようとする視点が登場する。
ああどんな辛い試練もこの人生の彩
そう思えばちょっとは楽になれるものでしょうか
「彩」という言葉は、この楽曲のタイトルであり、象徴だ。
ここでの「彩」は、幸せや成功だけでなく、“辛い経験そのもの”も含めて人生を形づくる色として捉えられている。
稲葉浩志の歌声は、一方的に励ますのではなく、「そう思えるかもしれないね」とそっと寄り添うような優しい距離感で、リスナーの心に届いてくる。
まとめ
INABA/SALASの「IRODORI」は、迷いながらも自分らしく生きようとするすべての人に寄り添う一曲だ。ファンクやポップスをベースにした軽快なグルーヴにのせて、稲葉浩志の歌声は、試練や不安も“人生の彩”だとそっと教えてくれる。
自信をなくしているとき、誰にも気づかれない孤独を感じるとき、それでも前に進みたいと願う人にこそ、この曲を聴いてほしい。自分の人生に、たしかな色を見出したいと思ったときに—「IRODORI」は、きっと力を貸してくれる。

【そわそわする】×「You Got Me So Wrong」
夜遅くまで働き詰めの毎日。誰かのために頑張っているはずなのに、ふと鏡に映る自分の顔が、誰か他人のように感じる瞬間がある。
INABA/SALASの『You Got Me So Wrong』は、そんな“見せている自分”と“隠している自分”の狭間で揺れる感情を、軽快なリズムとともに描き出す一曲だ。
ファンキーでシンプルなサウンドの奥に、複雑な感情が見え隠れする。大人になってからこそ刺さる、この“ほろ苦い逃避願望”を聴き逃さないでほしい。
これが本当の姿じゃないかもよ
A〜Bメロでは「誰かのために頑張る自分」と「その裏にある見えない疲弊やプレッシャー」という、社会人としてのリアルな感情を静かに描き出している。
夜毎遅くまでこの身を粉にして
仕事に精出しあなたを幸せにしてみせる
私に期待を寄せるその視線
裏切るわけにいかない見えないストレス
目に見えないぶん誰にも気づかれず、自分でも処理しきれない心の圧迫感が伝わってくる。優しさや真面目さゆえに、“頑張るしかない”という感情に押し込められてしまっているような息苦しさが伝わってくる。
感情を吐露するというよりも「淡々と」語られている点もポイントだろう。だからこそ、抑えたトーンの裏にある“切実さ”が、静かに、深く響いてくる。
サビでは、“本当の自分ってなんだろう?”というアイデンティティの揺らぎが一気に噴き出していく。
You got me so wrong, you got me so wrong
これが本当の姿じゃないかもよ
You got me so wrong, you got me so wrong
鏡に映るその顔はどんなの
ここで繰り返される “You got me so wrong” は、表面的には「あなたは私のことを間違って理解している」と訳される。
でもこの曲の流れを考えると、“you”は特定の他者ではなく、もっと広い存在―社会全体の期待や、役割に応えようとする日々の自分自身を含んでいると考えられる。
「これが本当の姿じゃないかもよ」というフレーズは、他人に向けた言葉でありつつ、自分への問いかけにも聞こえてくる。
その苦しみは声高に叫ばれることなく、稲葉浩志の表現力とクールなサウンドに静かに溶け込みながら、かえってリアルに、深く心に染みわたっていく。
まとめ
誰かに誤解されたときだけでなく、自分自身を見失いそうになったときにこそ聴いてほしい。
「You Got Me So Wrong」は、心の奥底で揺れている“本当の自分”の声に、そっと耳を澄ませるような一曲だ。
静かなグルーヴと抑えたボーカルが、言葉以上に雄弁に、その迷いや痛みを受け止めてくれる。ふと立ち止まりたくなる夜に、そっと寄り添ってくれるはずだ。

【集中】×「Bloodline」
親から受け継いだ価値観や人生観は、温もりとともに時に“枠”にもなる。正解を教えてくれるその声が、いつの間にか自分の進む道を狭めてはいないか。
INABA/SALASの「Bloodline」は、そんな葛藤を抱えるすべての人に刺さる一曲だ。稲葉浩志の真っ直ぐで切実なボーカルと、スティーヴィー・サラスのグルーヴィーなギターが絡み合い、血のつながりの意味と、その先へ進もうとする決意をエモーショナルに描き出していく。
大切なものをちゃんと受け継ぎながら、でもそれに縛られず、自分の足で新しい世界を切り開きたい」という決意と葛藤を描いた、成長と自立の物語。
家族との距離感に悩んだことがある人、自分の人生を選びたいと願う人の心に深く響く、静かなる決別の歌だ。
まだ見ぬ素晴らしい荒野へ
A〜Bメロは、親の愛情と助言に感じる違和感や息苦しさが表現されている。
パパとママいつだって愛情にあふれ
ああすればいいこうすればいいて教えてくれる
正解を知っているよな口ぶりだけど
狭い選択肢の中のマシな可能性
愛されて育ったけれど、それでもその道が“自分の人生”だとは思えない。親を否定しているのではなく、むしろその愛情を認めた上で、「自分で選びたい」「自分の人生を生きたい」という切実な声が、静かににじみ出ている。
サビ〜ポストコーラスでは、親から受け継いだ“Bloodline/血筋”という名のルーツに敬意を払いながら、それでもなお、その外に広がる“誰も歩いたことのない荒野”へと歩き出そうとする主人公の姿が描かれている。
家の外にゃまだ私の血筋が
歩いたことのない素晴らしい荒野が
まっさらのまま畝り広がる
少々衝撃はしゃあない覚悟して頂戴
Wow yeah, onegai ikasete
Wow, gomenyo mo matenai, let me go
ここに描かれているのは、“反抗”ではない。“冒険”だ。
愛されて育ったからこそ、その愛に守られた世界の外へ、自分自身の足で踏み出すという覚悟の瞬間。まっさらな大地は、先が見えない。でも、それを「素晴らしい」と言い切るところに、未来への希望が宿っている。
それは別れではない。自分自身と向き合い、まだ見ぬ未来へ進むための、はじまりの合図なのだろう。
まとめ
「Bloodline」は、誰かの敷いたレールを丁寧にたどるのではなく、自分自身の足で踏みしめながら“まだ見ぬ荒野”を進んでいく。そんな人生の姿勢を、音楽として提示してくれる一曲だ。
愛と葛藤、決意と不安。そのすべてを抱えて、それでも前へ。そのメッセージは、聴くたびに胸を打つ。
もしあなたが今、何かを選ぼうとしているなら。誰かの期待と、自分の気持ちのあいだで揺れているなら。この曲は、きっと背中を押してくれる。
“自分だけの道”を歩く、その一歩のそばに。この曲は、そんなあなたの人生にきっと寄り添ってくれるだろう。

【希望に満ちた】 ×「Take On Your Love」
INABA/SALAS「Take On Your Love」は、迷いながらも愛に踏み出す、そのリアルな心の動きが、じわりと沁みてくる一曲だ。
タイトルの「Take On Your Love」は、「あなたの愛を引き受ける」という直訳にとどまらず、“愛に挑むこと”、“愛を受け止めること”、そして“愛に飛び込むこと”といった多層的な意味を孕んでいる。
それは、経験を重ねたからこそ生まれる臆病さと、それを乗り越えてなお愛を信じる力、その両方を肯定する言葉だ。
アルバム『Maximum Huavo』の終盤に配置されたこの曲は、ファンキーな演奏と稲葉浩志の真っ直ぐな歌声が響き合い、心の奥をそっとノックしてくるような、エモーショナルな魅力にあふれている。
臆病な心に火を灯す、愛へのジャンプ
A〜Bメロでは、大胆にはなれない、でも、心は確かに動いている—そのリアルな心情が、音と詞の両面から丁寧に紡がれている。
怖いもの知らずも
経験を積んでゆけば
大胆にはなれないもの
自然の定理
どんなに惹かれても
どんなに渇いても
すぐ飛び込むのは無理
そんな私を笑ってあなたは言うでしょう
スティーヴィー・サラスのギターが、感情の機微に寄り添うようにリズムを刻み、ベースとドラムが心の揺れをグルーヴとして可視化する。派手さは抑えつつも、奥行きのあるアンサンブルが、歌詞に込められた葛藤を引き立てている。
惹かれているのに、渇いているのに、すぐには飛び込めない。それは決して臆病ではなく、過去を知っているからこその慎重さ。リスナーはふと自分の姿を重ねてしまうかもしれない。
だからこそ〈そんな私を笑って あなたは言うでしょう〉という一節には、胸を突かれるような切なさがある。
サビでは、迷いながらも愛を選ぼうとする強い意志が、濃縮されて伝わってくる。
Take on your love
諦観にゃ早い
「どうせうまくいかない」「傷つくのが怖いから」と諦めるにはまだ早い。
諦めるには、まだ感情が強く、希望が残っている。
そうした“愛にかける衝動”が「諦観にゃ早い」の一言に凝縮されている。
ブリッジパートでは、戸惑いや慎重さを乗り越えた先にある「もうごまかせない」という心の臨界点が表現されている。
何かが壊れそう
私を変えられるのはあなただけでしょう
最も感情の密度が高まるのがブリッジの2行だ。
〈何かが壊れそう〉という一節は、これまで抑えてきた気持ちがついに溢れ出しそうな、張りつめた空気を孕んでいる。ここで壊れそうなのは、冷静さか、過去の自分か、あるいは“怖がっていた気持ち”そのものかもしれない。
確かなのは、この瞬間に“変化”の気配がはっきりと立ち上がっているということだ。
続く〈私を変えられるのは あなただけでしょう〉という言葉は、核心そのものだ。
これは単なる甘えではなく「自分を変える力を信じられる相手」が目の前にいるという揺るぎない確信だ。
稲葉浩志のボーカルは、感情のふちをなぞるように、静かで力強い。このブリッジがあるからこそ、ラストのサビで響く「Take on your love」が、単なる繰り返しではなく“決意の言葉”として昇華されていく。
まとめ
「Take On Your Love」は、ただ“愛を語る”だけのラブソングではない。経験を重ねた者だけが知る“臆病さ”や“迷い”を、そのまま肯定しながら、それでも一歩踏み出そうとする感情を描いている。
ファンキーで躍動感のある演奏の中に、こんなにも繊細で真っ直ぐな心情が息づいている
愛に迷ったとき、立ち止まりそうになったとき、この曲はそっと「諦観にゃ早い」とささやいてくれる。その言葉に、もう一度だけ“愛を信じてみよう”と思える自分がいる—そんな勇気を与えてくれる一曲だ。

【うわついた】×「CELICA」

曲名にもなっている「CELICA(セリカ)」は、かつてトヨタが製造していたスポーツクーペ。1970年代から2000年代初頭まで販売され、日本だけでなく海外でも人気を博したモデル。丸みを帯びた流線型のボディと、若者の憧れを象徴するスタイリッシュなデザインで、“初めてのマイカー”として記憶に残っている人も多いだろう。
大きな夢が叶うわけでもない。人生を左右するような出来事が起きるわけでもない。それでも、あのとき、そんなセリカに乗って走ったことは、今も忘れられない。
INABA/SALASの楽曲「CELICA」は、そんな“何者にもなれなかった若者たち”の静かな記憶を、優しくすくい上げている一曲だ。
稲葉浩志の実体験をもとに描かれた歌詞は、ライブが飛んで時間を持て余した若者たちが、古びたセリカでただあてもなく走るという、なんでもない一日を切り取っている。
けれどその“なんでもなさ”の中にこそ、言いようのない焦りや、どこにもぶつけられない感情、そしてほんの少しの希望が滲んでいる。
ファンキーで哀愁を帯びたサウンド、スティーヴィー・サラスの提案によって稲葉浩志がエルヴィス・プレスリーを意識した低音ボーカルに挑戦した「稲葉プレスリー」スタイルのボーカルが、その心情をリアルに描き出している。
“意味なんてない”と歌いながら、どこか懐かしさが胸を締めつける―そんな体験が、この曲には詰まっている。
ただ走るだけの日に宿る、名もなき青春の記憶
Aメロでは、「CELICA」という楽曲全体が持つ“静かな青春の記憶”の中で、最もセンシティブな感情が表現されている。
夜明け前の雑魚寝のアパート
電話が震え
誰か囁くように話して
すすり泣いてた
その情景からは、夢や現実、人間関係に揺れる不安定な青春の空気が伝わってくる。セリフはないが、音のない会話が交わされているような、静かで重たい時間が、Aメロには刻まれている。
Bメロは、夢を追う若者が直面する現実の隙間を描いたパートだ。
あいつは実家(いえ)に戻った末に
ライブは飛んじまい
俺たちはヒマ古いセリカで
あてもなく走る
仲間の一人が実家に帰ったことで、予定されていたライブが中止に。夢に向かうはずだったその日が、突然空白になってしまった。
その空白を埋めるように、古いセリカであてもなく走る。ここで描かれるのは、行き場のない情熱と時間。
何かを成し遂げるわけでもなく、ただ車を走らせることで、そのもどかしさや宙ぶらりんな気持ちをやり過ごしている。
セリカという一台の車が、“動けるけれど進めない青春”の象徴として登場している。
サビでは、停滞した青春の一瞬を音にしたような場面が描かれている。何も起きなかったことそのものが、後から思えば“物語”になる―そんな儚さとリアルが、ここに詰まっている。
どうでもいい感じで過ぎる
知らない街のサイン
たいした意味などないよ
時間は売るほどあるよね
あくびが出るくらい
何かが変わる気配、、気配はない
登場する言葉は、どれも淡々としていて、どこか諦めにも似た響きを持っている。でもそこには、不思議なリアリティと、懐かしさが滲んでいる。
「知らない街のサイン」が視界を流れ、「あくびが出るくらい」の退屈が心を支配していく。何かが変わるような気配さえない、けれどそれを誰も否定しない空気。
それでもこの時間は、決して無意味ではない。意味がないからこそ、強く焼き付く記憶がある。変わらなかったからこそ、そこにあった友情や孤独が、何十年経ってもふと蘇るのだ。
ブリッジでは、それまで続いていた“あてもないドライブ”が終わり、ふいに日常へと戻される場面が描かれている。
夕方前に駅前にポトンと落とされて
いつもの通りなのに途方に
暮れたのは何故
「ポトンと落とされて」という表現には、唐突な切断感と、ほんの少しの虚しさがにじんでいる。
何も変わっていないはずなのに、どこか自分だけが取り残されているような感覚。何も起きなかった一日が終わりを迎えたとき、何も変わらない現実が逆に心に刺さる。そんな喪失感が鮮明に描かれている。
夢でも希望でもない時間”を過ごしたあとに、何も変わらない日常がふいに寂しく感じられる。そんな感情がふっとリスナーの心にも浮かんでくる。
それは、青春の終わりでもなく、挫折でもない。ただ、何も起こらなかった一日が、思いのほか心に残っていたことに、走り去るセリカを見送りながら気づいたのだろう。
まとめ
「CELICA」は、大きな夢も劇的な展開も描かない。それでも、何者でもなかった自分たちが確かにそこにいたことを、静かに、でも確かに刻み込んでくれる。
風を切って走るセリカの姿に重ねて思い出すのは、あの退屈だったはずの時間が、今ではもう戻れない“かけがえのない瞬間”だったということだ。
忘れていた自分に、そっと会いに行くような一曲。だからこそ、この曲は今、聴きたくなる。

【楽しい】×「CELEBRATION ~歓喜の使者~」
INABA/SALASの2ndアルバム『Maximum Huavo』。そのラストを飾る「CELEBRATION ~歓喜の使者~」は、単なるエンディングではない。
むしろ“ここから始まる”という希望とエネルギーを感じさせる、まさに「祝祭」の名を冠するにふさわしい一曲だ。
スティーヴィー・サラスのグルーヴィーなギター、そして稲葉浩志の伸びやかで力強いボーカルが絡み合い、聴き手を一気に高揚させる。ファンキーでダンサブルなビートの中に、日常の中で小さな喜びを見つけ出すまなざしや、どんな困難の中でも前を向こうとする強い意志が宿っている。
ラストナンバーでありながら、まるで新しい旅の始まりを告げるかのような―そんな不思議な開放感が、この曲にはある。
今この瞬間を祝おう─ラストを飾る祝祭歌
Aメロでは、困難な状況の中にあっても、希望や価値を見出そうとする強い意志が表現されている。
砂漠の中に落とした一粒の
小さなダイヤモンド見つけ出してみせましょう
何もないように思える日々の中にも、確かに価値あるものが埋まっている。それを、自分の意思で見つけにいくんだというポジティブなメッセージが伝えられている。
サビは、楽曲の核となるメッセージが凝縮された祝福と覚醒のコーラスだ。
朝も昼も夜も関係ない
祝杯をあげよう
歓んでよ
知らん顔はやめにしましょう
友よ今が消えてしまう
その前に
「今」は一瞬で過ぎ去ってしまうからこそ、祝う価値がある。
未来のためでも、過去の清算でもない、“この瞬間”の重みを強く訴えかけている。
今という瞬間に心を開き、感情を惜しまず解き放て―祝うべきことは、ほかでもない“今ここ”にある。そんなメッセージを“友”と呼びかけながら、リスナーにまっすぐ届けている。
明るくファンキーなサウンドに乗せて届けられることで、この言葉の説得力はさらに強まり、ただのポジティブソングではなく、生き方そのものを鼓舞する応援歌として響く。
ブリッジは、楽曲全体の中でもっとも内面的で、主人公の「覚悟」や「使命感」が最も強く表れている。
嵐の中も涙は見せない
希望を探す私は歓喜の使者
誰かのために強くあろうとする姿勢。このフレーズには、稲葉浩志という表現者の人生観や、ステージに立ち続ける者としてのプライドがにじんでいる。
その想いは、リスナー一人ひとりの「自分を保って生きる」姿と呼応し、静かで揺るがぬ強さとなって心に届いてくる。
まとめ
どんなに乾いた世界でも、喜びは確かに存在している―それを見つけ、分かち合おうとする意志こそが、この曲の持つ真の強さだ。
INABA/SALAS「CELEBRATION ~歓喜の使者~」は、単なるラストナンバーではない。嵐の中を進みながら、それでも誰かのために笑おうとするその姿勢に、きっと私たちは励まされている。
祝杯をあげる理由は、目の前にある。
そんな確かな希望を、音楽という形でそっと手渡してくれる―この曲は、そんな“歓喜の使者”のような存在だ。

このアルバムを通して感じたこと
『Maximum Huavo』を初めて聴いたとき、ただ“かっこいい”以上の何かを感じた。
ギターもビートもボーカルも、ジャンルに収まりきらない自由さがあって、どの音にも熱と衝動が宿っていた。けれどそれは一方的にぶつかってくるものではなく、気づけばこちらの心の奥まで入り込んで、静かに揺さぶってくるような感覚だった。
音を浴びるうちに、自分の中の言葉にならない感情が浮かび上がってくる。落ち込んでいた日にも、このアルバムを聴いたら少しだけ前を向けた。
何を言われたわけでもないのに、ただ音だけで気持ちが動く――それがこの作品の強さだと思う。
音が止まったあとの余韻までもが印象的だった。熱が残るような静けさの中で、自分と向き合う時間が生まれる。
『Maximum Huavo』は、ただ聴くだけじゃなく、聴くたびに心が少し変わるようなアルバムだ。
※本記事において引用している歌詞は、すべてINABA/SALASによるアルバム『Maximum Huavo』に収録された楽曲からの一部抜粋です。著作権は各著作権者に帰属しており、当サイトは正当な引用のもとでこれを掲載しています。著作権に配慮して歌詞全文の掲載は行っておりません。



